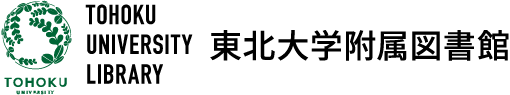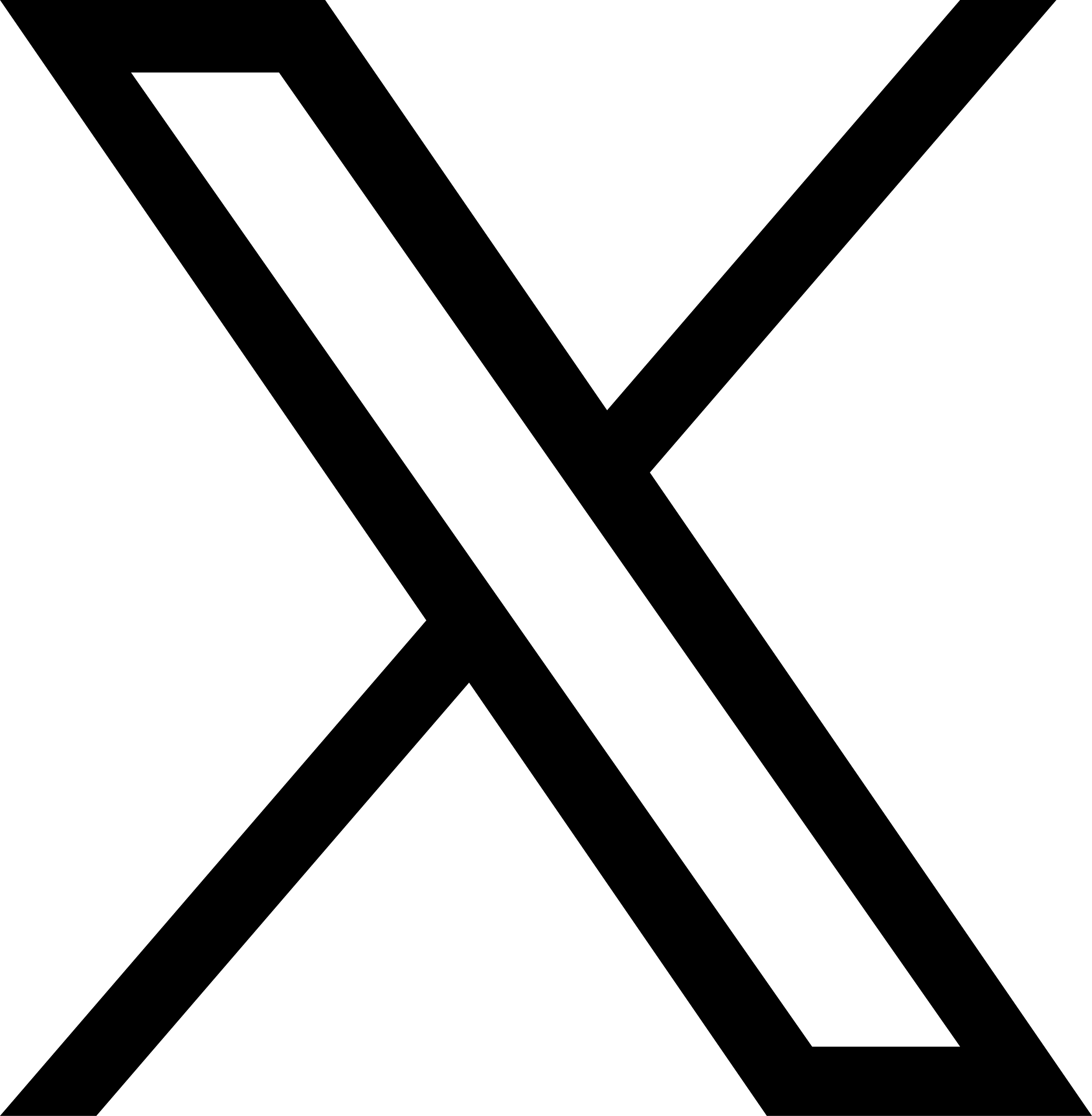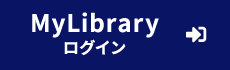Q&A
研究成果(学術論文等)の機関リポジトリへの登録について、よくある質問をまとめています。(※本ページの情報は随時更新されます)
また、リポジトリに登録されたデータは国内外の論文データベース(CiNii Research、国立国会図書館、OpenAIRE、COREなど)に反映されるため、参照される機会が増えることが見込まれます。
※IZUMIの利用方法については、図書館ではお答えできません。情報部へお問い合わせください。
※運用については今後変更される可能性があります。
ただし、次項にあるように、許諾を得た証拠となる文書などが他にある場合は、それを許諾書に代えてご提出いただいても構いません。
・日本の学協会誌:SCPJ:学協会著作権ポリシーデータベース
・海外の学術雑誌:Open policy finder
tour★grp.tohoku.ac.jp (★は@に置き換えてください)
登録の対象
Q:対象論文は最近発表した論文ですか?過去の論文でも対象になりますか?
A:即時オープンアクセスが義務づけられているのは2025年度以降の新規公募分の競争的研究費による研究成果ですが、対象外(研究助成を受けていない論文や過去の論文)であっても、出版社が機関リポジトリへの掲載を認めているものについては随時登録を受け付けております。強制するものではありませんので、著者ご自身が「広く公開したい」と思ったタイミングで登録をご検討ください。Q:自分の論文は出版社のサイトですでにオープンアクセスになっているのですが、登録しなければならないのですか?
A:可能であればぜひお願いします。論文が既に出版社サイトでオープンアクセスとなっていても、万が一、出版社側の都合により公開を持続できなくなった場合、論文へのアクセスが絶たれてしまいます。機関リポジトリにアーカイブすることで、半永久的に論文へのアクセスが可能になります。また、リポジトリに登録されたデータは国内外の論文データベース(CiNii Research、国立国会図書館、OpenAIRE、COREなど)に反映されるため、参照される機会が増えることが見込まれます。
Q:論文の査読にあたって、根拠データをリポジトリ等で公開するようジャーナルから求められています。論文ではないコンテンツを単独で登録できますか?
A:研究データ(根拠データ)の公開には、本学データレイク「IZUMI」(※学内限定)をご利用ください。Q:論文の査読にあたって、研究データを公開の上、DOIを通知するようジャーナルから求められています。どのような手続きを行えばいいですか?
A:リポジトリは研究データ(根拠データ)の登録には対応していませんが、データレイク「IZUMI」(※学内限定)で公開永続化されたデータの外部共有URLに対してDOIを付与できます。まずはIZUMIへ当該のデータを登録し、公開永続化を行った上で、こちらの【DOI付与申請フォーム】から申請してください。(東北大メール(Gmail)でのログインが必要です)※IZUMIの利用方法については、図書館ではお答えできません。情報部へお問い合わせください。
※運用については今後変更される可能性があります。
Q:論文の査読にあたって、プレプリントをリポジトリ等で公開するようジャーナルから求められています。論文を査読者だけが閲覧できるように、ファイルにパスワードを設定するか、URLを知っている人だけアクセスできるようにしたいのですが。
A:リポジトリには、特定の個人にのみ閲覧を可能とする機能はありません。パスワードの設定やURL限定公開などによるアクセス制限を設けたい場合は、データレイク「IZUMI」(※学内限定)をご利用ください。著作権について
Q:共著者がたくさんいます。「登録許諾書」は責任著者の所属と氏名を明記して、一枚だけ提出としてもよいですか。
A:登録依頼者が事前に許諾を得なかったため、リポジトリでの公開を意図していなかった共著者とトラブルになり、公開を取り下げた事例が報告されています。これらのトラブルを避け、共著者間の信頼関係を保つため、全著作権者の承諾を得ることを推奨します。お手数ですが、全員分ご提出ください。ただし、次項にあるように、許諾を得た証拠となる文書などが他にある場合は、それを許諾書に代えてご提出いただいても構いません。
Q:共著者から許諾を得たのですが、「登録許諾書」の様式ではなくメールで回答がきてしまいました。許諾書を改めて依頼しなければなりませんか。
A:同意が確認できる内容であれば、「登録許諾書」の別途提出は不要です。代わりとして、メールの写しをPDFでお送りください。Q:著作権は学会にありますが、規定で学会の許諾を得ることなくリポジトリに公開してよいことになっています。この場合、「登録許諾書」への記入は必要ですか。
A:「登録許諾書」の提出は不要です。「東北大学機関リポジトリ(TOUR)登録依頼書」のみご提出ください。Q:著作権が学会にあるのですが、 編集委員長の名前、または学会長の名前、どちらで書類をもらえばよいですか。
A:当該雑誌の著作権について代表となっている方にご依頼ください。どちらが代表なのかは学会により異なりますので、当該雑誌の事務局へお尋ねください。もし先方でも判断ができない場合は学会長の名前で書類を作成してください。Q:当該雑誌ではクリエイティブ・コモンズ・ライセンス (CC BY)が適用されています。これを見ると、コピーや再配布が認められていて、著作権者に改めてリポジトリ登録の許諾を得る必要がないように思われますが。
A:「登録許諾書」の提出は不要です。「東北大学機関リポジトリ(TOUR)登録依頼書」のみご提出ください。出版社ポリシーについて
Q:図書館側で公開可否は確認していますか。
A:出版社・学会の公開ポリシーがあるものについては、図書館でダブルチェックを行います。ポリシーが不明な場合や投稿時に個別の取り決め等があった場合には、出版社への確認をお願いする場合があります。Q:公開の可否はどのように判断しているのですか。
A:下記データベースおよび出版社や学協会ウェブサイトを確認しています。・日本の学協会誌:SCPJ:学協会著作権ポリシーデータベース
・海外の学術雑誌:Open policy finder
Q:公開できる版にエンバーゴ(公開禁止期間)があるようです。
A:エンバーゴ期間完了後に機関リポジトリで公開するよう、図書館で留意し登録いたします。エンバーゴに関わらずご提出いただいてかまいません。費用について
Q:TOURでオープンアクセスにするにあたり費用はかかりますか。
A:東北大学の機関リポジトリにデータを登録するものなので、費用はかかりません。Q:出版社でオープンアクセスにする(ゴールドOA)ための料金は、図書館が支払ってくれるのですか。
A:残念ながら図書館では、学術雑誌への投稿時のオープンアクセスに関する予算はありません。ゴールドOAにする場合は、ご自身の研究費から支払いをお願いします。 なお、論文投稿時のAPC割引等についての情報はこちらのページをご参照ください。その他
Q:論文や書類はどのように提出すればよいですか。
A:メール添付やGoogleドライブによる共有、ファイル転送サービス等を使用し、附属図書館オープンアクセス推進係までご提出ください。Q:学外に転出した場合、登録した論文はどうなりますか。
A:「東北大学機関リポジトリ(TOUR)運用指針」では、コンテンツを提供できる者として「提供対象コンテンツを生成した時点で、本学に在籍していた者」を含めています。よって転出された後も、継続して公開いたします。このページに関する問い合わせ先
東北大学附属図書館 情報管理課 オープンアクセス推進係tour★grp.tohoku.ac.jp (★は@に置き換えてください)