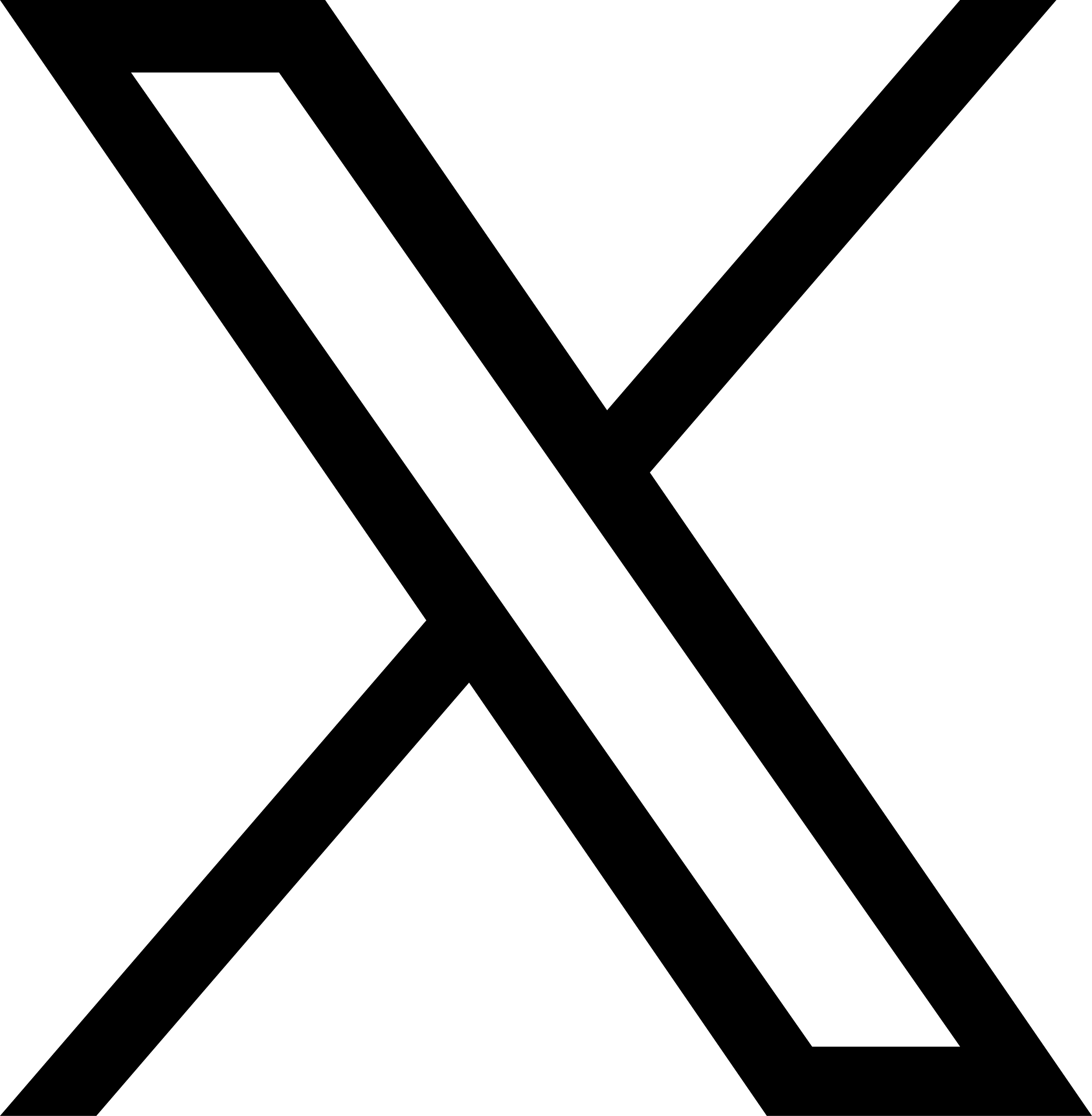жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ
е°ҸиӘ¬еҹ·зӯҶжҷӮд»Јв…Ў
гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»38е№ҙпјҲ1905пјүй ғгҒӢгӮүгҖҒж•ҷеё«гӮ’з¶ҡгҒ‘гӮӢгҒӢгҒқгӮҢгҒЁгӮӮе°ҸиӘ¬е®¶гҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгҖҒиҝ·гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°й–ҖдёӢз”ҹгҒ®гҒІгҒЁгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢдёӯе·қиҠіеӨӘйғҺе®ӣгҒҰгҒ®жҳҺжІ»38е№ҙ7жңҲ15ж—Ҙд»ҳгҒ®жүӢзҙҷгҒ§гҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖе…ҲйҒ”ж—Ҙжң¬ж–°иҒһгҒҢгҒҚгҒҰдҪ•гҒ§гӮӮжҷӮгҖ…гҒӢгҒ‘гҒЁгҒ„гҒөгҒӢгӮүгҖӮеғ•гӮӮгҒӨгҒҸгҒҘгҒҸиҖғгҒёгҒҹгҒӯгҖҒжҜҺж—ҘдёҖ欄жӣёгҒ„гҒҰжҜҺж—ҘеҚҒеҶҶгӮӮгҒҸгӮҢгӮӢгҒӘгӮүеӯҰж ЎгӮ’иҫһиҒ·гҒ—гҒҰж–°иҒһеұӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹж–№гҒҢгҒ„гӮқгҒЁгҖӮ
гҖҖгҒҫгҒҹгҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒ®еҹ·зӯҶеҫҢгҒ®жҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲй ғгҒ«гҒҜгҖҒжјұзҹігҒҜзҹҘдәәгҒҹгҒЎгҒ«е®ӣгҒҰгҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжӣёз°ЎгӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖдҪҷгҒҜеҗҫж–ҮгӮ’д»ҘгҒҰзҷҫд»ЈгҒ®еҫҢгҒ«дјқгҒёгӮ“гҒЁж¬ІгҒҷгӮӢйҮҺеҝғ家гҒӘгӮҠгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүдҪҷгҒҜйҡЈгӮҠиҝ‘жүҖгҒ®иіһиіӣгӮ’жұӮгӮҒгҒҡгҖӮеӨ©дёӢгҒ®дҝЎд»°гӮ’жұӮгӮҖгҖӮеӨ©дёӢгҒ®дҝЎд»°гӮ’жұӮгӮҒгҒҡгҖӮеҫҢдё–гҒ®еҙҮжӢқгӮ’жңҹгҒҷгҖӮжӯӨеёҢжңӣгҒӮгӮӢгҒЁгҒҚдҪҷгҒҜе§ӢгӮҒгҒҰдҪҷгҒ®еҒүеӨ§гҒӘгӮӢгӮ’ж„ҹгҒҡгҖӮ
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ21ж—ҘжЈ®з”°иҚүе№іе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖд»Ҡиҝ„гҒҜе·ұгӮҢгҒ®еҰӮдҪ•гҒ«еҒүеӨ§гҒӘгӮӢгҒӢгӮ’и©ҰгҒҷж©ҹдјҡгҒҢгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮе·ұгӮҢгӮ’дҝЎй јгҒ—гҒҹдәӢгҒҢдёҖеәҰгӮӮгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮжңӢеҸӢгҒ®еҗҢжғ…гҒЁгҒӢзӣ®дёҠгҒ®еҫЎжғ…гҒЁгҒӢгҖҒиҝ‘жүҖиҝ‘иҫәгҒ®еҘҪж„ҸгҒЁгҒӢгӮ’й јгӮҠгҒ«гҒ—гҒҰз”ҹжҙ»гҒ—гӮ„гҒҶгҒЁгҒ®гҒҝз”ҹжҙ»гҒ—гҒҰгӮҗгҒҹгҖӮжҳҜгҒӢгӮүгҒҜгҒқгӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒҜжұәгҒ—гҒҰгҒӮгҒҰгҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮеҰ»еӯҗгӮ„гҖҒиҰӘж—ҸгҒҷгӮүгӮӮгҒӮгҒҰгҒ«гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮдҪҷгҒҜдҪҷдёҖдәәгҒ§иЎҢгҒҸжүҖиҝ„иЎҢгҒӨгҒҰгҖҒиЎҢгҒҚе°ҪгҒ„гҒҹжүҖгҒ§ж–ғгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ23ж—ҘзӢ©йҮҺдәЁеҗүе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖеғ•гҒҜдёҖйқўгҒ«ж–јгҒҰдҝіи«§зҡ„ж–ҮеӯҰгҒ«еҮәе…ҘгҒҷгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«дёҖйқўгҒ«ж–јгҒҰжӯ»гҒ¬гҒӢз”ҹгҒҚгӮӢгҒӢгҖҒе‘ҪгҒ®гӮ„гӮҠгҒЁгӮҠгӮ’гҒҷгӮӢж§ҳгҒӘз¶ӯж–°гҒ®еҝ—еЈ«гҒ®еҰӮгҒҚзғҲгҒ—гҒ„зІҫзҘһгҒ§ж–ҮеӯҰгӮ’гӮ„гҒӨгҒҰиҰӢгҒҹгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒӘгҒ„гҒЁдҪ•гҒ гҒӢйӣЈгӮ’гҒҷгҒҰгӮқжҳ“гҒ«гҒӨгҒҚеҠҮгӮ’еҺӯгҒҶгҒҰй–‘гҒ«иө°гӮӢжүҖи¬Ӯи…°жҠңж–ҮеӯҰиҖ…гҒ®ж§ҳгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҰгҒӘгӮүгӮ“
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ26ж—Ҙд»ҳйҲҙжңЁдёүйҮҚеҗүжӣёз°Ўпјү
гҖҖжҳҺжІ»40е№ҙпјҲ1907пјүгҖҒжјұзҹігҒҜгҒӨгҒ„гҒ«ж•ҷиҒ·гӮ’иҫһгҒ—гҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһзӨҫгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹгҖӮжјұзҹігҒ®е…ҘзӨҫгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒйіҘеұ…зҙ е·қгҖҒжұ иҫәдёүеұұгҖҒжёӢе·қзҺ„иҖігӮүгҒҢй–ўгӮҸгҒЈгҒҹгҖӮд»ҘеҫҢгҖҒжјұзҹігҒ®е°ҸиӘ¬дҪңе“ҒгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰжңқж—Ҙж–°иҒһгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖеӨ§еӯҰж•ҷеё«гҒҢж–°иҒһзӨҫгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒ§гҒҚгҒ”гҒЁгҒҜеҪ“жҷӮгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘи©ұйЎҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӨ§еӯҰгӮ’иҫһгҒ—гҒҰжңқж—Ҙж–°иҒһгҒ«йҖҷе…ҘгҒӨгҒҹгӮүйҖўгҒөдәәгҒҢзҡҶй©ҡгҒ„гҒҹйЎ”гӮ’гҒ—гҒҰеұ…гӮӢгҖӮдёӯгҒ«гҒҜдҪ•ж•…гҒ гҒЁиҒһгҒҸгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеӨ§жұәж–ӯгҒ гҒЁиӨ’гӮҒгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮеӨ§еӯҰгӮ’гӮ„гӮҒгҒҰж–°иҒһеұӢгҒ«гҒӘгӮӢдәӢгҒҢе·ҰзЁӢгҒ«дёҚжҖқиӯ°гҒӘзҸҫиұЎгҒЁгҒҜжҖқгҒҜгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖж–°иҒһеұӢгҒҢе•ҶеЈІгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеӨ§еӯҰеұӢгӮӮе•ҶеЈІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе•ҶеЈІгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒж•ҷжҺҲгӮ„еҚҡеЈ«гҒ«гҒӘгӮҠгҒҹгҒҢгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒӢгӮүгҒҶгҖӮжңҲжЈ’гӮ’дёҠгҒ’гҒҰгӮӮгӮүгҒөеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒӢгӮүгҒҶгҖӮеӢ…д»»е®ҳгҒ«гҒӘгӮӢеҝ…иҰҒгҒҜгҒӘгҒӢгӮүгҒҶгҖӮж–°иҒһгҒҢдёӢеҚ‘гҒҹе•ҶеЈІгҒ§гҒӮгӮҢгҒ°еӨ§еӯҰгӮӮдёӢеҚ‘гҒҹе•ҶеЈІгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҸӘеҖӢдәәгҒЁгҒ—гҒҰе–¶жҘӯгҒ—гҒҰгӮҗгӮӢгҒ®гҒЁгҖҒеҫЎдёҠгҒ§еҫЎе–¶жҘӯгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒЁгҒ®е·®дёҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲгҖҺе…ҘзӨҫгҒ®иҫһгҖҸпјү
гҖҖжҳҺжІ»40е№ҙ3жңҲжң«гҒӢгӮү4жңҲгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒдә¬йғҪгҖҒеӨ§йҳӘгӮ’ж—…иЎҢгҒ—гҒҹгҖӮдә¬йғҪгҒҜгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰгҖҒеӯҗиҰҸгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«иЁӘгӮҢгҒҹең°гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒЁжқҘгҒҰгҖҒгҒңгӮ“гҒ–гҒ„гҒЁдә¬йғҪгӮ’еҗҢгҒҳгӮӮгҒ®гҒЁжҖқгҒӨгҒҹгҒ®гҒҜгӮӮгҒҶеҚҒдә”е…ӯе№ҙгҒ®жҳ”гҒ®гҒӘгӮӢгҖӮеӨҸгҒ®еӨңгҒ®жңҲдёёгҒҚгҒ«д№—гҒҳгҒҰгҖҒжё…ж°ҙгҒ®е ӮгӮ’еҫҳеҫҠгҒ—гҒҰгҖҒжҳҺгҒӢгҒӘгӮүгҒ¬еӨңгҒ®иүІгӮ’гӮҶгҒӢгҒ—гҒҚгӮӮгҒ®гӮқж§ҳгҒ«гҖҒйҒ гҒҸзңјгӮ’еҫ®иҢ«гҒ®еә•гҒ«ж”ҫгҒӨгҒҰгҖҒе№ҫзӮ№гҒ®зҙ…зҮҲгҒ«еӨўгҒ®еҰӮгҒҸжҹ”гҒӢгҒӘгӮӢз©әжғігӮ’зёҰгҒҫгӮқгҒ«й…”гҒҜгҒ—гӮҒгҒҹгӮӢгҒҜгҖҒеҲ¶жңҚгҒ®йҮҰгӮ’зңҹйҚ®гҒЁзҹҘгӮҠгҒӨгӮқгӮӮгҖҒй»„йҮ‘гҒЁеј·гҒІгҒҹгӮӢжҷӮд»ЈгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮзңҹйҚ®гҒҜзңҹйҚ®гҒЁжӮҹгҒӨгҒҹгҒЁгҒҚгҖҒгӮҸгӮҢзӯүгҒҜеҲ¶жңҚгӮ’жҚЁгҒҰгӮқиөӨиЈёгҒ®е„ҳдё–гҒ®дёӯгҒёйЈӣгҒіеҮәгҒ—гҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜиЎҖгӮ’еҳ”гҒ„гҒҰж–°иҒһеұӢгҒЁгҒӘгӮӢгҖҒдҪҷгҒҜе°»гӮ’з«ҜжҠҳгҒӨгҒҰиҘҝеӣҪгҒёеҮәеҘ”гҒҷгӮӢгҖӮеҫЎдә’гҒ®дё–гҒҜеҫЎдә’гҒ«зү©йЁ’гҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҖӮзү©йЁ’гҒ®жҘөеӯҗиҰҸгҒҜгҒЁгҒҶпјҸпјјйӘЁгҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҖӮе…¶йӘЁгӮӮд»ҠгҒҜи…җгӮҢгҒӨгӮқгҒӮгӮӢгҖӮеӯҗиҰҸгҒ®йӘЁгҒҢи…җгӮҢгҒӨгӮқгҒӮгӮӢд»Ҡж—ҘгҒ«иҮігҒӨгҒҰгҖҒгӮҲгӮӮгӮ„гҖҒжјұзҹігҒҢж•ҷеё«гӮ’гӮ„гӮҒгҒҰж–°иҒһеұӢгҒ«гҒӘгӮүгҒҶгҒЁгҒҜжҖқгҒҜгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгӮүгҒҶгҖӮ
пјҲгҖҢдә¬гҒ«зқҖгҒ‘гӮӢеӨ•гҖҚпјү
гҖҖжјұзҹігҒҜжңқж—Ҙж–°иҒһе…ҘзӨҫ第1дҪңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҢиҷһзҫҺдәәиҚүгҖҚпјҲжҳҺжІ»40е№ҙ6жңҲ23ж—ҘпҪһ10жңҲ29ж—ҘпјүгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢдёүи¶ҠгҒ§гҒҜиҷһзҫҺдәәиҚүжөҙиЎЈгӮ’еЈІгӮҠеҮәгҒҷгҖҒзҺүе®қе ӮгҒ§гҒҜиҷһзҫҺдәәиҚүжҢҮијӘгӮ’еЈІгӮҠеҮәгҒҷгҖҒгӮ№гғҶгғјгӮ·гғ§гғігҒ®ж–°иҒһеЈІеӯҗгҒҜгҖҢжјұзҹігҒ®иҷһзҫҺдәәиҚүгҖҚгҒЁиЁҖгҒӨгҒҰжңқж—Ҙж–°иҒһгӮ’еЈІгҒӨгҒҰгҒӮгӮӢгҒҸгҒЁгҒ„гҒөйўЁгҒ«гҖҒдё–й–“гҒ§гҒҜеӨ§йЁ’гҒҺгӮ’гҒ—гҒҹгҖҚпјҲгҖҺеӨҸзӣ®жјұзҹігҖҸпјүгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҖиҷһзҫҺдәәиҚүгҒҜжҜҺж—ҘгҒӢгҒ„гҒҰгӮҗгӮӢгҖӮи—Өе°ҫгҒЁгҒ„гҒөеҘігҒ«гҒқгӮ“гҒӘеҗҢжғ…гӮ’гӮӮгҒӨгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮҢгҒҜе«ҢгҒӘеҘігҒ гҖӮи©©зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢеӨ§дәәгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮеҫізҫ©еҝғгҒҢж¬ д№ҸгҒ—гҒҹеҘігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгҒ„гҒӨгӮ’д»•иҲһгҒІгҒ«ж®әгҒҷгҒ®гҒҢдёҖзҜҮгҒ®дё»ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҶгҒҫгҒҸж®әгҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҠ©гҒ‘гҒҰгӮ„гӮӢгҖӮ然гҒ—еҠ©гҒӢгӮҢгҒ°зҢ¶гҖ…и—Өе°ҫгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜ駄зӣ®гҒӘдәәй–“гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжңҖеҫҢгҒ«е“ІеӯҰгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮжӯӨе“ІеӯҰгҒҜдёҖгҒӨгҒ®гӮ»гӮӘгғӘгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеғ•гҒҜжӯӨгӮ»гӮӘгғӘгғјгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢзӮәгӮҒгҒ«е…ЁзҜҮгӮ’гҒӢгҒ„гҒҰгӮҗгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүжұәгҒ—гҒҰгҒӮгӮ“гҒӘеҘігӮ’гҒ„гӮқгҒЁжҖқгҒӨгҒЎгӮ„гҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮ
пјҲжҳҺжІ»40е№ҙ7жңҲ19ж—Ҙе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
гҖҖгҖҢиҷһзҫҺдәәиҚүгҖҚгҒ®еҫҢгҒҜгҖҒгҖҢеқ‘еӨ«гҖҚпјҲжҳҺжІ»41е№ҙ1жңҲ1ж—ҘпҪһ4жңҲ6ж—ҘпјүгҖҒгҖҢеӨўеҚҒеӨңгҖҚпјҲжҳҺжІ»41е№ҙ7жңҲ25ж—ҘпҪһ8жңҲпјүгҖҒз¶ҡгҒ‘гҒҰгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚпјҲжҳҺжІ»41е№ҙ9жңҲ1ж—ҘпҪһ12жңҲ29ж—ҘпјүгҖҒгҖҢгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҖҚпјҲжҳҺжІ»42е№ҙ6жңҲ27ж—ҘпҪһ10жңҲ14ж—ҘпјүгҖҒгҖҢй–ҖгҖҚпјҲжҳҺжІ»43е№ҙ3жңҲ1ж—ҘпҪһ6жңҲ12ж—ҘпјүгҒ®гҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеүҚжңҹдёүйғЁдҪңгҖҚгӮ’йҖЈијү гҒҷгӮӢгҖӮзү№гҒ«гҖҺдёүеӣӣйғҺгҖҸгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢдёүеӣӣйғҺгҒЁдёҺж¬ЎйғҺгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒ«гҒҜгҖҒеӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ®жјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒЁгҒ®й–ўдҝӮгҒҢеҸҚжҳ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгӮӢгҖӮ
гҖҖйЎҢеҗҚвҖ•гҖҢйқ’е№ҙгҖҚгҖҢжқұиҘҝгҖҚгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҖҢе№ігҖ…ең°гҖҚ еҸігҒ®гҒҶгҒЎеҫЎжҠһгҒҝиў«дёӢеәҰеҖҷгҖӮе°Ҹз”ҹгҒ®гҒҜгҒҳгӮҒгҒӨгҒ‘гҒҹеҗҚгҒҜдёүеӣӣйғҺгҒ«еҖҷгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚе°ӨгӮӮе№іеҮЎгҒ«гҒҰгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒЁеӯҳеҖҷгҖӮгҒҹгӮһгҒӮгҒҫгӮҠиӘӯгӮ“гҒ§иҰӢгҒҹгҒ„ж°—гҒҜиө·гӮҠз”ігҒҷгҒҫгҒҳгҒҸгҒЁгӮӮиҰҡеҖҷгҖӮ
гҖҖз”°иҲҺгҒ®й«ҳзӯүеӯҰж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰеӨ§еӯҰгҒ«йҖҷе…ҘгҒӨгҒҹдёүеӣӣйғҺгҒҢж–°гӮүгҒ—гҒ„з©әж°—гҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҖӮгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰеҗҢиј©гҒ гҒ®е…Ҳиј©гҒ гҒ®иӢҘгҒ„еҘігҒ гҒ®гҒ«жҺҘи§ҰгҒ—гҒҰгҖҒиүІгҖ…гҒ«еӢ•гҒ„гҒҰжқҘгӮӢгҖӮжүӢй–“гҒҜжӯӨз©әж°—гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«жҳҜзӯүгҒ®дәәй–“гӮ’ж”ҫгҒҷдёҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгҒЁгҒҜдәәй–“гҒҢеӢқжүӢгҒ«жіігҒ„гҒ§гҖҒиҮӘгҒӢгӮүжіўзҖҫгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒ гӮүгҒҶгҒЁжҖқгҒҶгҖӮ
пјҲжҳҺжІ»41е№ҙжёӢе·қзҺ„иҖіе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜжһңзү©гҒҢеҘҪгҒҚгҒ гҒӨгҒҹгҖӮдё”гҒӨгҒ„гҒҸгӮүгҒ§гӮӮйЈҹгҒёгӮӢз”·гҒ гҒӨгҒҹгҖӮгҒӮгӮӢжҷӮеӨ§гҒҚгҒӘжЁҪжҹҝгӮ’еҚҒе…ӯйЈҹгҒӨгҒҹдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮдҪ•гҒЁгӮӮгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮиҮӘеҲҶжҠ”гҒҜеҲ°еә•еӯҗиҰҸгҒ®зңҹдјјгҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒ„гҖӮвҖ•дёүеӣӣйғҺгҒҜ笑гҒӨгҒҰиҒһгҒ„гҒҰгӮҗгҒҹгҖӮгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮеӯҗиҰҸгҒ®и©ұдёҲгҒ«гҒҜиҲҲе‘ігҒҢгҒӮгӮӢж§ҳгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҹгҖӮ
пјҲгҖҺдёүеӣӣйғҺгҖҸпјү
гҖҖиүІгҖ…гҒӘж„Ҹе‘ігҒ«ж–јгҒҰгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҒ«гҒҜеӨ§еӯҰз”ҹгҒ®дәӢгӮ’жҸҸгҒҹгҒҢгҖҒжӯӨе°ҸиӘ¬гҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒӢгӮүе…ҲгҒ®дәӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҒ®дё»дәәе…¬гҒҜгҒӮгҒ® йҖҡгӮҠеҚҳзҙ”гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӯӨдё»дәәе…¬гҒҜгҒқгӮҢгҒӢгӮүеҫҢгҒ®з”·гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүжӯӨзӮ№гҒ«ж–јгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯӨдё»дәәе…¬гҒҜжңҖеҫҢгҒ«гҖҒеҰҷгҒӘйҒӢе‘ҪгҒ«йҷҘгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ•гҒҚдҪ•гҒҶгҒӘгӮӢгҒӢгҒҜжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжӯӨж„Ҹе‘ігҒ«ж–јгҒҰгӮӮдәҰгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲгҖҺгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҖҸдәҲе‘Ҡпјү
гҖҖжӢқеҫ©гҖӮи‘үжӣёгӮ’гҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҖӮгҖҢй–ҖгҖҚгҒҢеҮәгҒҹгҒЁгҒҚгҒӢгӮүд»Ҡж—ҘгҒҫгҒ§иӘ°гӮӮдҪ•гӮӮгҒ„гҒӨгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜдёҖдәәгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜиҝ‘й ғеӯӨзӢ¬гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«ж…ЈгӮҢгҒҰиҠёиЎ“дёҠгҒ®еҗҢжғ…гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ§гӮӮгҒ©гҒҶгҒӢгҒ“гҒҶгҒӢжҡ®гӮүгҒ—гҒҰиЎҢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҫ“гҒӨгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®дҪңзү©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиіһиіӣгҒ®еЈ°гҒӘгҒ©гҒҜе…ЁгҒҸдәҲжңҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҢй–ҖгҖҚгҒ®дёҖйғЁеҲҶгҒҢиІҙж–№гҒ«иӘӯгҒҫгӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҰиІҙж–№гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’иІҙж–№гҒ®еҸЈгҒӢгӮүиҒһгҒҸгҒЁе¬үгҒ—гҒ„жәҖи¶ігҒҢ湧гҒ„гҒҰеҮәгҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲеӨ§жӯЈе…ғе№ҙ10жңҲ12ж—ҘйҳҝйғЁж¬ЎйғҺе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖжҳҺжІ»42е№ҙпјҲ1909пјүгҖҒжјұзҹігҒҜдёӯжқ‘жҳҜе…¬гҒ®жӢӣеҫ…гҒ§жәҖе·һгҖҒжңқй®®гӮ’ж—…иЎҢгҒ—гҖҒгҖҢжәҖйҹ“гҒЁгҒ“гӮҚгҒ©гҒ“гӮҚгҖҚгҒ«гҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгҖӮ
гҖҖжҳҺжІ»43е№ҙпјҲ1910пјү3жңҲгҒӢгӮү6жңҲгҒҫгҒ§гҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһгҒ«гҖҺй–ҖгҖҸгӮ’йҖЈијүгҒ—гҒҹгҖӮйҖЈијүзөӮдәҶеҫҢгҖҒжјұзҹігҒҜиғғжҪ°зҳҚгҒ®гҒҹгӮҒе…ҘйҷўгҒҷгӮӢгҖӮ8жңҲгҒ«гҒҜгҖҒи»ўең°зҷӮйӨҠгҒ®гҒҹгӮҒдјҠиұҶгҒ®дҝ®е–„еҜәжё©жіүгҒ«еҗ‘гҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—е®ҝгҒ«еҲ°зқҖгҒ—гҒҹзҝҢж—ҘгҒӢгӮүз—…зҠ¶гҒҢжӮӘеҢ–гҒ—гҖҒ8жңҲ24ж—ҘгҒ«гҒҜеӨ§йҮҸгҒ®еҗҗиЎҖгӮ’гҒ—еҚұзҜӨзҠ¶ж…ӢгҒ«йҷҘгҒЈгҒҹгҖӮгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢдҝ®е–„еҜәгҒ®еӨ§жӮЈгҖҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ жјұзҹігҒҜгҒ“гҒ®гҒЁгҒҚгҒ®зҠ¶ж…ӢгӮ’гҖҢдёүеҚҒеҲҶгҒ®жӯ»гҖҚгҒЁе‘јгҒігҖҒгҒӨгҒҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°жҮҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеј·гҒІгҒҰеҜҗиҝ”гӮҠгӮ’еҸігҒ«жү“гҒҹгҒҶгҒЁгҒ—гҒҹдҪҷгҒЁгҖҒжһ•е…ғгҒ®йҮ‘зӣҘгҒ«й®®иЎҖгӮ’иӘҚгӮҒгҒҹдҪҷгҒЁгҒҜгҖҒдёҖеҲҶгҒ®йҡҷгӮӮгҒӘгҒҸйҖЈз¶ҡгҒ—гҒҰгӮҗгӮӢгҒЁгҒ®гҒҝдҝЎгҒҳгҒҰгӮҗгҒҹгҖӮе…¶й–“гҒ«гҒҜдёҖжң¬гҒ®й«ӘжҜӣгӮ’жҢҹгӮҖдҪҷең°гҒ®гҒӘгҒ„иҝ„гҒ«гҖҒиҮӘиҰҡгҒҢеғҚгҒ„гҒҰжқҘгҒҹгҒЁгҒ®гҒҝеҝғеҫ—гҒҰгӮҗгҒҹгҖӮзЁӢзөҢгҒҰеҰ»гҒӢгӮүгҖҒе·Ұж§ҳгҒўгӮ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖҒгҒӮгҒ®жҷӮдёүеҚҒеҲҶиЁұгӮҠгҒҜжӯ»гӮ“гҒ§е…ҘгӮүгҒ—гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҒЁиҒһгҒ„гҒҹжҠҳгҒҜе…ЁгҒҸй©ҡгҒ„гҒҹгҖӮ пјҲдёӯз•Ҙпјүе®ҹгӮ’дә‘гҒөгҒЁжӯӨзөҢйЁ“вҖ•з¬¬дёҖзөҢйЁ“гҒЁдә‘гҒІеҫ—гӮӢгҒӢгӮһз–‘е•ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжҷ®йҖҡгҒ®зөҢйЁ“гҒЁзөҢйЁ“гҒ®й–“гҒ«жҢҹгҒҫгҒӨгҒҰжҜ«гӮӮе…¶йҖЈзөҗгӮ’еҰЁгҒ’еҫ—гҒӘгҒ„гҒ»гҒ©еҶ…е®№гҒ«д№ҸгҒ—гҒ„жӯӨвҖ•дҪҷгҒҜдҪ•гҒЁдә‘гҒӨгҒҰгҒқгӮҢгӮ’еҪўе®№гҒ—гҒҰеҸҜгҒ„гҒӢйҒӮгҒ«иЁҖи‘үгҒ«зӘ®гҒ—гҒҰд»•иҲһгҒөгҖӮдҪҷгҒҜзң гӮҠгҒӢгӮүйҶ’гӮҒгҒҹгҒЁгҒ„гҒөиҮӘиҰҡгҒ•гҒёгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮйҷ°гҒӢгӮүйҷҪгҒ«еҮәгҒҹгҒЁгӮӮжҖқгҒҜгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮеҫ®гҒӢгҒӘзҫҪйҹігҖҒйҒ гҒҚгҒ«еҺ»гӮӢзү©гҒ®йҹҝгҖҒйҖғгҒ’гҒҰиЎҢгҒҸеӨўгҒ®еҢӮгҒІгҖҒеҸӨгҒ„иЁҳжҶ¶гҒ®еҪұгҖҒж¶ҲгҒҲгӮӢеҚ°иұЎгҒ®еҗҚж®ӢвҖ•еҮЎгҒҰдәәй–“гҒ®зҘһз§ҳгӮ’еҸҷиҝ°гҒҷгҒ№гҒҚиЎЁзҸҫгӮ’ж•°гҒҲе°ҪгҒ—гҒҰжјёгҒҸй«Јй«ҙгҒҷгҒ№гҒҚйңҠеҰҷгҒӘеўғз•ҢгӮ’йҖҡйҒҺгҒ—гҒҹгҒЁгҒҜз„Ўи«–иҖғгҒёгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮгҒҹгӮһиғёиӢҰгҒ—гҒҸгҒӘгҒӨгҒҰжһ•гҒ®дёҠгҒ®й ӯгӮ’еҸігҒ«еӮҫгҒ‘ж§ҳгҒЁгҒ—гҒҹж¬ЎгҒ®зһ¬й–“гҒ«гҖҒиөӨгҒ„иЎҖгӮ’йҮ‘зӣҘгҒ®еә•гҒ«иӘҚгӮҒгҒҹдёҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…¶й–“гҒ«е…ҘгӮҠиҫјгӮ“гҒ дёүеҚҒеҲҶгҒ®жӯ»гҒҜгҖҒжҷӮй–“гҒӢгӮүдә‘гҒӨгҒҰгӮӮгҖҒз©әй–“гҒӢгӮүдә‘гҒӨгҒҰгӮӮзөҢйЁ“гҒ®иЁҳжҶ¶гҒЁгҒ—гҒҰе…ЁгҒҸдҪҷгҒ«еҸ–гҒӨгҒҰеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҒЁдёҖиҲ¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҰ»гҒ®иӘ¬жҳҺгӮ’иҒһгҒ„гҒҹжҷӮдҪҷгҒҜжӯ»гҒЁгҒҜеӨ«зЁӢжһңж•ўгҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒӨгҒҹгҖӮгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰдҪҷгҒ®й ӯгҒ®дёҠгҒ«гҒ—гҒӢгҒҸеҚ’然гҒЁй–ғгҒ„гҒҹз”ҹжӯ»дәҢйқўгҒ®еҜҫз…§гҒ®гҖҒеҰӮдҪ•гҒ«гӮӮжҖҘеҠҮгҒ§дё”жІЎдәӨжёүгҒӘгҒ®гҒ«ж·ұгҒҸж„ҹгҒҳгҒҹгҖӮ
пјҲгҖҢжҖқгҒІеҮәгҒҷдәӢгҒӘгҒ©гҖҚпјү
гҖҖгҒҫгҒҹжҳҺжІ»44е№ҙ2жңҲгҖҒж–ҮйғЁзңҒгҒӢгӮүеҚҡеЈ«еҸ·жҺҲдёҺгҒ®йҖҡйҒ”гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжјұзҹігҒҜгҒ“гӮҢгӮ’иҫһйҖҖгҒ—гҒҹгҒҹгӮҒеҚҡеЈ«еҸ·жҺҲдёҺгӮ’е·ЎгҒЈгҒҰдәӢж…ӢгҒҢзҙӣзіҫгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖеҚҡеЈ«еҲ¶еәҰгҒҜеӯҰе•ҸеҘЁеҠұгҒ®е…·гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж”ҝеәңгҒӢгӮүиҰӢгӮҢгҒ°жңүеҠ№гҒ«йҒ•гҒІгҒӘгҒ„гҖӮгҒ‘гӮҢгҒ©гӮӮдёҖеӣҪгҒ®еӯҰиҖ…гӮ’жҢҷгҒ’гҒҰжӮүгҒҸеҚҡеЈ«гҒҹгӮүгӮ“гҒҢгҒҹгӮҒгҒ«еӯҰе•ҸгӮ’гҒҷгӮӢгҒЁдә‘гҒөж§ҳгҒӘж°—йўЁгӮ’йӨҠжҲҗгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеҸҲгҒҜе·Ұж§ҳжҖқгӮҸгӮҢгӮӢзЁӢгҒ«гӮӮжҘөз«ҜгҒӘеӮҫеҗ‘гӮ’еёҜгҒігҒҰгҖҒеӯҰиҖ…гҒҢиЎҢеӢ•гҒҷгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒеӣҪ家гҒӢгӮүиҰӢгҒҰгӮӮејҠе®ігҒ®еӨҡгҒ„гҒ®гҒҜзҹҘгӮҢгҒҰгӮҗгӮӢгҖӮдҪҷгҒҜеҚҡеЈ«еҲ¶еәҰгӮ’з ҙеЈҠгҒ—гҒӘгҒ‘гҒ°гҒӘгӮүгӮ“гҒЁгҒҜиҝ„гҒҜиҖғгҒёгҒӘгҒ„гҖӮ然гҒ—еҚҡеЈ«гҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еӯҰиҖ…гҒ§гҒӘгҒ„ж§ҳгҒ«гҖҒдё–й–“гӮ’жҖқгҒҜгҒӣгӮӢзЁӢеҚҡеЈ«гҒ«дҫЎеҖӨгӮ’иіҰдёҺгҒ—гҒҹгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеӯҰе•ҸгҒҜе°‘ж•°гҒ®еҚҡеЈ«гҒ®е°Ӯжңүзү©гҒЁгҒӘгҒӨгҒҰгҖҒеғ…гҒӢгҒӘеӯҰиҖ…зҡ„иІҙж—ҸгҒҢгҖҒеӯҰжЁ©гӮ’жҺҢжҸЎгҒ—е°ҪгҒҷгҒ«иҮігӮӢгҒЁе…ұгҒ«гҖҒйҒёгҒ«жҙ©гӮҢгҒҹгӮӢд»–гҒҜе…ЁгҒҸй–‘еҚҙгҒ•гӮҢгӮӢгҒ®зөҗжһңгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҺӯгҒөгҒ№гҒҚејҠе®ігҒ®з¶ҡеҮәгҒӣгӮ“дәӢгӮ’дҪҷгҒҜеҲҮгҒ«жҶӮгҒөгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮдҪҷгҒҜжӯӨж„Ҹе‘ігҒ«ж–јгҒҰд»ҸиҳӯиҘҝгҒ«гӮўгӮ«гғҮгғҹгғјгҒ®гҒӮгӮӢдәӢгҒҷгӮүгӮӮеҝ«гӮҲгҒҸжҖқгҒӨгҒҰеұ…гӮүгҒ¬гҖӮ
гҖҖеҫ“гҒӨгҒҰдҪҷгҒ®еҚҡеЈ«гӮ’иҫһйҖҖгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜеҫ№й ӯеҫ№е°ҫдё»зҫ©гҒ®е•ҸйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲгҖҢеҚҡеЈ«е•ҸйЎҢгҒ®жҲҗиЎҢгҖҚпјү
гҖҖжҳҺжІ»45е№ҙпјҲ1912пјү1жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҺеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҸгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰе°ҸиӘ¬гҒ®еҹ·зӯҶгӮ’еҶҚй–ӢгҒҷгӮӢгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҚгӮ’йҖЈијүгҒҷгӮӢгҒ«гҒӮгҒҹгҒЈгҒҰгҖҢиҮӘеҲҶгҒ®жӣёгҒҸгӮӮгҒ®гӮ’жҜҺж—Ҙж—ҘиӘІгҒ®гӮ„гҒҶгҒ«гҒ—гҒҰиӘӯгӮ“гҒ§е‘үгӮҢгӮӢиӘӯиҖ…гҒ®еҘҪж„ҸгҒ гҒ®гҒ«гҖҒй…¬гҒ„гҒӘгҒҸгҒҰгҒҜжёҲгҒҫгҒӘгҒ„гҖҚпјҲгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҒ«е°ұгҒ„гҒҰгҖҚпјүгҒЁиӘһгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜе…ғж—ҘгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгҒҰгҖҒеҪјеІёйҒҺиҝ„жӣёгҒҸдәҲе®ҡгҒ гҒӢгӮүеҚҳгҒ«гҒқгҒҶеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹиҝ„гҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„е®ҹгҒҜз©әгҒ—гҒ„жЁҷйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӢгҒӯгҒҰгҒӢгӮүиҮӘеҲҶгҒҜеҖӢгҖ…гҒ®зҹӯз·ЁгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹжң«гҒ«гҖҒе…¶гҒ®еҖӢгҖ…гҒ®зҹӯз·ЁгҒҢзӣёеҗҲгҒ—гҒҰдёҖй•·з·ЁгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«д»•зө„гӮ“гҒ гӮүгҖҒж–°иҒһе°ҸиӘ¬гҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеӨ–йқўзҷҪгҒҸиӘӯгҒҫгӮҢгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ’жҢҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҢгҖҒгҒӨгҒ„гҒқгӮҢгӮ’и©ҰгҒҝгӮӢж©ҹдјҡгӮӮгҒӘгҒҸгҒҰд»Ҡж—Ҙиҝ„йҒҺгҒҺгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒгӮӮгҒ—иҮӘеҲҶгҒ®жүӢйҡӣгҒҢиЁұгҒҷгҒӘгӮүгҒ°жӯӨгҒ®гҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҚгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰгҒ®жҖқгҒҜгҒҸйҖҡгӮҠгҒ«дҪңгӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
пјҲгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҒ«е°ұгҒ„гҒҰгҖҚпјү

еӨ§жӯЈ3е№ҙгҒ®жјұзҹіпјҲгҖҢзЎқеӯҗжҲёгҒ®дёӯгҖҚеҹ·зӯҶй ғпјү
гҖҖз¶ҡгҒ„гҒҰгҖҢиЎҢдәәгҖҚпјҲеӨ§жӯЈе…ғе№ҙ1жңҲ12ж—ҘпҪһеӨ§жӯЈ2е№ҙ11жңҲ17ж—ҘпјүгҖҒгҖҢгҒ“гӮқгӮҚгҖҚпјҲеӨ§жӯЈ3е№ҙ4жңҲ20ж—ҘпҪһ8жңҲ11ж—ҘпјүгҒЁгҖҒгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеҫҢжңҹдёүйғЁдҪңгҖҚгӮ’е®ҢжҲҗгҒ•гҒӣгҖҒ еӨ§жӯЈ4е№ҙпјҲ1915пјүгҒ«гҒҜгҖҒиҮӘдјқзҡ„иҰҒзҙ гҒ®еј·гҒ„гҖҢйҒ“иҚүгҖҚпјҲеӨ§жӯЈ4е№ҙ6жңҲ3ж—ҘпҪһ9жңҲ14ж—ҘпјүгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҹгҖӮз¶ҡгҒҸеӨ§жӯЈ5е№ҙ5жңҲгҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҖҢжҳҺжҡ—гҖҚпјҲеӨ§жӯЈ5е№ҙ5жңҲ26 ж—ҘпҪһ12жңҲ14ж—ҘпјүгӮ’йҖЈијүгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖ еғ•гҒҜдёҚзӣёеӨүгҖҢжҳҺжҡ—гҖҚгӮ’еҚҲеүҚдёӯжӣёгҒ„гҒҰгӮҗгҒҫгҒҷгҖӮеҝғжҢҒгҒҜиӢҰз—ӣгҖҒеҝ«жҘҪгҖҒеҷЁжў°зҡ„гҖҒгҒ“гҒ®дёүгҒӨгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰгӮҗгҒҫгҒҷгҖӮеӯҳеӨ–ж¶јгҒ—гҒ„гҒ®гҒҢдҪ•гӮҲгӮҠд»•еҗҲгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮжҜҺж—Ҙзҷҫеӣһиҝ‘гҒҸгӮӮгҒӮгӮ“гҒӘдәӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгӮҗгӮӢгҒЁеӨ§гҒ„гҒ«дҝ—дәҶгҒ•гӮҢгҒҹеҝғжҢҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§дёүгҖҒеӣӣж—ҘеүҚгҒӢгӮүеҚҲеҫҢгҒ®ж—ҘиӘІгҒЁгҒ—гҒҰжјўи©©гӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—ҘгҒ«дёҖгҒӨдҪҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰдёғиЁҖеҫӢгҒ§гҒҷгҖӮдёӯгҖ…гҒ§гҒҚгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮеҺӯгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒҷгҒҗе·ІгӮҒгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҒ„гҒҸгҒӨеҮәжқҘгӮӢгҒӢеҲҶгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
пјҲеӨ§жӯЈ5е№ҙ8жңҲ21ж—Ҙд№…зұіжӯЈйӣ„гғ»иҠҘе·қйҫҚд№Ӣд»ӢгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—еӨ§жӯЈ5е№ҙпјҲ1916пјү11жңҲдёӢж—¬гҖҒжјұзҹігҒҜиғғжҪ°зҳҚгӮ’еҶҚзҷәгҒ•гҒӣгҖҒз—…еәҠгҒ«гҒӨгҒҸгҖӮгҒқгҒ—гҒҰ12жңҲ9ж—ҘгҖҒгҖҺжҳҺжҡ—гҖҸгӮ’жңӘе®ҢгҒ®гҒҫгҒҫж®ӢгҒ—гҖҒж°ёзң гҒ—гҒҹгҖӮ
- в– еҸӮиҖғж–ҮзҢ®
- в– гҖҢжјұзҹігҒ®з”ҹж¶ҜгҖҚеҗ„гғҡгғјгӮёгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢжјұзҹігҒҠгӮҲгҒіеӯҗиҰҸгҒ®еҶҷзңҹгҒҜгҖҒзҘһеҘҲе·қиҝ‘д»Јж–ҮеӯҰйӨЁгҖҒжқҫеұұеёӮз«ӢеӯҗиҰҸиЁҳеҝөеҚҡзү©йӨЁгҖҒи—Өз”°дёүз”·з·ЁйӣҶдәӢеӢҷжүҖгӮҲгӮҠжҸҗдҫӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҶҷзңҹгҒ®з„Ўж–ӯи»ўијүгӮ’зҰҒгҒҳгҒҫгҒҷгҖӮ
- в– жң¬зЁҝгҒҜгҖҒгҖҺе№іжҲҗ15е№ҙеәҰжқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁдјҒз”»еұ•гҖҖжҳҺжІ»гғ»еӨ§жӯЈжңҹгҒ®ж–ҮдәәгҒҹгҒЎвҖҗжјұзҹігӮ’гҒЁгӮҠгҒҫгҒҸдәәгҖ…вҖҗгҖҸеұ•зӨәдјҡеӣійҢІгҖҒгҖҢжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҖҚгҒ«еҠ зӯҶгғ»дҝ®жӯЈгӮ’ж–ҪгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ