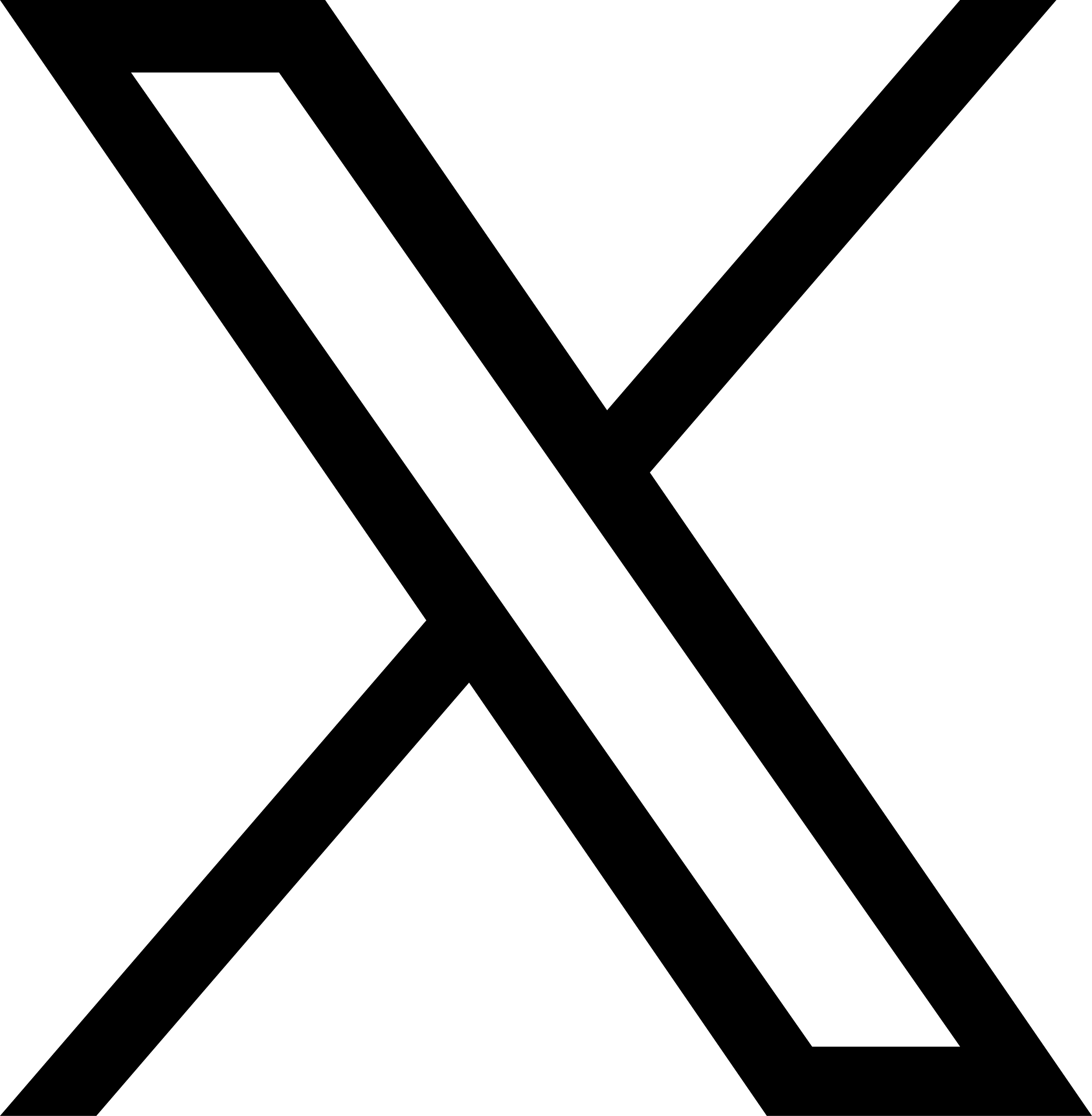жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ
еӯҰз”ҹжҷӮд»Ј
жјұзҹігҒЁжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҒ®еҮәдјҡгҒ„гҒЁдәӨжөҒ
гҖҖжҳҺжІ»17е№ҙпјҲ1884пјү9жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜжқұдә¬еӨ§еӯҰдәҲеӮҷй–ҖдәҲ科пјҲжҳҺжІ»19е№ҙ4жңҲгҖҒ第дёҖй«ҳзӯүдёӯеӯҰж ЎгҒ«ж”№з§°пјүгҒ«е…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢзҙҡгҒ«гҒҜгҖҒжӯЈеІЎеёёеүҮпјҲеӯҗиҰҸпјүгҖҒеҚ—ж–№зҶҠжҘ гҖҒеұұз”°жӯҰеӨӘйғҺпјҲзҫҺеҰҷпјүгҖҒиҠіиіҖзҹўдёҖгӮүгҖҒеҫҢгҒ«дҝідәәгӮ„еӯҰиҖ…гҖҒдҪң家гҒЁгҒ—гҒҰжҙ»иәҚгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢдәәзү©гӮүгҒҢгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖж–ҮеӯҰзҡ„гҒӘеҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒ—гҒӮгҒЈгҒҹжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒ гҒҢгҖҒеҪ“еҲқгҖҒдәҢдәәгҒҜиҰӘгҒ—гҒҸдәӨгӮҸгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгӮҲгҒҶгҒ гҖӮ
гҖҖжӯЈеІЎеӯҗиҰҸпјҲжң¬еҗҚеёёиҰҸгҖҒе№јеҗҚеҮҰд№ӢеҠ©гҖҒгҒ®гҒЎгҒ«еҚҮгҒЁж”№еҗҚпјүгҒҜгҖҒж…¶еҝң3е№ҙпјҲ1867пјү9жңҲ17ж—ҘпјҲйҷ°жҡҰпјүгҖҒдјҠдәҲеӣҪжё©жіүйғЎи—ӨеҺҹж–°з”әпјҲзҸҫеңЁгҖҒжқҫеұұеёӮиҠұең’з”әпјүгҒ«з”ҹгҒҫгӮҢгҒҹгҖӮзҲ¶гҒҜжқҫеұұи—©еЈ«гҒ®еёёе°ҡгҖҒжҜҚгҒҜжқҫеұұи—©гҒ®е„’еӯҰиҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹеӨ§еҺҹиҰіеұұгҒ®й•·еҘігғ»е…«йҮҚгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—зҲ¶гҒҜиӢҘгҒҸгҒ—гҒҰжӯ»еҺ»гҒ—гҒҹгҒҹгӮҒгҖҒеӯҗиҰҸгҒЁеҰ№гҒ®еҫӢгҒҜгҖҒжҜҚгҒЁеӨ§еҺҹ家гҒ®еәҮиӯ·гҒ®гӮӮгҒЁгҒ«жҲҗй•·гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮзү№гҒ«зҘ–зҲ¶гғ»иҰіеұұгҒҜгҖҒе№јгҒ„еӯҗиҰҸгҒ«жјўж–Үгғ»жјўи©©гҒ®зҙ иӘӯгӮ’ж•ҷгҒҲгӮӢгҒӘгҒ©еӨ§еӨүгҒ«еҸҜж„ӣгҒҢгӮҠгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҖҢеҫҢжқҘеӯҰиҖ…гҒЁгҒӘгӮҠгҒҰзҝҒгҒ®еҸігҒ«еҮәгҒ§гӮ“гҒЁжҖқгҒёгӮҠгҖҚпјҲгҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸпјүгҒЁиӘһгӮӢгҒ»гҒ©гҖҒиҰіеұұгҒ«жҶ§жҶ¬гҒ®еҝөгӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҜҚгғ»е…«йҮҚгҒҜе№је°‘гҒ®еӯҗиҰҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢе°ҸгҒ•гҒ„жҷӮеҲҶгҒ«гҒҜгӮҲгҒӨгҒҪгҒ©гҒёгҒјгҒ§пјҸпјјејұе‘іеҷҢгҒ§гҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүзө„гҒ®иҖ…гҒӘгҒ©гҒ«гҒ„гҒўгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгӮӮйҖғгҒ’гҒҰжҲ»гӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§гҖҒеҰ№гҒ®ж–№гҒҢгҒӮгҒӘгҒҹзҹігӮ’жҠ•гҒ’гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰе…„гҒ®ж•өжү“гӮ’гҒҷгӮӢгӮ„гҒҶгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгҒҜгғҳгғңгҒ§гҒ”гҒ–гҒ„гҒҫгҒҷгҖҚпјҲгҖҢжҜҚе ӮгҒ®и«Үи©ұгҖҚпјү
гҖҖеӯҗиҰҸиҮӘиә«гӮӮгҖҒгҖҢеғ•гҒҜеӯҗдҫӣгҒ®жҷӮгҒӢгӮүејұе‘іеҷҢгҒ®жіЈе‘іеҷҢгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгҒҰе°ҸеӯҰж ЎгҒ«еҫҖгҒҰгӮӮгҒҹгҒігҒҹгҒіжіЈгҒӢгҒ•гӮҢгҒҰеұ…гҒҹгҖҚпјҲгҖҺеўЁжұҒдёҖж»ҙгҖҸпјүгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒе°ҸеӯҰз”ҹгҒ®й ғгҒӢгӮүеүөдҪңжҙ»еӢ•гҒ«зҶұдёӯгҒ—гҖҒйӣ‘иӘҢгӮ’дҪңгҒЈгҒҰгҒҜд»Ій–“гҒҹгҒЎгҒ«еӣһиҰ§гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒҫгҒҹдёӯеӯҰз”ҹгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒҜгҖҒж”ҝжІ»гҒ«гӮӮеј·гҒ„й–ўеҝғгӮ’жҠұгҒҚгҖҒзӣӣгӮ“гҒ«ж”ҝи«Үжј”иӘ¬гӮ’иЎҢгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»15е№ҙй ғгҒӢгӮүжқұдә¬гҒ§еӯҰгҒ¶гҒ“гҒЁгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒжҳҺжІ»16е№ҙпјҲ1883пјү6жңҲгҖҒеҝөйЎҳгҒҢеҸ¶гҒЈгҒҰдёҠдә¬гҒҷгӮӢгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҒ®гҒЎгҒ«гҖҢдҪҷгҒҜз”ҹгӮҢгҒҰгӮҲгӮҠгҒҶгӮҢгҒ—гҒҚгҒ“гҒЁгҒ«гҒӮгҒІжҖқгҒҜгҒҡгҒ«гҒ“пјҸпјјгҒЁгӮ‘гҒҝгҒҰе№іж°—гҒ§гӮҗгӮүгӮҢгҒ–гӮҠгҒ—гҒ“гҒЁдёүеәҰгҒӮгӮҠ第дёҖгҒҜеңЁдә¬гҒ®еҸ”зҲ¶гҒ®гӮӮгҒЁгӮҲгӮҠдҪҷгҒ«жқұдә¬гҒ«жқҘгӮҢгҒЁгҒ„гҒөжүӢзҙҷжқҘгҒҹгӮҠгҒ—жҷӮгҖҚпјҲгҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸпјүгҒЁиЁҳгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»18е№ҙпјҲ1885пјүгҖҒе…ҘеӯҰеҲқе№ҙеәҰгҒ®еӯҰе№ҙжң«и©ҰйЁ“гҒ§дёҚеҗҲж јгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒиҗҪ第гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҖҢж•°еӯҰгҒ®жҷӮй–“гҒ«гҒҜиӢұиӘһгӮҲгӮҠеӨ–гҒ®иӘһгҒҜдҪҝгӮҸгӮҢгҒ¬гҒЁгҒ„гҒҶиҰҸеҲ¶гҖҚгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҖҢж•°еӯҰгҒЁиӢұиӘһгҒЁдәҢгҒӨгҒ®ж•өгӮ’дёҖжҷӮгҒ«еј•гҒҚеҸ—гҒ‘гҒҹгҒӢгӮүгҒҹгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҖҚгҖҒгҖҢдҪҷгҒҢиҗҪ第гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜе№ҫдҪ•еӯҰгҒ«иҗҪ第гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒөгӮҲгӮҠгҒҜеҜ§гӮҚиӢұиӘһгҒ«иҗҪ第гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒөж–№гҒҢйҒ©еҪ“гҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҖҚпјҲгҖҺеўЁжұҒдёҖж»ҙгҖҸпјүгҖӮ
гҖҖдёҖж–№гҒ®жјұзҹігӮӮгҖҒгҖҢжғ°гҒ‘гҒҰеұ…гӮӢгҒ®гҒҜз”ҡгҒ еҘҪгҒҚгҒ§е°‘гҒ—гӮӮеӢүеј·гҒӘгӮ“гҒӢгҒ—гҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖҚгҖҒгҖҢе”ҜйҒҠгӮ“гҒ§еұ…гӮӢгҒ®гӮ’иұӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ®еҰӮгҒҸжҖқгҒӨгҒҰжҖ гҒ‘гҒҰеұ…гҒҹгҖҚпјҲгҖҢиҗҪ第гҖҚпјүгҒЁгҒ“гӮҚгҖҒжҳҺжІ»19е№ҙпјҲ1886пјүгҖҒи…№иҶңзӮҺгҒ®гҒҹгӮҒйҖІзҙҡи©ҰйЁ“гӮ’еҸ—гҒ‘гӮүгӮҢгҒҡжҲҗзёҫгӮӮжӮӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒиҗҪ第гҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒҶгҖӮжјұзҹігҒҜгҒ“гҒ®иҗҪ第гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰеҫҢе№ҙгҒӨгҒҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖдәәй–“гҒЁдә‘гҒөгӮӮгҒ®гҒҜиҖғгҒҲзӣҙгҒҷгҒЁеҰҷгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒзңҹйқўзӣ®гҒ«гҒӘгҒӨгҒҰеӢүеј·гҒҷгӮҢгҒ°гҖҒд»Ҡиҝ„е°‘гҒ—гӮӮеҲҶгҒӢгӮүгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгӮӮгҒ®гӮӮзһӯ然гҒЁеҲҶгӮӢж§ҳгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүжҒҒгӮ“гҒӘйўЁгҒ«иҗҪ第гӮ’ж©ҹгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮҚгӮ“гҒӘж”№йқ©гӮ’гҒ—гҒҰеӢүеј·гҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеғ•гҒ®дёҖиә«гҒ«гҒЁгҒӨгҒҰжӯӨиҗҪ第гҒҜйқһеёёгҒ«и–¬гҒ«гҒӘгҒӨгҒҹж§ҳгҒ«жҖқгҒҜгӮҢгӮӢгҖӮ
пјҲгҖҢиҗҪ第гҖҚпјү

еӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ®жјұзҹіпјҲе·ҰгҖҒеҸігҒҜзұіеұұпјү
гҖҖжҳҺжІ»21е№ҙпјҲ1888пјү9жңҲгҖҒжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒҜ第дёҖй«ҳзӯүдёӯеӯҰж Ўжң¬з§‘第дёҖйғЁпјҲж–Ү科пјүгҒ«е…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮе°Ӯж”»гӮ’жұәгӮҒгӮӢгҒ•гҒ„жјұзҹігҒҜгҒҜгҒҳгӮҒе»әзҜү科гӮ’еёҢжңӣгҒ—гҖҒе°ҶжқҘгҒҜгҖҢгғ”гғ©гғҹгғ„гғүгҒ§гӮӮе»әгҒҰгӮӢж§ҳгҒӘеҝғз®—гҒ§еұ…гҖҚгҒҹгҒҢгҖҒеҗҢзҙҡз”ҹгҒ®зұіеұұдҝқдёүйғҺгҒ«гҖҒгҖҢгҒқгӮҢгӮҲгӮҠгӮӮж–ҮеӯҰгӮ’гӮ„гӮҢгҖҒж–ҮеӯҰгҒӘгӮүгҒ°еӢү強次第гҒ§е№ҫзҷҫе№ҙе№ҫеҚғе№ҙгҒ®еҫҢгҒ«дјқгҒёгӮӢеҸҜгҒҚеӨ§дҪңгӮӮеҮәжқҘгӮӢгҒўгӮ„гҒӘгҒ„гҒӢгҖҚгҒЁеӢ§гӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҖҢжұәеҝғгӮ’зӮәзӣҙгҒ—гҒҰгҖҒеғ•гҒҜж–ҮеӯҰгӮ’гӮ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«е®ҡгӮҒгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеӣҪж–ҮгӮ„жјўж–ҮгҒӘгӮүеҲҘгҒ«з ”究гҒҷгӮӢеҝ…иҰҒгӮӮгҒӘгҒ„ж§ҳгҒӘж°—гҒҢгҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҖҒе…¶еҮҰгҒ§иӢұж–ҮеӯҰгӮ’е°Ӯж”»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒ—гҒҹгҖӮгҖҚпјҲгҖҢиҗҪ第гҖҚпјүгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒ«ж–ҮеӯҰгӮ’еӢ§гӮҒгҒҹзұіеұұгҒҜгҖҒжјұзҹігҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢгҒқгӮҢгҒ“гҒқзңҹжҖ§еӨүзү©гҒ§еёёгҒ«е®Үе®ҷгҒҢгҒ©гҒҶгҒ®гҖҒдәәз”ҹгҒҢгҒ©гҒҶгҒ®гҒЁеӨ§гҒҚгҒӘгҒ“гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠиЁҖгҒӨгҒҰеұ…гӮӢгҖҚпјҲи«Үи©ұгҖҢжҷӮж©ҹгҒҢжқҘгҒҰгӮҗгҒҹгӮ“гҒ гҖҚпјүдәәзү©гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҗиҰҸгҒЁгӮӮдәӨйҒҠгӮ’жҢҒгҒЈгҒҹгҖӮеёқеӣҪеӨ§еӯҰе“ІеӯҰ科гҒ®еӯҗиҰҸгҒҢеӣҪж–Ү科гҒ«и»ўз§‘гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒзұіеұұгҒ®жүҚиғҪгҒ«й©ҡеҳҶгҒ—гҖҒе“ІеӯҰгҒ§гҒҜзұіеұұгҒ«йҒ©гӮҸгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢзҗҶз”ұгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгӮӮиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒҢиҰӘгҒ—гҒҸдәӨжөҒгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҒ®гҒҜжҳҺжІ»22е№ҙпјҲ1889пјү1жңҲй ғгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮдәҢдәәгҒҜгҖҒе…ұйҖҡгҒ®и¶Је‘ігҒ§гҒӮгӮӢеҜ„еёӯгҒ®и©ұйЎҢгҒӘгҒ©гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰиҰӘдәӨгӮ’ж·ұгӮҒгҒҰиЎҢгҒҸгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»22е№ҙгҒ®гҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸгҒ®дёӯгҒ§гҖҒжјұзҹігӮ’гҖҢи«ҮеҝғгҒ®еҸӢгҖҚгҖҒгҖҢз•ҸеҸӢгҖҚгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеҫҢе№ҙгҖҒжјұзҹігҒҜеӯҗиҰҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖйқһеёёгҒ«еҘҪгҒҚе«ҢгҒ„гҒ®гҒӮгҒӨгҒҹдәәгҒ§гҖҒж»…еӨҡгҒ«дәәгҒЁдәӨйҡӣгҒӘгҒ©гҒҜгҒ—гҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮеғ•гҒ гҒ‘гҒ©гҒҶгҒ„гҒөгӮӮгҒ®гҒӢдәӨйҡӣгҒ—гҒҹгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүеҪјгҒЁеғ•гҒЁдәӨйҡӣгҒ—е§ӢгӮҒгҒҹгӮӮдёҖгҒӨгҒ®еҺҹеӣ гҒҜдәҢдәәгҒ§еҜ„еёӯгҒ®и©ұгӮ’гҒ—гҒҹжҷӮе…Ҳз”ҹгӮӮеӨ§гҒ«еҜ„еёӯйҖҡгӮ’д»ҘгҒӨгҒҰд»»гҒҳгҒҰеұ…гӮӢгҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеғ•гӮӮеҜ„еёӯгҒ®дәӢгӮ’зҹҘгҒӨгҒҰгӮҗгҒҹгҒ®гҒ§и©ұгҒҷгҒ«и¶ігӮӢгҒЁгҒ§гӮӮжҖқгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҖӮе…¶гҒӢгӮүеӨ§гҒ«иҝ‘гӮҲгҒӨгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ пјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖдҪ•гҒ§гӮӮеӨ§е°ҶгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ‘гӮҠгӮ„жүҝзҹҘгҒ—гҒӘгҒ„з”·гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮдәҢдәәгҒ§йҒ“гӮ’жӯ©гҒ„гҒҰгӮҗгҒҰгӮӮгҒҚгҒӨгҒЁиҮӘеҲҶгҒ®жҖқгҒөйҖҡгӮҠгҒ«еғ•гӮ’гҒІгҒӨгҒұгӮҠе»»гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ гҖӮе°ӨгӮӮеғ•гҒҢгҒҗгҒҶгҒҹгӮүгҒ§гҒӮгҒӨгҒҰгҒ“гҒЎгӮүгҒёиЎҢгҒӢгҒҶгҒЁеҪјгҒҢгҒ„гҒөгҒЁе…¶йҖҡгӮҠгҒ«гҒ—гҒҰеұ…гҒӨгҒҹзӮәгҒ§гҒӮгӮүгҒҶгҖӮ
пјҲгҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҚпјү
гҖҖеӯҗиҰҸгҒЁгҒ„гҒөз”·гҒҜдҪ•гҒ§гӮӮиҮӘеҲҶгҒҢе…Ҳз”ҹгҒ®гӮ„гҒҶгҒӘз©ҚгӮҠгҒ§еұ…гӮӢз”·гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮдҝіеҸҘгӮ’иҰӢгҒӣгӮӢгҒЁзӣҙгҒҗгҒ«гҒқгӮҢгӮ’зӣҙгҒ—гҒҹгӮҠеңҸзӮ№гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҒ„гӮқгҒ«гҒ—гҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ§еғ•гҒҢжјўи©©гӮ’дҪңгҒӨгҒҰиҰӢгҒӣгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒзӣҙгҒҗгҒ«еҸҲзӯҶгӮ’гҒЁгҒӨгҒҰгҒқгӮҢгӮ’зӣҙгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒеңҸзӮ№гӮ’гҒӨгҒ‘гҒҹгӮҠгҒ—гҒҰиҝ”гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒ§д»ҠеәҰгҒҜиӢұж–ҮгӮ’з¶ҙгҒӨгҒҰиҰӢгҒӣгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢгҖҒеҘҙгҒ•гӮ“гҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒҜд»•ж–№гҒӘгҒ„гӮӮгҒ®гҒ гҒӢгӮүVery goodгҒЁжӣёгҒ„гҒҰиҝ”гҒ—гҒҹгҖӮ
пјҲй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҺжјұзҹіж°ҸгҒЁз§ҒгҖҸпјү
гҖҖдёҖж–№еӯҗиҰҸгҒҜгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖдҪҷгҒҜдәӨйҡӣгӮ’еҘҪгӮҖиҖ…гҒӘгӮҠгҖҖеҸҲдәӨйҡӣгӮ’е«ҢгҒөиҖ…д№ҹгҖҖдҪ•ж•…гҒ«еҘҪгӮҖгӮ„гҖҖиүҜеҸӢгӮ’еҫ—гҒҰеҝғдәӢгӮ’и«ҮгҒҳиүұйӣЈзӣёеҠ©гҒ‘гӮ“гҒЁж¬ІгҒҷгӮҢгҒ°д№ҹгҖҖдҪ•ж•…гҒ«е«ҢгҒөгӮ„гҖҖжӮӘеҸӢгӮ’йҖҖгҒ‘е…үйҷ°гӮ’жөӘиІ»гҒӣгҒҡиӘҳе°ҺгӮ’гҒ®гҒҢгӮҢгӮ“гҒЁж¬ІгҒҷгӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҖҖдҪҷгғҸеҒҸеұҲгҒӘгӮҠгҖҖй ‘еӣәгҒӘгӮҠгҖҒгҒҷгҒҚгҒӘдәәгғҸз„Ўжҡ—гҒ«гҒҷгҒҚгҒ«гҒҰе«ҢгҒІгҒӘдәәгғҸз„Ўжҡ—гҒ«гҒҚгӮүгҒІгҒӘгӮҠ
пјҲгҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸжҳҺжІ»22е№ҙпјү
гҖҖжјұзҹіжңҖгӮӮгҒҫгҒҳгӮҒгҒ®жҖ§иіӘгҒ«гҒҰеӯҰж ЎгҒ«гҒӮгӮҠгҒҰз”ҹеҫ’гӮ’зҺҮгҒ„гӮӢгҒ«гӮӮеҺіж јгӮ’дё»гҒЁгҒ—гҒҰдёҚиҰҸеҫӢгҒ«жөҒгӮӢгӮӢгӮ’иЁұгҒ•гҒҡгҖӮзҙ«еҪұгҒ®ж–Үз« дҝіеҸҘеёёгҒ«ж»‘зЁҪи¶Је‘ігӮ’йӣўгӮҢгҒҡгҖӮжӯӨдәәдәҰз”ҡгҒ гҒҫгҒҳгӮҒгҒ®ж–№гҒ«гҒҰгҖҒеӨ§еҸЈгҒӮгҒ‘гҒҰ笑гҒҶгҒ“гҒЁгҒҷгӮүдҪҷгӮҠиҰӢгҒҶгҒ‘гҒҹгӮӢдәӢз„ЎгҒ—гҖӮ
пјҲгҖҺеўЁжұҒдёҖж»ҙгҖҸпјү
гҖҖгҒҫгҒҹжјұзҹій–ҖдёӢгҒ®еҜәз”°еҜ…еҪҰгҒҜгҖҒжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖзҶҠжң¬гҒ®иҝ‘жіҒгҒӢгӮүжјұзҹіеё«гҒ®гҒҶгӮҸгҒ•гҒ«гҒӘгҒӨгҒҰжҳ”и©ұгӮӮеҮәгҒҹгҖӮеё«гҒҜеӯҰз”ҹгҒ®й ғгҒҜиҮігҒӨгҒҰеҜЎиЁҖгҒӘжё©й ҶгҒӘдәәгҒ§еӯҰж ЎгҒӘгҒ©гӮӮиҮігҒӨгҒҰж¬ еёӯгҒҢе°‘гҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҒҢеӯҗиҰҸгҒҜдҝіеҸҘеҲҶйЎһгҒ«гҒЁгӮҠгҒӢгӮқгҒӨгҒҰгҒӢгӮүж¬ еёӯгҒ°гҒӢгӮҠгҒ—гҒҰеұ…гҒҹгҒ•гҒҶгҒ гҖӮеё«гҒЁеӯҗиҰҸгҒЁиҰӘеҜҶгҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҒ®гҒҜзҹҘгӮҠеҗҲгҒӨгҒҰгҒӢгӮүеӣӣе№ҙгӮӮгҒҹгҒӨгҒҰеҫҢгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒҢжҮҮж„ҸгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйҡҸеҲҶеӯҗдҫӣгӮүгҒ—гҒҸиӯ°и«–гҒӘгӮ“гҒӢгҒ—гҒҰжҷӮгҖ…е–§еҳ©гҒӘгҒ©гӮӮгҒҷгӮӢгҖӮ
пјҲгҖҢеӯҗиҰҸеәөгӮ’иЁӘгҒҶиЁҳгҖҚпјү
гҖҖй«ҳзӯүеӯҰж ЎгӮ’еҮәгҒҰеӨ§еӯҰгҒёгҒҜгҒІгӮӢжҷӮгҒ«гҖҒе…Ҳз”ҹгҒ®зҙ№д»ӢгӮ’иІ°гҒӨгҒҰдёҠж №еІёй¶ҜжЁӘз”әгҒ«з—…еәҠгҒ®жӯЈеІЎеӯҗиҰҸеӯҗгӮ’иЁӘгҒӯгҒҹгҖӮгҒқгҒ®жҷӮгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒеӨҸзӣ®е…Ҳз”ҹгҒ®е°ұиҒ·е…¶д»–гҒ«е°ұгҒ„гҒҰиүІгҖ…йӘЁгӮ’жҠҳгҒӨгҒҰйҒӢеӢ•гӮ’гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒөгӮ„гҒҶгҒӘи©ұгӮ’гҒ—гҒҰиҒһгҒӢгҒӣгҒҹгҖӮе®ҹйҡӣеӯҗиҰҸгҒЁе…Ҳз”ҹгҒЁгҒҜдә’гҒ«з•Ҹ敬гҒ—еҗҲгҒӨгҒҹжңҖгӮӮиҰӘгҒ—гҒ„дәӨеҸӢгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒЁжҖқгҒҜгӮҢгӮӢгҖӮдҪөгҒ—гҖҒе…Ҳз”ҹгҒ«иҒһгҒҸгҒЁгҖҒжҷӮгҒ«гҒҜгҖҢдёҖдҪ“жӯЈеІЎгҒЁгҒ„гҒөз”·гҒҜгҒӘгӮ“гҒ§гӮӮиҮӘеҲҶгҒ®ж–№гҒҢгҒҲгӮүгҒ„гҒЁжҖқгҒӨгҒҰеұ…гӮӢгҖҒз”ҹж„Ҹж°—гҒӘеҘҙгҒ гӮҲгҖҚгҒӘгҒ©гӮқдә‘гҒӨгҒҰ笑гҒҜгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгҒӨгҒҹгҖӮгҒ•гҒҶдә‘гҒІгҒӘгҒҢгӮүгҖҒдә’гҒ«иЁұгҒ—еҗҲгҒІгҒӘгҒӨгҒӢгҒ—гҒҢгӮҠеҗҲгҒӨгҒҰеұ…гӮӢеҝғжҢҒгҒҢгӮҲгҒҸеҲҶгҒӢгӮӢгӮ„гҒҶгҒ«жҖқгҒҜгӮҢгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮ
пјҲгҖҢеӨҸзӣ®жјұзҹіе…Ҳз”ҹгҒ®иҝҪжҶ¶гҖҚпјү
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»22е№ҙпјҲ1889пјү5жңҲеҲқж—¬гҒ«е–ҖиЎҖгҒ—гҖҒиӮәзөҗж ёгҒЁиЁәж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҖҢеҚҜгҒ®иҠұгӮ’гӮҒгҒҢгҒ‘гҒҰгҒҚгҒҹгҒӢжҷӮйіҘгҖҚгҖҒгҖҢеҚҜгҒ®иҠұгҒ®ж•ЈгӮӢгҒҫгҒ§йіҙгҒҸгҒӢеӯҗиҰҸгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒжҷӮйіҘпјҲгҒ»гҒЁгҒЁгҒҺгҒҷпјүгҒ®еҸҘгӮ’ж•°еҚҒзЁ®дҪңгӮҠгҖҒд»ҘеҫҢгҖҒгҖҢеӯҗиҰҸгҖҚгҒЁеҸ·гҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжҷӮйіҘгҒҜгҖҒгҖҢе•јгҒ„гҒҰиЎҖгӮ’еҗҗгҒҸгҖҚгҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҖҒиӮәз—…гҒ®иұЎеҫҙгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒгҖҢд»ҠгӮҲгӮҠеҚҒе№ҙгҒ®е‘ҪгҖҚпјҲгҖҢе–ҖиЎҖе§Ӣжң«гҖҚпјүгҒЁиҰҡжӮҹгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»22е№ҙпјҲ1889пјү5жңҲ13ж—ҘгҖҒгҖҢеҸӘд»ҠгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеӨ§дәӢгҒ®е ҙеҗҲж•…еҮәжқҘгӮӢгҒ гҒ‘гҒ®еҫЎйқҷйӨҠгҒҜе°ӮдёҖгҒЁеҘүеӯҳеҖҷгҖҚгҖҒгҖҢе°ҸгҒ«гҒ—гҒҰгҒҜеҫЎжҜҚе ӮгҒ®зӮәеӨ§гҒ«гҒ—гҒҰгҒҜеӣҪ家гҒ®зӮәиҮӘж„ӣгҒӣгӮүгӮҢгӮ“дәӢгҒ“гҒқжңӣгҒҫгҒ—гҒҸеӯҳеҖҷгҖҚгҒЁеӯҗиҰҸгҒ®з—…зҠ¶гӮ’ж…®гӮӢжӣёз°ЎгӮ’йҖҒгӮҠгҖҒгҖҢеё°гӮҚгҒөгҒЁжіЈгҒӢгҒҡгҒ«з¬‘гҒёжҷӮйіҘгҖҚгҖҒгҖҢиҒһгҒӢгҒөгҒЁгҒҰиӘ°гӮӮеҫ…гҒҹгҒ¬гҒ«жҷӮйіҘгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҸҘгӮ’ж·»гҒҲгҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒй•·е…„гғ»ж¬Ўе…„гӮ’зөҗж ёгҒ§дәЎгҒҸгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдёүе…„гӮӮгҒҫгҒҹгҒ“гҒ®жҷӮгҖҒзөҗж ёгҒ§з—…еәҠгҒ«гҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒж®ҠжӣҙгҒ«еӯҗиҰҸгҒ®з—…зҠ¶гҒҢж°—жҺӣгҒӢгӮҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҒ«йҒ•гҒ„гҒӘгҒ„гҖӮеӯҗиҰҸгҒ®з—…гӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒ®дәӨжөҒгҒҜгӮҲгӮҠдёҖеұӨгҖҒиҰӘеҜҶгҒ•гӮ’еў—гҒ—гҒҰиЎҢгҒҸгҖӮ
гҖҖ5жңҲдёӢж—¬гҒ«гҒҜгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®е’Ңжјўи©©ж–ҮйӣҶгҖҺдёғиҚүйӣҶгҖҸпјҲгҒӘгҒӘгҒҸгҒ•гҒ—гӮ…гҒҶпјүгҒ®е·»жң«гҒ®и©•гҒ§гҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҖҢжјұзҹігҖҚгҒ®еҸ·гӮ’з”ЁгҒ„гҒҹгҖӮгҖҢжјұзҹігҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚгҒҜгҖҒеҘҮгҒ—гҒҸгӮӮгҖҒеӯҗиҰҸгҒҢжҳҺжІ»14гҖҒ15е№ҙй ғгҒ«гҖҒеҗҚд№—гҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеҸ·гҒ§гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹпјҲгҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸпјүгҖӮ
гҖҖд»–ж–№гҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжјұзҹігҒҢжҳҺжІ»22е№ҙ9жңҲй ғгҒ«жӣёгҒ„гҒҹжјўи©©зҙҖиЎҢж–ҮгҖҺжңЁеұ‘йҢІгҖҸпјҲгҒјгҒҸгҒӣгҒӨгӮҚгҒҸпјүгӮ’иӘӯгҒҝгҖҒгҖҢй јгҒҝгӮӮгҒ—гҒӘгҒ„гҒ®гҒ«и·ӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгӮҲгҒ“гҒ—гҖҚпјҲгҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҚпјүгҖҒгҖҢеҰӮеҗҫе…„иҖ…еҚғиҗ¬е№ҙдёҖдәәз„үиҖігҖҚгҒЁзө¶иіӣгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖдҪҷгҒ®зөҢйЁ“гҒ«гӮҲгӮӢгҒ«иӢұеӯҰгҒ«й•·гҒҡгӮӢиҖ…гҒҜжјўеӯҰгҒ«зҹӯгҒӘгӮҠгҖҖе’ҢеӯҰгҒ«й•·гҒҡгӮӢиҖ…гҒҜж•°еӯҰгҒ«зҹӯгҒӘгӮҠгҒЁгҒ„гҒөгҒҢеҰӮгҒҸгҖҖеҝ…гҒҡдёҖй•·дёҖзҹӯгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®д№ҹгҖҖзӢ¬гӮҠжјұзҹігҒҜй•·гҒңгҒ–гӮӢжүҖгҒӘгҒҸйҒ”гҒӣгҒ–гӮӢжүҖгҒӘгҒ—гҖҒ然гӮҢе…ұе…¶иӢұеӯҰгҒ«й•·гҒҡгӮӢгҒҜдәәзҡҶд№ӢгӮ’зҹҘгӮӢгҖҒиҖҢгҒ—гҒҰе…¶жјўж–Үжјўи©©гҒ«е·§гҒӘгӮӢдәәжҒҗгӮүгҒҸгҒҜзҹҘгӮүгҒ–гӮӢгҒ№гҒ—гҖҖж•…гҒ«гҒ“гӮқгҒ«йҷ„иЁҳгҒҷгӮӢгҒ®гҒҝ
пјҲгҖҺзӯҶгҒҫгҒӢгҒӣгҖҸпјү
гҖҖжјұзҹігҒ®гҖҺжңЁеұ‘йҢІгҖҸгҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®гҖҺдёғиҚүйӣҶгҖҸгҒ«и§ҰзҷәгҒ•гӮҢгҒҰжӣёгҒӢгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒдҪ•гӮҲгӮҠгӮӮгҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҒ«иҰӢгҒӣгӮӢдәӢгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰжӣёгҒӢгӮҢгҖҚпјҲе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҖҢгҖҺжңЁеұ‘йҢІгҖҸи§ЈиӘ¬гҖҚпјүгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢжјұзҹігҖҚгҒЁгҖҢеӯҗиҰҸгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеёҢд»ЈгҒ®ж–ҮеӯҰзҡ„жүҚиғҪгӮ’жҢҒгҒӨдәҢдәәгҒ®гҖҒжҜ”йЎһгҒ®гҒӘгҒ„зӣҹеҸӢй–ўдҝӮгҒҜгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰе§ӢгҒҫгӮӢгҖӮдәҢдәәгҒҜгҖҒжјұзҹігҒҢгҖҢдёҖдҪ“жӯЈеІЎгҒҜз„Ўжҡ—гҒ«жүӢзҙҷгӮ’ гӮҲгҒ“гҒ—гҒҹз”·гҒ§гҖҒе…¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢеҲҶйҮҸгҒҜгҒ“гҒЎгӮүгҒӢгӮүгӮӮйҒЈгҒЈгҒҹгҖҚпјҲгҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҚпјүгҒЁиӘһгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒжүӢзҙҷгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгӮӮеҸӢжғ…гӮ’ж·ұгӮҒгҒҰиЎҢгҒҸгҖӮдҫӢгҒҲгҒ°жјұзҹігҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ«гҖҒгҖҢжӯӨй ғгҒҜдҪ•гҒЁгҒӘгҒҸжө®дё–гҒҢгҒ„гӮ„гҒ«гҒӘгӮҠгҒ©гҒҶиҖғгҒёгҒҰгӮӮиҖғгҒёзӣҙгҒ—гҒҰгӮӮгҒ„гӮ„гҒ§пјҸпјјз«ӢгҒЎеҲҮгӮҢгҒҡгҖҚгҖҒгҖҢиІҙеҗӣгҒ®жүӢеүҚгҒҜгҒҘгҒӢгҒ—гҒҸеҗҫгҒӘгҒҢгӮүжғ…гҒӘгҒҚеҘҙгҒЁжҖқгҒёгҒ©гҒ“гӮҢгӮӮmisanthropicз—…гҒӘгӮҢгҒ°жҳҜйқһгӮӮгҒӘгҒ—гҖҚпјҲжҳҺжІ»23е№ҙ8жңҲ9ж—ҘпјүгҒЁиӢҰжӮ©гҒҷгӮӢеҝғжғ…гӮ’зҺҮзӣҙгҒ«жӣёгҒҚйҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹдәҢдәәгҒ®й–“гҒ§гҒҜгҖҒж–ҮеӯҰиҰігғ»дәәз”ҹиҰігӮ’е·ЎгҒЈгҒҰгҖҒеҝҢжҶҡгҒ®гҒӘгҒ„жү№еҲӨгӮ’еҗ«гӮ“гҒ жӣёз°ЎгҒҢдәӨжҸӣгҒ•гӮҢгҒҹжҠҳгӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҫЎеүҚе…јгҒҰеҫЎи¶Јеҗ‘гҒ®е°ҸиӘ¬гҒҜе·ігҒ«зӯҶгӮ’дёӢгҒ—зөҰгҒІгҒ—гӮ„д»ҠеәҰгҒҜеҰӮдҪ•гҒӘгӮӢж–ҮдҪ“гӮ’з”ЁгҒІзөҰгҒҶеҫЎж„ҸиҰӢгҒӘгӮҠгӮ„委зҙ°гҒҜжӢқиҰӢгҒ®дёҠйҖҗдёҖжү№и©•гӮ’и©ҰгӮҖгӮӢз©ҚгӮҠгҒ«еҖҷгҒёгҒ©гӮӮе…Һи§’еӨ§е…„гҒ®ж–ҮгҒҜгҒӘгӮҲпјҸпјјгҒЁгҒ—гҒҰе©ҰдәәжөҒгҒ®зҝ’ж°—гӮ’и„ұгҒӣгҒҡ
пјҲжҳҺжІ»22е№ҙ12жңҲ31ж—ҘеӯҗиҰҸе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖе°Ҹз”ҹе…ғжқҘеӨ§е…„гӮ’д»ҘгҒҰеҗҫгҒҢжңӢеҸӢдёӯдёҖиҰӢиӯҳгӮ’жңүгҒ—иҮӘе·ұгҒ®е®ҡиҰӢгҒ«з”ұгҒӨгҒҰдәәз”ҹгҒ®иҲӘи·ҜгҒ«иҲөгӮ’гҒЁгӮӢгӮӮгҒ®гҒЁдҝЎгҒҳеұ…еҖҷе…¶дҝЎгҒҳгҒҚгӮҠгҒҹгӮӢжңӢеҸӢгҒҢгҒӢгӮқгӮӢе°ҸдҫӣгҒ гҒҫгҒ—гҒ®е°ҸеҶҠеӯҗгӮ’д»ҘгҒҰж°—зҜҖгҒ®жүӢжң¬гҒ«гҒӣгӮҲгҒЁгӮҸгҒ–пјҸпјјжҒөжҠ•гҒӣгӮүгӮҢгҒҹгӮӢгҒҜгҒӨгӮ„пјҸпјје…¶ж„ҸгӮ’еҫ—гҒҡ
пјҲжҳҺжІ»24е№ҙ11жңҲ7ж—Ҙд»ҳеӯҗиҰҸе®ӣжӣёз°Ўпјү
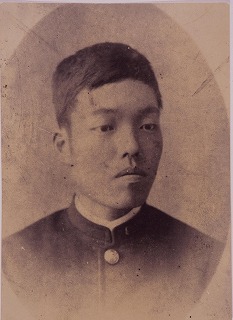
еӯҰз”ҹжҷӮд»ЈгҒ®еӯҗиҰҸпјҲжҳҺжІ»23е№ҙпјү
гҖҖгҒҫгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜдәҢдәәгҒҜгҖҢеҰҫгҖҚгҖҒгҖҢжң—еҗӣгҖҚпјҲжҳҺжІ»22е№ҙ9жңҲ27ж—ҘеӯҗиҰҸе®ӣжӣёз°ЎпјүгҒЁжҲҜгӮҢеҗҲгҒ„гҖҒгҒҫгҒҹгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҢгҒӮгӮқгҒқгҒҶпјҸпјјгҖҒжҳЁж—ҘзңјеҢ»иҖ…гҒёгҒ„гҒӨгҒҹжүҖгҒҢгҖҒгҒ„гҒӨгҒӢеҗӣгҒ«и©ұгҒ—гҒҹеҸҜж„ӣгӮүгҒ—гҒ„еҘігҒ®еӯҗгӮ’иҰӢгҒҹгҒӯгҖҒвҖ•пј»йҠҖпјҪжқҸиҝ”гҒ—гҒ«з«№гҒӘгҒҜгӮ’гҒӢгҒ‘гҒҰвҖҗвҖҗеӨ©ж°—дәҲе ұгҒӘгҒ—гҒ®зӘҒ然гҒ®йӮӮйҖ…гҒ гҒӢгӮүгҒІгӮ„гҒӨгҒЁй©ҡгҒ„гҒҰжҖқгҒҜгҒҡйЎ”гҒ«зҙ…и‘үгӮ’ж•ЈгӮүгҒ—гҒҹгҒӯгҖҚ пјҲжҳҺжІ»24е№ҙ7жңҲ18ж—ҘеӯҗиҰҸе®ӣжӣёз°ЎпјүгҒЁжҒӢеҝғгӮ’д»„гӮҒгҒӢгҒҷгӮҲгҒҶгҒӘжӣёз°ЎгӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгӮӮгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжҳҺжІ»23е№ҙпјҲ1890пјү9жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜеёқеӣҪеӨ§еӯҰж–Ү科еӨ§еӯҰиӢұж–Ү科гҖҒеӯҗиҰҸгҒҜеҗҢе“ІеӯҰ科пјҲгҒ®гҒЎгҒ«еӣҪж–Ү科гҒ«и»ўз§‘пјүгҒ«е…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжҳҺжІ»20е№ҙгҒ«ж–°иЁӯгҒ•гӮҢгҒҹиӢұж–Ү科гҒ«гҒҜ2е№ҙдёҠгҒ«е…Ҳиј©гҒҢпј‘дәәгҒ„гӮӢгҒ гҒ‘гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҳҺжІ»23е№ҙгҒ«иӢұж–Ү科гҒ«е…ҘеӯҰгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜжјұзҹігҒҹгҒ гҒІгҒЁгӮҠгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹиӢұж–Ү科гҒ®3е№ҙеҫҢиј©гҒ«гҒҜеңҹдә•жҷ©зҝ гҒҢгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒгғҮгӮЈгӮҜгӮҪгғіж•ҷжҺҲгҒӢгӮүиӢұиӘһгғ»иӢұж–ҮеӯҰгӮ’еӯҰгӮ“гҒ гҖӮжҲҗзёҫе„Әз§ҖгҒӘеҪјгҒҜгҖҒж•ҷжҺҲгҒӢгӮүдҫқй јгҒ•гӮҢгҖҒгҖҺж–№дёҲиЁҳгҖҸгӮ’иӢұиЁігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»26е№ҙпјҲ1893пјүгҒ«жқҘж—ҘгҒ—гҒҹгӮұгғјгғҷгғ«гҒ®и¬ӣзҫ©гӮ’иҒҙи¬ӣгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜзү№еҫ…з”ҹгҒЁгҒӘгӮҠжҺҲжҘӯж–ҷе…ҚйҷӨгҒӘгҒ©гҒ®зү№е…ёгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒиӢұж–ҮеӯҰз ”з©¶гҒ«еҜҫгҒҷгӮӢжј з„¶гҒЁгҒ—гҒҹдёҚе®үгҒЁз–‘е•ҸгӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖз§ҒгҒҜеӨ§еӯҰгҒ§иӢұж–ҮеӯҰгҒЁгҒ„гҒөе°Ӯй–ҖгӮ’гӮ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮе…¶иӢұж–ҮеӯҰгҒЁгҒ„гҒөгӮӮгҒ®гҒҜдҪ•гӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гҒӢгҒЁеҫЎе°ӢгҒӯгҒ«гҒӘгӮӢгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒгҒқгӮҢгӮ’дёүе№ҙе°Ӯж”»гҒ—гҒҹз§ҒгҒ«гӮӮдҪ•гҒҢдҪ•гҒ гҒӢгҒҫгҒӮеӨўдёӯгҒ гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮе…¶й ғгҒҜгғӮгӮҜгӮҪгғігҒЁгҒ„гҒөдәәгҒҢж•ҷеё«гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜе…¶е…Ҳз”ҹгҒ®еүҚгҒ§и©©гӮ’иӘӯгҒҫгҒӣгӮүгӮҢгҒҹгӮҠж–Үз« гӮ’иӘӯгҒҫгҒӣгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒдҪңж–ҮгӮ’дҪңгҒӨгҒҰгҖҒеҶ и©һгҒҢиҗҪгҒЎгҒҰгӮҗгӮӢгҒЁдә‘гҒӨгҒҰеҸұгӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҖҒзҷәйҹігҒҢй–“йҒ•гҒӨгҒҰгӮҗгӮӢгҒЁжҖ’гӮүгӮҢгҒҹгӮҠгҒ—гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮи©ҰйЁ“гҒ«гҒҜгӮҰгӮ©гғјгғ…гӮҰгӮ©гғјгӮ№гҒҜдҪ•е№ҙгҒ«з”ҹгӮҢгҒҰдҪ•е№ҙгҒ«жӯ»гӮ“гҒ гҒЁгҒӢгҖҒгӮ·гӮЁгӮҜгӮ№гғ”гғӨгҒ®гғ•гӮ©гғӘгӮӘгҒҜе№ҫйҖҡгӮҠгҒӮгӮӢгҒӢгҒЁгҒӢгҖҒжҲ–гҒҜгӮ№гӮігғ„гғҲгҒ®жӣёгҒ„гҒҹдҪңзү©гӮ’е№ҙд»Јй ҶгҒ«дёҰгҒ№гҒҰиҰӢгӮҚгҒЁгҒӢгҒ„гҒҶе•ҸйЎҢгҒ°гҒӢгӮҠеҮәгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮе№ҙгҒ®иӢҘгҒ„гҒӮгҒӘгҒҹж–№гҒ«гӮӮгҒ»гҒјжғіеғҸгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒ§гҒӣгҒҶгҖҒжһңгҒҹгҒ—гҒҰгҒ“гӮҢгҒҢиӢұж–ҮеӯҰгҒӢдҪ•гҒҶгҒ гҒӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҢгҖӮиӢұж–ҮеӯҰгҒҜгҒ—гҒ°гӮүгҒҸжҺӘгҒ„гҒҰ第дёҖж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜдҪ•гҒҶгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒ гҒӢгҖҒжҳҜгҒ§гҒҜеҲ°еә•и§ЈгӮӢзӯҲгҒҢгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүе…ҺгҒ«и§’дёүе№ҙеӢүеј·гҒ—гҒҰгҖҒйҒӮгҒ«ж–ҮеӯҰгҒҜи§ЈгӮүгҒҡгҒҳгҒҫгҒІгҒ гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү гҖҖз§ҒгҒҜгҒқгӮ“гҒӘгҒӮгӮ„гҒөгӮ„гҒӘж…ӢеәҰгҒ§дё–гҒ®дёӯгҒёеҮәгҒҰгҒЁгҒҶгҒЁгҒҶж•ҷеё«гҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҒЁгҒ„гҒөгӮҲгӮҠж•ҷеё«гҒ«гҒ•гӮҢгҒҰд»•иҲһгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮе№ёгҒ«иӘһеӯҰгҒ®ж–№гҒҜжҖӘгҒ—гҒ„гҒ«гҒӣгӮҲгҖҒдҪ•гҒҶгҒӢж–ҜгҒҶгҒӢеҫЎиҢ¶гӮ’жҝҒгҒ—гҒҰиЎҢгҒӢгӮҢгӮӢгҒӢгӮүгҖҒе…¶ж—ҘгҖ…гҖ…гҒҜгҒҫгҒӮз„ЎдәӢгҒ«жёҲгӮ“гҒ§гӮҗгҒҫгҒ—гҒҹгҒҢгҖҒи…№гҒ®дёӯгҒҜеёёгҒ«з©әиҷҡгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮз©әиҷҡгҒӘгӮүдёҖгҒқжҖқгҒ„еҲҮгӮҠгҒҢеҘҪгҒӢгҒӨгҒҹгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒдҪ•гҒ гҒӢдёҚж„үеҝ«гҒӘз…®гҒҲеҲҮгӮүгҒӘгҒ„жј з„¶гҒҹгӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҖҒиҮігӮӢжүҖгҒ«жҪңгӮ“гҒ§гӮҗгӮӢгӮҲгҒҶгҒ§е ӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲгҖҢз§ҒгҒ®еҖӢдәәдё»зҫ©гҖҚпјү
гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»25е№ҙпјҲ1892пјүгҒ«гҒҜжқұдә¬е°Ӯй–ҖеӯҰж Ўи¬ӣеё«гҖҒжҳҺжІ»26е№ҙгҒ«гҒҜжқұдә¬й«ҳзӯүеё«зҜ„еӯҰж ЎгҒ®иӢұиӘһеҳұиЁ—гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—жҳҺжІ»27е№ҙгҒ«гҒҜзҘһзөҢиЎ°ејұгҒҢжҳӮгҒҳгҖҒ12жңҲгҖҒйҺҢеҖүгҒ®еҶҶиҰҡеҜәгҒ«еҸӮзҰ…гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖдёҖж–№гҒ®еӯҗиҰҸгҒҜгҖҒ次第гҒ«еӯҰжҘӯгӮҲгӮҠгӮӮдҝіеҸҘгӮ„е°ҸиӘ¬гҒ«й–ўеҝғгӮ’еӢҹгӮүгҒӣгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢи©ҰйЁ“гҒ гҒӢгӮүдҝіеҸҘгӮ’гӮ„гӮҒгҒҰжә–еӮҷгҒ«еҸ–гӮҠгҒӢгҒӢгӮүгҒҶгҒЁжҖқгҒөгҒЁгҖҒдҝіеҸҘгҒҢй »гӮҠгҒ«жө®гҒӢгӮ“гҒ§жқҘгӮӢгҖҚгҒ»гҒ©гҖҢдҝійӯ”гҒ«йӯ…е…ҘгӮүгӮҢгҖҚгҖҢгӮӮгҒҶеҠ©гҒӢгӮҠгӮ„гҒҶгҒҜгҒӘгҒ„гҖҚпјҲгҖҺеўЁжұҒдёҖж»ҙгҖҸпјүгҒЁиҰіеҝөгҒ—гҖҒжҳҺжІ»25е№ҙгҒ®еӯҰе№ҙжң«и©ҰйЁ“гҒ«иҗҪ第гҒ—гҒҹгҒ“гҒЁгӮ’гҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ«гҒ—гҒҰжҳҺжІ»26е№ҙ3жңҲжң«гҖҒеӨ§еӯҰгӮ’йҖҖеӯҰгҒҷгӮӢгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҢе°ҸеӯҗгҒ®иҖғгҒёгҒ«гҒҰгҒҜгҒӨгҒҫгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮдҪ•гҒ§гӮӮеҚ’жҘӯгҒҷгӮӢгҒҢдёҠеҲҶеҲҘгҒЁеӯҳеҖҷгҖӮйЎҳгҒҸгҒ°д»ҠдёҖжҖқжЎҲгҒӮгӮүгҒҫгҒ»гҒ—гҒҶгҖҚгҖҒгҖҢйіҙгҒҸгҒӘгӮүгҒ°жәҖжңҲгҒ«йіҙгҒ‘гҒ»гҒЁгӮқгҒҺгҒҷгҖҚпјҲжҳҺжІ»25е№ҙ7жңҲ19ж—Ҙжӣёз°ЎпјүгҒЁеӯҗиҰҸгҒ®йҖҖеӯҰгӮ’еј•гҒҚгҒЁгӮҒгҒҹгҒҢгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜиҮӘз«ӢгҒ®йҒ“гӮ’йҒёгӮ“гҒ гҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»25е№ҙ12жңҲгҖҒйҷёзҫҜеҚ—гҒҢзӨҫй•·гӮ’еҠӘгӮҒгӮӢж—Ҙжң¬ж–°иҒһзӨҫгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҒҷгҒ§гҒ«гҖҢж—Ҙжң¬гҖҚгҒ«гҖҢгҒӢгҒ‘гҒҜгҒ—гҒ®иЁҳгҖҚгӮ„гҖҢзҚәзҘӯжӣёеұӢдҝіи©ұгҖҚгҒӘгҒ©гӮ’йҖЈијүгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒжӯЈејҸгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹеҫҢгҒҜгҖҢж—Ҙжң¬гҖҚгҒ«дҝіеҸҘ欄гӮ’иЁӯзҪ®гҒҷгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒдҝіеҸҘгҒ®йқ©ж–°гӮ’жҺЁгҒ—йҖІгӮҒгҒҰиЎҢгҒҸгҖӮ
гҖҖгҒқгҒ—гҒҰеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒз—…ж°—гҒ®иә«гҒ§гҒӮгӮҠгҒӘгҒҢгӮүгҖҒжҳҺжІ»28е№ҙ4жңҲ10ж—ҘгҖҒж—Ҙжё…жҲҰдәүгҒ®еҫ“и»ҚиЁҳиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰдёӯеӣҪгҒёжёЎгҒЈгҒҹгҖӮжҲҰең°гҒ§гҒҜгҖҒжЈ®йҙҺеӨ–гҒЁдјҡгҒ„гҖҒдҝіеҸҘгҒ®гҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гӮ’иӘһгӮҠеҗҲгҒЈгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒ“гҒ®еҫ“и»ҚгҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®з—…зҠ¶гӮ’дёҖеұӨжӮӘеҢ–гҒ•гҒӣгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖеҗҢгҒҳй ғгҖҒжјұзҹігҒҜеӯҗиҰҸгҒ®ж•…йғ·гҒ§гҒӮгӮӢжқҫеұұгҒёгҖҒиӢұиӘһж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰиөҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ