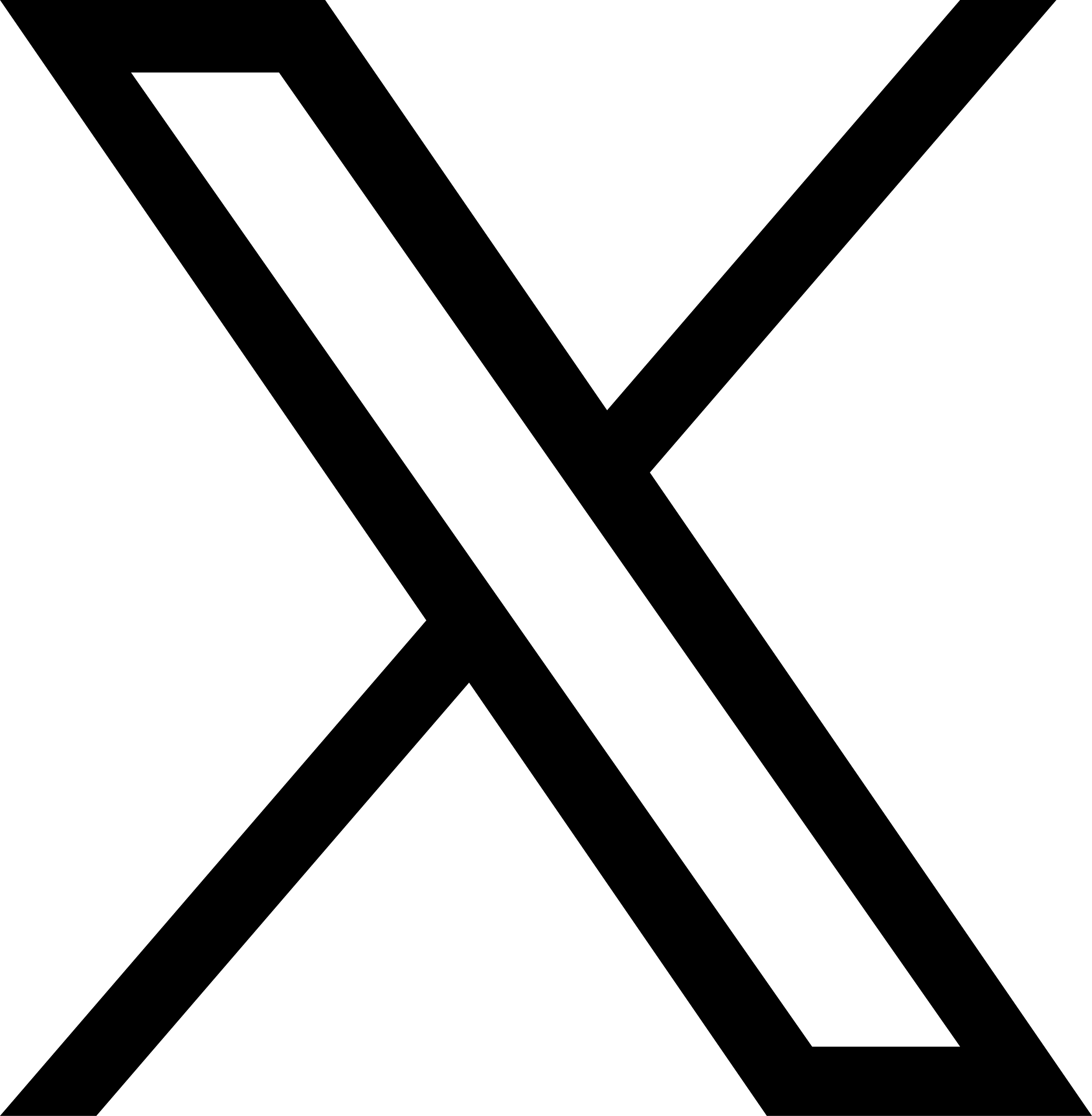жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ
е°ҸиӘ¬еҹ·зӯҶжҷӮд»Јв…
гҖҖжјұзҹігҒҜжҳҺжІ»36е№ҙпјҲ1903пјү1жңҲгҒ«её°еӣҪгҒ—гҒҹгҖӮеҗҢе№ҙ4жңҲгҖҒ第дёҖй«ҳзӯүеӯҰж ЎиӢұиӘһеҳұиЁ—гҖҒжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰж–Ү科еӨ§еӯҰи¬ӣеё«гҒ«е°ұд»»гҒҷгӮӢгҖӮ
гҖҖдёҖй«ҳгҒ§гҒҜжҳҺжІ»36е№ҙ5жңҲ22ж—ҘгҒ«гҖҒжјұзҹігҒ®ж•ҷгҒҲеӯҗгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹи—Өжқ‘ж“ҚгҒҢгҖҢиҸҜеҺігҒ®ж»қгҖҚгҒ«е…Ҙж°ҙгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢ件гҒҢиө·гҒ“гҒЈгҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒе®ҝйЎҢгӮ’гҒ—гҒҰжқҘгҒӘгҒ„и—Өжқ‘гӮ’еҺігҒ—гҒҸеҸұгҒЈгҒҹгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒиҮӘеҲҶгҒ®еҸұиІ¬гҒҢеҺҹеӣ гҒ§и—Өжқ‘гҒҢиҮӘж®әгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁиҖғгҒҲгҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжқұдә¬еёқеӣҪеӨ§еӯҰгҒ§гҒҜгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҢиӢұж–ҮеӯҰжҰӮиӘ¬гҖҚгҒӘгҒ©гӮ’и¬ӣзҫ©гҒҷгӮӢгҖӮиӘһеӯҰгҒ«еҺігҒ—гҒҸзҗҶи«–зҡ„гҒ§з·»еҜҶгҒӘжјұзҹігҒ®жҺҲжҘӯгҒҜгҖҒеүҚд»»иҖ…гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгғ©гғ•гӮ«гғҮгӮЈгӮӘгғ»гғҸгғјгғіпјҲе°Ҹжіүе…«йӣІпјүгҒ®жғ…зҶұзҡ„гҒӘжҺҲжҘӯгҒ«иҰӘгҒ—гӮ“гҒ§гҒ„гҒҹз”ҹеҫ’гҒҹгҒЎгҒ«йҒ•е’Ңж„ҹгӮ’дёҺгҒҲгҒҹгҖӮжјұзҹігҒ®ж•ҷгҒҲеӯҗгҒ®дёҖдәәгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹйҮ‘еӯҗеҒҘдәҢгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖзү№гҒ«жјұзҹіе…Ҳз”ҹгҒ®и¬ӣзҫ©гҒҜгҖҒгҒқгҒ®з ”究гҒ®гӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢж–ҮеӯҰгҒқгӮҢиҮӘиә«гӮ’й‘‘иіһгҒҷгӮӢжҷӮгҒ«еҝ…иҰҒгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢжү№и©•еӯҰгҒ®дёҖз«ҜгӮ’еҲҶжһҗзҡ„гҒ«еҸ–жүұгҒҠгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢжүҖгҒ«йҮҚзӮ№гҒҢжҺӘгҒ„гҒҰгҒӮгҒЈгҒҹзӮәгҒ«гҖҒгғҳгғ«гғіе…Ҳз”ҹгҒ®еҰӮгҒҸз«ӢжҙҫгҒӘиҠёиЎ“гҒҜзҗҶгҒҸгҒӨгҒ¬гҒҚгҒ«гҒ—гҒҰзӣҙиҰҡзҡ„гҒ«й‘‘иіһгҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶз«Ӣе ҙгҒЁгҒҜж—ўгҒ«ж №жң¬зҡ„гҒ«з•°гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲйҮ‘еӯҗеҒҘдәҢгҖҺдәәй–“жјұзҹігҖҸпјү
гҖҖгҒ—гҒӢгҒ—дёҖиҲ¬и¬ӣзҫ©гҒ®гҖҺгғһгӮҜгғҷгӮ№гҖҸгҒ®жҺҲжҘӯгҒҜгҖҒеҪ“жҷӮгҖҒгӮ·гӮ§гӮӨгӮҜгӮ№гғ”гӮўгҒ®еҠҮгҒҢдёҠжј”гҒ•гӮҢдәәж°—гӮ’еҚҡгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮҠгҖҒгҖҢеӨ§е…Ҙз№ҒжҳҢгҖҚпјҲеҗҢпјүгҒ гҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ
гҖҖеё°еӣҪеҫҢгҒ®жјұзҹігҒҜзІҫзҘһзҡ„гҒ«дёҚе®үе®ҡгҒӘзҠ¶ж…ӢгҒҢз¶ҡгҒҸгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдёҚе®үгҒӘж—ҘгҖ…гҒҜеҰ»гҒ®йҸЎеӯҗгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°жҳҺжІ»36е№ҙпјҲ1903пјү6жңҲй ғгҒӢгӮүжҳҺжІ»37е№ҙпјҲ1904пјү5жңҲй ғгҒҫгҒ§з¶ҡгҒ„гҒҹгӮҲгҒҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҰ»гҒ®йҸЎеӯҗгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжў…йӣЁжңҹй ғгҒӢгӮүгҒҗгӮ“пјҸпјјй ӯгҒҢжӮӘгҒҸгҒӘгҒӨгҒҰгҖҒдёғжңҲгҒ«е…ҘгҒӨгҒҰгҒҜзӣҠгҖ…жӮӘгҒҸгҒӘгӮӢдёҖж–№гҒ§гҒҷгҖӮеӨңдёӯгҒ«дҪ•гҒҢзҷӘгҒ«йҡңгӮӢгҒ®гҒӢгҖҒз„Ўжҡ—гҒЁзҷҮзҷӘгӮ’гҒҠгҒ“гҒ—гҒҰгҖҒжһ•гҒЁиЁҖгӮҸгҒҡдҪ•гҒЁгҒ„гҒҜгҒҡгҖҒжүӢеҪ“гӮҠ次第гҒ®гӮӮгҒ®гӮ’ж”ҫгӮҠеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҖӮеӯҗдҫӣгҒҢжіЈгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒӨгҒҰгҒҜжҖ’гӮҠеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҒ—гҖҒжҷӮгҒ«гҒҜдҪ•гҒҢдҪ•гӮ„гӮүгҒ•гҒӨгҒұгӮҠгӮҸгҒ‘гҒҢгӮҸгҒӢгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒиҮӘеҲҶдёҖдәәжҖ’гӮҠеҮәгҒ—гҒҰгҒҜеҪ“гӮҠж•ЈгӮүгҒ—гҒҰеұ…гӮҠгҒҫгҒҷгҖӮгҒ©гҒҶгҒ«гӮӮжүӢгҒҢгҒӨгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮ
пјҲгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјү
гҖҖгҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжјұзҹігҒ®дёҚе®үгҒӘж—ҘгҖ…гҒ®дёӯгҒ§еҹ·зӯҶгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸгҒ®з¬¬дёҖеӣһгҒҜгҖҒжҳҺжІ»38е№ҙпјҲ1905пјү1жңҲзҷәиЎҢгҒ®йӣ‘иӘҢгҖҺгғӣ гғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸ第8巻第4еҸ·гҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒдёҖеӣһйҷҗгӮҠгҒ®гҒӨгӮӮгӮҠгҒ§жӣёгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘеҸҚйҹҝгӮ’е‘јгҒіз¬¬еҚҒеӣһгҒҫгҒ§еҗҢиӘҢгҒ«ж–ӯз¶ҡзҡ„гҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжҳҺжІ»38е№ҙгҒ«гҒҜгҖҺеҗҫиј© гғҸзҢ«гғҮгӮўгғ«гҖҸдёҠзҜҮгҒҢеҲҠиЎҢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮдёҠзҜҮгҒ®жҢҝзөөгӮ’жӢ…еҪ“гҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгғ•гғ©гғігӮ№з•ҷеӯҰгҒӢгӮүеё°еӣҪгҒ—гҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®з”»е®¶гғ»дёӯжқ‘дёҚжҠҳгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҒ•гҒҰжӯЈеІЎеӯҗиҰҸеҗӣгҒЁгҒҜе…ғгҒӢгӮүгҒ®еҸӢдәәгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒз§ҒгҒҢеҖ«ж•ҰгҒ«еұ…гӮӢжҷӮжӯЈеІЎгҒ«дёӢе®ҝгҒ§й–үеҸЈгҒ—гҒҹжЁЎж§ҳгӮ’жүӢзҙҷгҒ«жӣёгҒ„гҒҰйҖҒгӮӢгҒЁгҖҒжӯЈеІЎгҒҜгҒқгӮҢгӮ’гҖҺгғӣгғҲгғҪгӮ®гӮ№гҖҸгҒ«ијүгҒӣгҒҹгҖӮ гҖҺгғӣгғҲгғҪгӮ®гӮ№гҖҸгҒЁгҒҜе…ғгҒӢгӮүй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгҒӨгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҢиҝ‘еӣ гҒ§з§ҒгҒҢж—Ҙжң¬гҒёеё°гҒӨгҒҹжҷӮпјҲжӯЈеІЎгҒҜгӮӮгҒҶжӯ»гӮ“гҒ§еұ…гҒҹпјүз·ЁијҜиҖ…гҒ®иҷҡеӯҗгҒӢгӮүдҪ•гҒӢжӣёгҒ„гҒҰе‘үгӮҢгҒӘгҒ„гҒӢгҒЁеҳұгҒҫгӮҢгҒҹгҒ®гҒ§е§ӢгӮҒгҒҰгҖҺеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҸгҒЁгҒ„гҒөгҒ®гӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҖӮжүҖгҒҢиҷҡеӯҗгҒҢгҒқгӮҢгӮ’иӘӯгӮ“гҒ§гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜдёҚеҸҜгҒҫгҒӣгӮ“гҒЁдә‘гҒөгҖӮиЁігӮ’иҒһгҒ„гҒҰиҰӢгӮӢгҒЁж®өгҖ…гҒӮгӮӢгҖӮд»ҠгҒҜдёёгҒ§еҝҳгӮҢгҒҰд»•иҲһгҒӨгҒҹгҒҢгҖҒе…ҺгҒ«и§’е°ӨгӮӮгҒ гҒЁжҖқгҒӨгҒҰжӣёгҒҚзӣҙгҒ—гҒҹгҖӮ гҖҖд»ҠеәҰгҒҜиҷҡеӯҗгҒҢеӨ§гҒ„гҒ«иіһгӮҒгҒҰгҒқгӮҢгӮ’гҖҺгғӣгғҲгғҪгӮ®гӮ№гҖҸгҒ«ијүгҒӣгҒҹгҒҢгҖҒе®ҹгҒҜгҒқгӮҢгҒҜдёҖеӣһгҒҚгӮҠгҒ®гҒӨгӮӮгӮҠгҒ гҒӨгҒҹгҒ®гҒ гҖӮгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢиҷҡеӯҗгҒҢйқўзҷҪгҒ„гҒӢгӮүз¶ҡгҒҚгӮ’жӣёгҒ‘гҒЁгҒ„гҒөгҒ®гҒ§гҖҒгҒ гӮ“пјҸпјјжӣёгҒ„гҒҰеұ…гӮӢгҒҶгҒЎгҒ«гҒӮгӮ“гҒӘгҒ«й•·гҒҸгҒӘгҒӨгҒҰдәҶгҒӨгҒҹгҖӮгҒЁгҒ„гҒөгӮ„гҒҶгҒӘиЁігҒ гҒӢгӮүгҖҒз§ҒгҒҜгҒҹгӮһеҒ¶з„¶гҒқгӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҒЁгҒ„гҒөгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒеҲҘгҒ«еҪ“жҷӮгҒ®ж–ҮеЈҮгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒ©гҒҶгҒӢгҒҶгҒЁгҒ„гҒөиҖғгӮӮдҪ•гӮӮгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮгҒҹгӮһжӣёгҒҚгҒҹгҒ„гҒӢгӮүжӣёгҒҚгҖҒдҪңгӮҠгҒҹгҒ„гҒӢгӮүдҪңгҒӨгҒҹгҒҫгӮқгҒ§гҖҒгҒӨгҒҫгӮҠиЁҖгҒёгҒ°з§ҒгҒҢгҒӮгӮқгҒ„гҒөжҷӮж©ҹгҒ«йҒ”гҒ—гҒҰеұ…гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ пјҲгҖҢжҷӮж©ҹгҒҢжқҘгҒҰгӮҗгҒҹгӮ“гҒ вҖ•еҮҰеҘідҪңиҝҪжҮҗи«ҮгҖҚпјү
гҖҖжқұйўЁеҗӣиӢҰжІҷејҘеҗӣзҡҶеӢқжүӢгҒӘдәӢгӮ’з”іеҖҷеӨ«ж•…гҒ«еӨӘе№ігҒ®йҖёж°‘гҒ«еҖҷзҸҫе®ҹдё–з•ҢгҒ«гҒӮгҒ®дё»зҫ©гҒ§гҒҜеҰӮдҪ•гҒЁеӯҳеҖҷеҫЎеҸҚеҜҫеҫЎе°ӨгҒ«еҖҷгҖӮжјұзҹіе…Ҳз”ҹгӮӮеҸҚеҜҫгҒ«еҖҷгҖӮ
гҖҖеҪјгӮүгҒ®дә‘гҒөжүҖгҒҜзҡҶзңҹзҗҶгҒ«еҖҷ然гҒ—еҸӘдёҖйқўгҒ®зңҹзҗҶгҒ«еҖҷгҖӮжұәгҒ—гҒҰдҪңиҖ…гҒ®дәәз”ҹиҰігҒ®е…ЁйғЁгҒ«з„Ўд№Ӣж•…е…¶иҫәгҒҜеҫЎдәҶзҹҘиў«дёӢеҖҷгҖӮгҒӮгӮҢгҒҜз·ҸдҪ“гҒҢи«·еҲәгҒ«еҖҷгҖӮзҸҫд»ЈгҒ«гҒӮгӮ“гҒӘи«·еҲәгҒҜе°ӨгӮӮйҒ©еҲҮгҒЁеӯҳгҒҳзҢ«дёӯгҒ«еҸҺгӮҒеҖҷгӮӮгҒ—е°Ҹз”ҹгҒ®еҖӢжҖ§и«–гӮ’и«–ж–ҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒӢгҒ‘гҒ°еҸҚеҜҫгҒ®ж–№йқўгҒЁеҸҢж–№гҒ®еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢжүҖгӮ’иӯ°и«–иҮҙгҒ—еәҰгҒЁеӯҳеҖҷгҖӮ
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ8жңҲ7ж—Ҙз•”жҹіиҠҘиҲҹе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖгҖҺзҢ«гҖҸгҒ§гҒҷгҒӢгҖҒгҒӮгӮҢгҒҜжңҖеҲқгҒҜдҪ•гӮӮгҒӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й•·гҒҸз¶ҡгҒ‘гҒҰжӣёгҒ“гҒҶгҒЁгҒ„гҒөиҖғгҒҲгӮӮгҒӘгҒ—гҖҒи…№жЎҲгҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒӢгӮүз„Ўи«–дёҖеӣһгҒ гҒ‘гҒ§д»•иҲһгҒөз©ҚгӮҠгҖӮгҒҫгҒҹж–ҜгҒҸгҒҫгҒ§ дё–й–“гҒ®и©•еҲӨгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҶгӮ„гҒҶгҒЁгҒҜе°‘гҒ—гӮӮжҖқгҒӨгҒҰеұ…гӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮжңҖеҲқиҷҡеӯҗеҗӣгҒӢгӮүгҖҢдҪ•гҒӢжӣёгҒ„гҒҰе‘үгӮҢгҖҚгҒЁй јгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮҢгӮ’дёҖеӣһжӣёгҒ„гҒҰгӮ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҒеәҰгҒқгҒ®й ғж–Үз« з ”з©¶дјҡгҒЁгҒ„гҒөгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒӨгҒҰгҖҒгҖҺзҢ«гҖҸгҒ®еҺҹзЁҝгӮ’гҒқгҒ®дјҡгҒёеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгӮ’е…¶еёӯгҒ§еҜ’е·қйј йӘЁеҗӣгҒҢжң—иӘӯгҒ—гҒҹгҒ•гҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨҡеҲҶжң—иӘӯгҒ®д»•ж–№гҒ§гӮӮж—ЁгҒӢгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҒӣгҒҶгҖҒз”ҡгҒҸе…¶еёӯгҒ§е–қйҮҮгӮ’еҚҡгҒ—гҒҹгҒ•гҒҶгҒ§гҒҷгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖеҰҷгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжӣёгҒ„гҒҰд»•иҲһгҒӨгҒҹеҪ“еә§гҒҜгҖҒ全然иғёдёӯгҒ®ж–Үеӯ—гӮ’еҗҗгҒҚеҮәгҒ—гҒҰд»•иҲһгҒӨгҒҰгҖҒгӮӮгҒҶжӯӨж¬ЎгҒ«гҒҜдҪ•гӮӮжӣёгҒҸгӮ„гҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜз„ЎгҒ„гҒЁжҖқгҒҶзЁӢгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒжүЁеҚҒж—ҘзөҢгҒЎе»ҝж—ҘзөҢгҒӨгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁж—ҘгҖ…гҒ®еҮәжқҘдәӢгӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҒҰгҖҒеҸҲж–°гҒҹгҒ«жӣёгҒҚгҒҹгҒ„гӮ„гҒҶгҒӘж„ҹжғігӮӮ湧гҒ„гҒҰжқҘгӮӢгҖӮжқҗж–ҷгӮӮи’җгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮж–ҜгӮ“гҒӘйўЁгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҺзҢ«гҖҸгҒӘгҒ©гҒҜжӣёгҒӢгҒҶгҒЁжҖқгҒёгҒ°е№ҫгӮүгҒ§гӮӮй•·гҒҸз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮ
пјҲгҖҢж–ҮеӯҰи«ҮгҖҚпјү
гҖҖдёҖж–№гҖҒжјұзҹігҒ«гҖҺгғӣгғҲгғҪгӮ®гӮ№гҖҸгҒёгҒ®еҹ·зӯҶгӮ’гҒҷгҒҷгӮҒгҒҹй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҒҜж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжӯӨй ғгӮҸгӮҢзӯүд»Ій–“гҒ®ж–Үз« зҶұгҒҜйқһеёёгҒ«зӣӣгӮ“гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮж®ҶгҒ©жҜҺжңҲгҒ®гӮ„гҒҶгҒ«йӣҶдјҡгҒ—гҒҰж–Үз« дјҡгӮ’й–ӢгҒ„гҒҰгӮҗгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҜеӯҗиҰҸеұ…еЈ«з”ҹеүҚгҒӢгӮүгҒӮгҒӨгҒҹдјҡгҒ§гҖҒгҖҢж–Үз« гҒ«гҒҜеұұгҒҢгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜ駄зӣ®гҒ гҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒөеӯҗиҰҸеұ…еЈ«гҒ®дё»ејөгҒ«еҹәгҒ„гҒҰгҖҒгӮҸгӮҢзӯүгҒҜгҒқгҒ®ж–Үз« дјҡгӮ’еұұдјҡгҒЁе‘јгӮ“гҒ§гӮҗгҒҹгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүйҒӮгҒ«жқҘгӮӢдёҖдәҢжңҲгҒ®дҪ•ж—ҘгҒ«ж №еІёгҒ®еӯҗиҰҸеәөгҒ§еұұдјҡгӮ’гӮ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгҒӨгҒҰгӮҗгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ«дҪ•гҒӢжӣёгҒ„гҒҰгҒҝгҒҰгҒҜгҒ©гҒҶгҒӢгҖҒгҒқгҒ®иЎҢгҒҚгҒҢгҒ‘гҒ«гҒӮгҒӘгҒҹгҒ®е®…гҒёз«ӢеҜ„гӮӢгҒӢгӮүгҒЁгҒ„гҒөгҒ“гҒЁгӮ’зҙ„жқҹгҒ—гҒҹгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖгҒ“гҒ®гҖҢжҲ‘иј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚвҖ•жјұзҹіж°ҸгҒҜз§ҒгҒҢиЎҢгҒӨгҒҹжҷӮгҒ«гҒҜеҺҹзЁҝзҙҷгҒ®жӣёгҒҚеҮәгҒ—дёүеӣӣиЎҢжҳҺгҒ‘гҒҹгҒҫгӮқгҒ«гҒ—гҒҰзҪ®гҒ„гҒҰгҖҒгҒҫгҒ еҗҚгҒҜгҒӨгҒ‘гҒҰгӮҗгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮеҗҚеүҚгҒҜгҖҢзҢ«дјқгҖҚгҒ«гҒ—гӮҲгҒҶгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒЁгӮӮжӣёгҒҚеҮәгҒ—гҒ®з¬¬дёҖеҸҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖҢеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒ«е…¶е„ҳз”ЁгҒІгӮҲгҒҶгҒӢгҒЁжҖқгҒӨгҒҰжұәгҒ—гҒӢгҒӯгҒҰгӮҗгӮӢгҒЁгҒ®дәӢгҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮз§ҒгҒҜгҖҢеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚгҒ®ж–№гҒ«иіӣжҲҗгҒ—гҒҹгҖӮвҖ•гҒ“гӮҢгҒҜж–Үз« дјҡе“ЎдёҖеҗҢгҒ«гҖҒгҖҢе…ҺгҒ«и§’еӨүгҒӨгҒҰгӮҗгӮӢгҖӮгҖҚгҒЁгҒ„гҒөзӮ№гҒ«ж–јгҒҰиіӣиҫһгӮ’е‘ҲгҒӣгҒ—гӮҒгҒҹгҖӮгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰжҳҺжІ»дёүеҚҒе…«е№ҙдёҖжңҲзҷәиЎҢгҒ®гғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҒ®е·»й ӯгҒ«ијүгҒӣгҒҹгҖӮжӯӨгҒ®дёҖзҜҮгҒҢеҝҪгҒЎжјұзҹіж°ҸгҒ®еҗҚгӮ’ж–ҮеЈҮгҒ«еҳ–гҖ…гҒҹгӮүгҒ—гӮҒгҒҹдәӢгҒҜдё–дәәгҒ®иЁҳжҶ¶гҒ«ж–°гҒҹгҒӘгӮӢжүҖгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
пјҲй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҺжјұзҹіж°ҸгҒЁз§ҒгҖҸпјү
гҖҖжҳҺжІ»38е№ҙпјҲ1905пјүгҒӢгӮүжҳҺжІ»39е№ҙпјҲ1906пјүгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҢеҖ«ж•ҰеЎ”гҖҚгҖҒгҖҢгӮ«гғјгғ©гӮӨгғ«еҚҡзү©йӨЁгҖҚгҖҒгҖҢе№»еҪұгҒ®зӣҫгҖҚгҖҒгҖҢзҗҙгҒ®гҒқгӮүйҹігҖҚгҖҒгҖҢдёҖеӨңгҖҚгҖҒгҖҢи–ӨйңІиЎҢгҖҚгҖҒгҖҢеқҠгҒЈгҒЎгӮ„гӮ“гҖҚгҖҒгҖҢиҚүжһ•гҖҚгҒӘгҒ©гӮ’зӣёж¬ЎгҒ„гҒ§зҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҺеқҠгҒӨгҒЎгӮ„гӮ“гҖҸгҒ®дёӯгҒ®еқҠгҒӨгҒЎгӮ„гӮ“гҒЁгҒ„гҒҶдәәзү©гҒҜжҲ–зӮ№гҒҫгҒ§гҒҜж„ӣгҒҷгҒ№гҒҸгҖҒеҗҢжғ…гӮ’иЎЁгҒҷгҒ№гҒҚдҫЎеҖӨгҒ®гҒӮгӮӢдәәзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҚҳзҙ”йҒҺгҒҺгҒҰзөҢйЁ“гҒҢд№ҸгҒ—йҒҺгҒҺгҒҰзҸҫд»ҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӨҮйӣ‘гҒӘзӨҫдјҡгҒ«гҒҜеҶҶжәҖгҒ«з”ҹеӯҳгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„дәәгҒ гҒӘгҒЁиӘӯиҖ…гҒҢж„ҹгҒҳгҒҰеҗҲзӮ№гҒ—гҒ•гҒҲгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ§дҪңиҖ…гҒ®дәәз”ҹиҰігҒҢиӘӯиҖ…гҒ«еҫ№гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒҰгӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲгҖҢж–ҮеӯҰи«ҮгҖҚпјү
гҖҖгҒҹгҒ гҒҚгӮҢгҒ„гҒ«гҒҶгҒӨгҒҸгҒ—гҒҸжҡ®гӮүгҒҷгҖҒеҚігҒЎи©©дәәзҡ„гҒ«гҒҸгӮүгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҜз”ҹжҙ»гҒ®ж„Ҹзҫ©гҒ®дҪ•еҲҶдёҖгҒӢзҹҘгӮүгҒ¬гҒҢгӮ„гҒҜгӮҠжҘөгӮҒгҒҰеғ…е°‘гҒӘйғЁеҲҶгҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ§гҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдё»дәәе…¬гҒ§гҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮҢгӮӮгҒ„гҒ„гҒҢгӮ„гҒҜгӮҠд»ҠгҒ®дё–з•ҢгҒ«з”ҹеӯҳгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ®гӮҲгҒ„жүҖгӮ’йҖҡгҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгӮӨгғ–гӮ»гғіжөҒгҒ«еҮәгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮ
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ26ж—ҘйҲҙжңЁдёүйҮҚеҗүе®ӣжӣёз°Ўпјү
гҖҖз§ҒгҒ®гҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дё–й–“жҷ®йҖҡгҒ«гҒ„гҒҶе°ҸиӘ¬гҒЁгҒҜе…ЁгҒҸеҸҚеҜҫгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§жӣёгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе”ҜгҒ дёҖзЁ®гҒ®ж„ҹгҒҳ--зҫҺгҒҸгҒ—гҒ„ж„ҹгҒҳгҒҢиӘӯиҖ…гҒ®й ӯгҒ«ж®ӢгӮҠгҒ•гҒҲгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҖӮгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«дҪ•гӮӮзү№еҲҘгҒӘзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ•гӮҢгҒ°гҒ“гҒқгҖҒгғ—гғӯгғ„гғҲгӮӮз„ЎгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒдәӢ件гҒ®зҷәеұ•гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮ
пјҲи«Үи©ұгҖҢдҪҷгҒҢгҖҺиҚүжһ•гҖҸгҖҚпјү
гҖҖйҸЎеӯҗгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҷӮжңҹгҒ®жјұзҹігҒ®еҹ·зӯҶгҒ®ж§ҳеӯҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеҲҘгҒ«жң¬иҒ·гҒ«е°ҸиӘ¬гӮ’жӣёгҒҸгҒЁгҒ„гҒөж°—гӮӮгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒёгҖҒй•·гҒ„й–“жӣёгҒҚгҒҹгҒҸгҒҰжӣёгҒҚгҒҹгҒҸгҒҰе ӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гӮ’гҒ“гӮүгҒёгҒҰгӮҗгҒҹеҪўгҒ гҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒжӣёгҒҚеҮәгҒӣгҒ°ж®ҶгҒ©дёҖж°—е‘өжҲҗгҒ«з¶ҡгҒ‘ж§ҳгҒ«жӣёгҒ„гҒҹгӮ„гҒҶгҒ§гҒҷгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүжӣёгҒ„гҒҰгӮҗгӮӢгҒ®гӮ’иҰӢгҒҰгӮҗгӮӢгҒЁгҒ„гҒӢгҒ«гӮӮжҘҪгҒ•гҒҶгҒ§еӨңгҒӘгӮ“гҒһгӮӮдёҖз•ӘйҒ…гҒҸгҒҰеҚҒдәҢжҷӮдёҖжҷӮй ғгҒ§гҖҒеӨ§жҰӮгҒҜеӯҰж ЎгҒӢгӮүеё°гҒӨгҒҰжқҘгҒҰгҖҒеӨ•йЈҹеүҚеҫҢеҚҒжҷӮй ғиҝ„гҒ«иӢҰгӮӮгҒӘгҒҸжӣёгҒ„гҒҰдәҶгҒөжңүж§ҳгҒ§гҒ—гҒҹгҖӮпјҲдёӯз•ҘпјүеӮҚгҒ§иҰӢгҒҰеұ…гӮӢгҒЁгғҡгғігӮ’еҹ·гҒӨгҒҰеҺҹзЁҝз”ЁзҙҷгҒ«еҗ‘гҒёгҒ°зӣҙгҒЎгҒ«е°ҸиӘ¬гҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒЁгҒ„гҒӨгҒҹе…·еҗҲгҒ«ејөгӮҠеҲҮгҒӨгҒҰеұ…гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ гҒӢгӮүжІ№гҒҢд№—гҒӨгҒҰгӮҗгҒҹгҒ©гҒ“гӮҚгҒ®ж®өгҒҳгӮ„гҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒҷгӮӮгҒ®жӣёгҒҚжҗҚгҒҳгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒөгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒе…ЁгҒҸгҒЁгҒ„гҒӨгҒҰгҒ„гҒ„зЁӢгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ
пјҲгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјү
гҖҖжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ11ж—ҘгҒӢгӮүгҒҜгҖҒгҖҢжңЁжӣңж—ҘгҒ®еҚҲеҫҢдёүжҷӮгҒӢгӮүгӮ’йқўдјҡж—ҘгҒЁе®ҡеҖҷгҖҚпјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ7ж—Ҙд»ҳйҮҺжқ‘дјқеӣӣе®ӣжӣёз°ЎпјүгҒЁгҒ—гҖҒгҖҢжңЁжӣңдјҡгҖҚгҒҢй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢжңЁжӣңдјҡгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҖҒеҜәз”°еҜ…еҪҰгҖҒйҲҙжңЁдёүйҮҚеҗүгҖҒжЈ®з”°иҚүе№ігҖҒйҳҝйғЁж¬ЎйғҺгӮүгҒҢйӣҶгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹжјұзҹігҒ®жҷ©е№ҙгҖҒеӨ§жӯЈ4е№ҙпјҲ1916пјүгҒ«гҒҜгҖҒиҸҠжұ еҜӣгҖҒиҠҘе·қйҫҚд№Ӣд»ӢгҖҒд№…зұіжӯЈйӣ„гӮүгҒҢгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰжңЁжӣңдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжјұзҹіе…Ҳз”ҹгҒ®йқўдјҡж—ҘгҒҜйҖұгҒ®жңЁжӣңж—ҘгҒ§жңүгӮӢгҖӮе…¶ж—ҘгҒ®еӨ•ж–№гҒӢгӮүжјұзҹіе…Ҳз”ҹгҒ®й–ҖгҒ«еҮәе…ҘгҒҷгӮӢиӢҘгҒ„йҖЈдёӯгҒҢйӣҶгҒҫгҒӨгҒҰгҖҒеӢқжүӢгҒӘ無駄и©ұгӮ’гҒҷгӮӢгҒ®гҒҢеёёдҫӢгҒ«жҲҗгҒӨгҒҰеұ…гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜйҡҸеҲҶж—§гҒҸгҒӢгӮүгҒ®д»•жқҘгӮҠгҒ§гҖҒд»ҠгҒ«иҮігӮӢгӮӮйҖЈз¶ҝгҒЁгҒ—гҒҰи·ЎгӮ’зө¶гҒҹгҒӘгҒ„гҖӮе°ӨгӮӮйЎ”и§ҰгҒҜеӨ§еҲҶеӨүгҒӨгҒҹгҖӮеҲқжңҹгҒ®еҚғ駄жңЁжҷӮд»ЈгҒ«гҒҜгҖҒй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҒеқӮжң¬еӣӣж–№еӨӘпјҲжӯӨдәҢдәәгҒҜгҒҠејҹеӯҗгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјүеҜәз”°еҜ…еҪҰгҖҒжқҫж №жқұжҙӢеҹҺгҒӘгҒ©гҖҒж—ўгҒ«дёҖ家гӮ’жҲҗгҒ—гҒҹдәәгҖ…гҒ®йЎ”гӮӮжҷӮгҖ…иҰӢжҺӣгҒ‘гҒҰгҖҒгҒӨгӮһгҒ„гҒҰдёүйҮҚеҗүгҖҒиұҠйҡҶгҖҒиҮје·қгҖҒд»ҠгҒҜ第八й«ҳзӯүеӯҰж ЎгҒ®зҫ…з”ёиӘһгӮ’еҸ—гҒ‘жҢҒгҒӨгҒҰгҒ„еұ…гӮӢдёӯе·қиҠіеӨӘйғҺгҒӘгҒһгҒҢйҮҚгҒӘгӮӢеҸӮиҖ…гҒ§жңүгҒӨгҒҹгҖӮ
пјҲгҖҢжјұзҹіеұұжҲҝеә§и«ҮгҖҚпјү