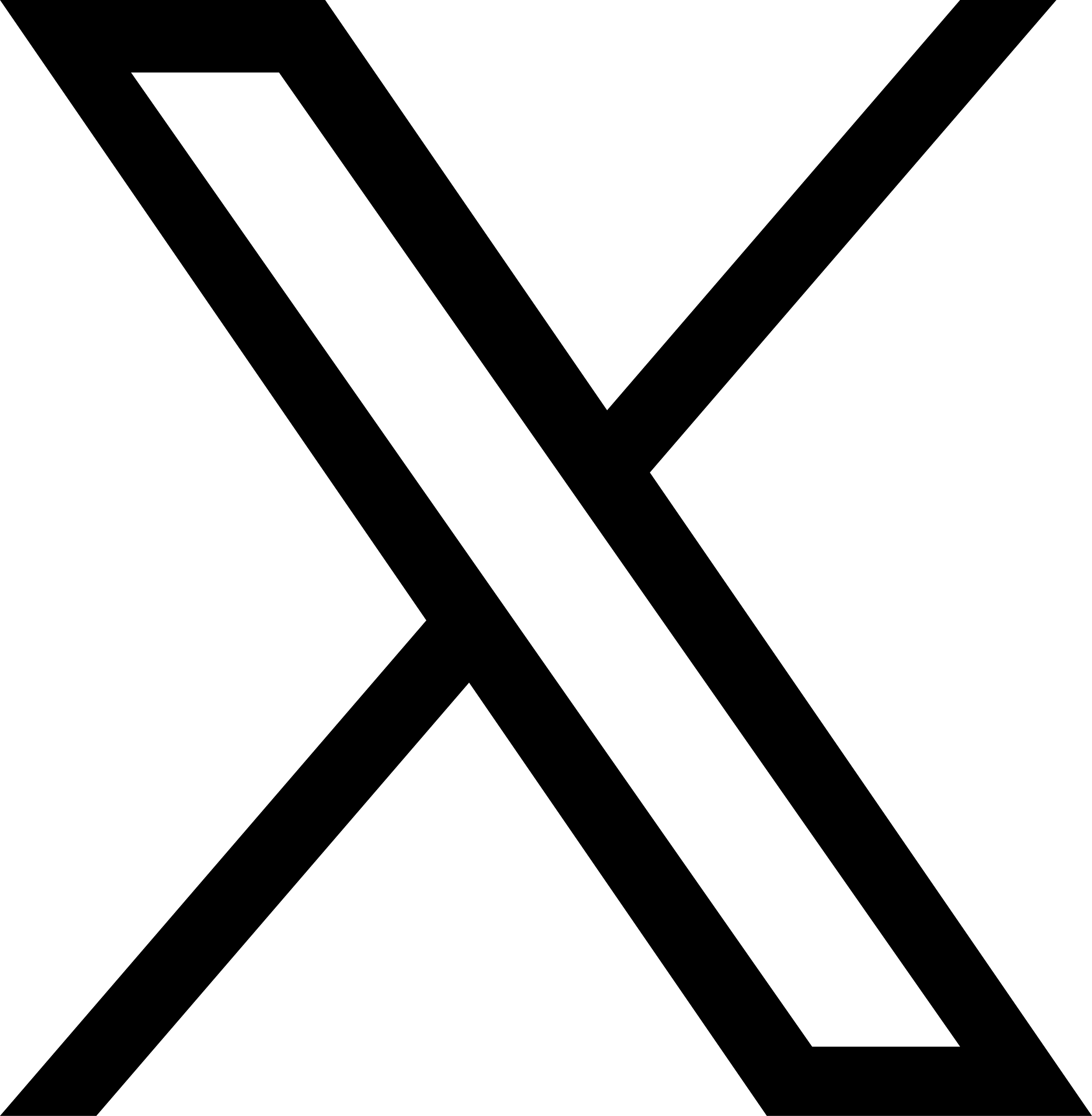жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ
жқҫеұұгғ»зҶҠжң¬жҷӮд»Ј
жқҫеұұжҷӮд»Ј
гҖҖжҳҺжІ»28е№ҙпјҲ1895пјү4жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜгҖҒеҸӢдәәиҸ…иҷҺйӣ„гҒ®ж–Ўж—ӢгҒ§гҖҒж„ӣеӘӣзңҢе°ӢеёёдёӯеӯҰж ЎгҒёиӢұиӘһгҒ®ж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰиөҙд»»гҒ—гҒҹгҖӮжјұзҹігҒ®дҝёзөҰгҒҜж Ўй•·гӮҲгӮҠгӮӮй«ҳгҒҸгҖҒжңҲйЎҚ80еҶҶгҒЁгҒ„гҒҶз ҙж јгҒ®еҫ…йҒҮгҒ гҒЈгҒҹгҖӮжқҫеұұгҒҜгҒ®гҒЎгҒ«гҖҺеқҠгҒЈгҒЎгӮ„гӮ“гҖҸгҒ®иҲһеҸ°гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ
гҖҖеӯҰж ЎгӮ’еҮәгҒҰгҒӢгӮүдјҠдәҲгҒ®жқҫеұұгҒ®дёӯеӯҰгҒ®ж•ҷеё«гҒ«жҡ«гҒҸгҒ„гҒӨгҒҹгҖҒгҒӮгҒ®гҖҺеқҠгҒЎгӮ„гӮ“гҖҸгҒ«гҒӮгӮӢгҒһгҒӘгӮӮгҒ—гҒ®иЁӣгӮ’дҪҝгҒөдёӯеӯҰгҒ®з”ҹеҫ’гҒҜгҒ“гӮқгҒ®йҖЈдёӯгҒ гҖҒеғ•гҒҜгҖҺеқҠгҒЎгӮ„гӮ“гҖҸиҰӢгҒҹгӮҲгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгӮ„гӮҠгҒҜгҒ—гҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгӮҲгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—гҒӮгҒ®дёӯгҒ«гҒӢгҒ„гҒҹжё©жіүгҒӘгӮ“гҒӢгҒҜгҒӮгҒӨгҒҹгҒ—гҖҒиөӨжүӢжӢӯгӮ’гҒ•гҒ’гҒҰгҒӮгӮӢгҒ„гҒҹгҒ“гҒЁгӮӮдәӢе®ҹгҒ гҖҒгӮӮгҒҶдёҖгҒӨеӣ°гӮӢгҒ®гҒҜжқҫеұұдёӯеӯҰгҒ«гҒӮгҒ®е°ҸиӘ¬гҒ®дёӯгҒ®еұұеөҗгҒЁгҒ„гҒөз¶ҪеҗҚгҒ®ж•ҷеё«гҒЁеҜёеҲҶгӮӮйҒ•гҒҜгҒ¬гҒ®гҒҢгӮҗгӮӢгҒЁгҒ„гҒөгҒ®гҒ§жјұзҹігҒҜгҒӮгҒ®з”·гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’гҒӢгҒ„гҒҹгӮ“гҒ гҒЁгҒ„гҒҜгӮҢгҒҰгӮӢгҒ®гҒ гҖҒжұәгҒ—гҒҰгҒқгӮ“гҒӘгҒӨгӮӮгӮҠгҒўгӮ„гҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒӢгӮүй–үеҸЈгҒ—гҒҹгҖӮ
пјҲи«Үи©ұгҖҢеғ•гҒ®жҳ”гҖҚпјү
гҒ—гҒӢгҒ—жјұзҹігҒҜгҖҒиҮӘиә«гҒ®ж•ҷеё«гҒЁгҒ—гҒҰгҒ®йҒ©жҖ§гҒ«з–‘гҒ„гӮ’жҠұгҒ„гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ
гҖҖдҪҷгҒҜж•ҷиӮІиҖ…гҒ«йҒ©гҒ•гҒҡгҖҒж•ҷиӮІе®¶гҒ®иіҮж јгӮ’жңүгҒӣгҒ–гӮҢгҒ°гҒӘгӮҠгҖҒе…¶дёҚйҒ©еҪ“гҒӘгӮӢз”·гҒҢгҖҒзіҠеҸЈгҒ®еҸЈгӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҖҒдёҖз•Әеҫ—жҳ“гҒҚгӮӮгҒ®гҒҜгҖҒж•ҷеё«гҒ®дҪҚең°гҒӘгӮҠгҖҒжҳҜзҸҫд»ҠгҒ®ж—Ҙжң¬гҒ«гҖҒзңҹгҒ®ж•ҷиӮІе®¶гҒӘгҒҚгӮ’зӨәгҒҷгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒзҸҫд»ҠгҒ®жӣёз”ҹгҒҜгҖҒдјјйқһж•ҷиӮІе®¶гҒ§гӮӮеҫЎиҢ¶гӮ’жҝҒгҒ—гҒҰж•ҷжҺҲгҒ—еҫ—гӮӢгҒЁдә‘гҒҶгҖҒжӮІгҒ—гӮҖгҒ№гҒҚдәӢе®ҹгӮ’зӨәгҒҷгӮӮгҒ®гҒӘгӮҠ
пјҲгҖҢж„ҡиҰӢж•°еүҮгҖҚпјү
гҖҖзЁӢгҒӘгҒҸж—Ҙжё…жҲҰдәүгҒ®еҫ“и»ҚиЁҳиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰдёӯеӣҪгҒ«жёЎгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹеӯҗиҰҸгҒҢеё°еӣҪгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еӯҗиҰҸгҒҜеё°еӣҪгҒ®йҖ”дёҠгҒ§е–ҖиЎҖгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒзҷӮйӨҠгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®жқҫеұұеё°йғ·гҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒҢдёҠдә¬гҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҒ®дә”еҚҒдҪҷж—Ҙй–“гҖҒдёӢе®ҝгҒ®пј‘йҡҺгӮ’з—…иә«гҒ®еӯҗиҰҸгҒ«иІёгҒ—дёҺгҒҲгҖҒиҮӘиә«гҒҜ2йҡҺгҒ§жҡ®гӮүгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜгҖҒгҖҢе°Ҹеӯҗиҝ‘й ғдҝій–ҖгҒ«е…ҘгӮүгӮ“гҒЁеӯҳеҖҷеҫЎй–‘жҡҮгҒ®зҜҖгҒҜеҫЎй«ҳзӨәгӮ’д»°гҒҺгҒҹгҒҸеҖҷгҖҚпјҲжҳҺжІ»28е№ҙ5жңҲ26ж—ҘеӯҗиҰҸе®ӣжӣёз°ЎпјүгҒЁиҝ°гҒ№гҖҒгҖҢж„ҡйҷҖд»ҸгҖҚгҒЁеҸ·гҒ—гҒҰеӯҗиҰҸгҒ®дҝіеҸҘд»Ій–“гҒ«еҠ гӮҸгҒЈгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеӯҗиҰҸгҒҢдёҠдә¬гҒ—гҒҰгҒӢгӮүгҒҜгҖҒжјұзҹігҒҜеҸҘзЁҝгӮ’йҖҒгӮҠгҖҒеӯҗиҰҸгҒ«и©•гӮ’жұӮгӮҒгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖгҖҖеғ•гҒҜдәҢйҡҺгҒ«еұ…гӮӢеӨ§е°ҶгҒҜдёӢгҒ«еұ…гӮӢгҖӮе…¶гҒҶгҒЎжқҫеұұдёӯеӯҰгҒ®дҝіеҸҘгӮ’йҒЈгӮӢй–ҖдёӢз”ҹгҒҢйӣҶгҒҫгҒӨгҒҰжқҘгӮӢгҖӮеғ•гҒҢеӯҰж ЎгҒӢгӮүеё°гҒӨгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁжҜҺж—ҘгҒ®гӮ„гҒҶгҒ«еӨҡеӢўжқҘгҒҰеұ…гӮӢгҖӮеғ•гҒҜжң¬гӮ’иӘӯгӮҖдәӢгӮӮгҒ©гҒҶгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮеҮәжқҘгӮ“гҖӮе°ӨгӮӮеҪ“жҷӮгҒҜгҒӮгҒҫгӮҠжң¬гӮӮиӘӯгӮҖж–№гҒ§гӮӮз„ЎгҒӢгҒӨгҒҹгҒҢе…ҺгҒ«и§’иҮӘеҲҶгҒ®жҷӮй–“гҒЁгҒ„гҒөгӮӮгҒ®гҒҢз„ЎгҒ„гҒ®гҒ гҒӢгӮүжӯўгӮҖгӮ’еҫ—гҒҡдҝіеҸҘгӮ’дҪңгҒӨгҒҹгҖӮе…¶гҒӢгӮүеӨ§е°ҶгҒҜжҳјгҒ«гҒӘгӮӢгҒЁи’Із„јгҒҚгӮ’еҸ–гӮҠеҜ„гҒӣгҒҰеҫЎжүҝзҹҘгҒ®йҖҡгӮҠгҒҙгҒЎгӮ„пјҸпјјгҒЁйҹігӮ’гҒ•гҒӣгҒҰйЈҹгҒөгҖӮе…¶гӮҢгӮӮзӣёи«Үз„ЎгҒҸиҮӘеҲҶгҒ§еӢқжүӢгҒ«е‘ҪгҒҳгҒҰеӢқжүӢгҒ«йЈҹгҒөгҖӮ
пјҲгҖҢжӯЈеІЎеӯҗиҰҸгҖҚпјү
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜжҳҺжІ»28е№ҙпјҲ1895пјү10жңҲдёӯж—¬гҒ«жқҫеұұгӮ’зҷәгҒЈгҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒ®дҝіеҸҘгҒ®дёӯгҒ§гӮӮжңҖгӮӮжңүеҗҚгҒӘеҸҘгҒ®1гҒӨгҖҒгҖҢжҹҝгҒҸгҒёгҒ°йҗҳгҒҢйіҙгӮӢгҒӘгӮҠжі•йҡҶеҜәгҖҚгҒҜгҖҒдёҠдә¬гҒ®йҖ”дёӯгҒ§з«ӢгҒЎеҜ„гҒЈгҒҹеҘҲиүҜгҒ§и© гҒҫгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖжҳҺжІ»28е№ҙпјҲ1895пјү12жңҲгҒ«гҒҜгҖҒжјұзҹігҒҜдёӯж №йҸЎеӯҗпјҲйҸЎгҖӮжҲёзұҚеҗҚгҒҜгӮӯгғЁпјүгҒЁиҰӢеҗҲгҒ„гӮ’гҒ—е©ҡзҙ„гӮ’гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҸЎеӯҗгҒ®зҲ¶гҖҒдёӯж №йҮҚдёҖгҒҜиІҙж—ҸйҷўжӣёиЁҳе®ҳй•·гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҸЎеӯҗгҒҜгҒқгҒ®й•·еҘігҒ гҒЈгҒҹгҖӮжјұзҹігҒҜйҸЎеӯҗгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒӨгҒҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹжғігӮ’е‘ЁеӣІгҒ«жјҸгӮүгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҖҢжӯҜдёҰгҒҢжӮӘгҒҸгҒҰгҒ•гҒҶгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгҒӘгҒ„гҒ®гҒ«гҖҒгҒқгӮҢгӮ’еј·гҒІгҒҰйҡ гҒ•гҒҶгҒЁгӮӮгҒӣгҒҡе№іж°—гҒ§еұ…гӮӢгҒЁгҒ“гӮҚгҒҢеӨ§еӨүж°—гҒ«е…ҘгҒӨгҒҹгҖҚпјҲеӨҸзӣ®йҸЎеӯҗгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјүгҖӮйҸЎеӯҗгҒЁгҒ®иҰӢеҗҲгҒ„гҒ®гҒҹгӮҒдёҠдә¬гҒ—гҒҰгҒ„гҒҹжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»29е№ҙ1жңҲ3ж—ҘгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®еұ…е®…пјҲеӯҗиҰҸеәөпјү гҒ§гҒ®еҸҘдјҡгҒ«еҸӮеҠ гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҸҘдјҡгҒ«гҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҖҒжјұзҹігҒ®гҒ»гҒӢгҖҒй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҖҒжІіжқұзў§жў§жЎҗгҖҒжЈ®йҙҺеӨ–гӮүгӮӮеҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
зҶҠжң¬жҷӮд»Ј
гҖҖжҳҺжІ»29е№ҙпјҲ1896пјү4жңҲгҖҒжјұзҹігҒҜзҶҠжң¬гҒ®з¬¬дә”й«ҳзӯүеӯҰж ЎгҒ«и»ўд»»гҒ—гҒҹгҖӮ6жңҲгҒ«гҒҜгҖҒзҶҠжң¬гҒ®еҖҹ家гҒ§йҸЎеӯҗгҒЁгҒ®зөҗе©ҡејҸиЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»29е№ҙ6жңҲ10ж—ҘгҒ®еӯҗиҰҸе®ӣгҒҰгҒ®жӣёз°ЎгҒ®дёӯгҒ§гҖҒгҖҢиЎЈжӣҙгҒёгҒҰдә¬гӮҲгӮҠе«ҒгӮ’иІ°гҒІгҒ‘гӮҠгҖҚгҒЁи© гӮ“гҒ гҖӮжјұзҹігҒ®зөҗе©ҡгҒ«еҪ“гҒҹгҒЈгҒҰеӯҗиҰҸгҒҜгҖҢз§ҰгҖ…гҒҹгӮӢжЎғгҒ®иӢҘи‘үгӮ„еҗӣеЁ¶гӮӢгҖҚгҒЁгҒ®еҸҘгӮ’и© гӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜзөҗе©ҡгҒ—гҒҰй–“гӮӮгҒӘгҒ„гҒ“гӮҚгҖҒйҸЎеӯҗгҒ«гҒӨгҒҺгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘһгҒЈгҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҖҢдҝәгҒҜеӯҰиҖ…гҒ§еӢүеј·гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖҒгҒҠеүҚгҒӘгӮ“гҒӢгҒ«гҒӢгҒҫгҒӨгҒҰгҒҜеұ…гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒҜжүҝзҹҘгҒ—гҒҰгӮҗгҒҰиІ°гҒІгҒҹгҒ„гҖҚпјҲгҖҺжјұзҹігҒ®жҖқгҒІеҮәгҖҸпјүгҖӮ
гҖҖдёҖж–№гҒ®еӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»29е№ҙй ғгҒӢгӮүи„ҠжӨҺгӮ«гғӘгӮЁгӮ№гҒ®гҒҹгӮҒз—…еәҠз”ҹжҙ»гӮ’дҪҷе„ҖгҒӘгҒҸгҒ•гӮҢгҖҒжҳҺжІ»30е№ҙгҒ«гҒҜ2еәҰгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠи…°йғЁгҒ®жүӢиЎ“гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹгҖӮгӮ«гғӘгӮЁгӮ№гҒЁиЁәж–ӯгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜй«ҳжөңиҷҡеӯҗгҒ«е®ӣгҒҰгҒҰгҖҢдҪҷгғ¬зЁӢгҒ®еӨ§жңӣгӮ’жҠұгҒҚгҒҰең°дёӢгҒ«йҖқгҒҸиҖ…гғҸгҒӮгӮүгҒҳгҖҚпјҲжҳҺжІ»29е№ҙ3жңҲ17ж—Ҙд»ҳпјүгҒЁгҒ®жӣёз°ЎгӮ’жӣёгҒҚйҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еӯҗиҰҸгҒҜз—…еәҠгҒ« гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮеүөдҪңжҙ»еӢ•гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҹгҖӮ
гҖҖжҳҺжІ»31е№ҙпјҲ1898пјүгҒ«гҒҜж–°иҒһгҖҢж—Ҙжң¬гҖҚгҒ«гҖҢжӯҢгӮҲгҒҝгҒ«дёҺгҒөгӮӢжӣёгҖҚгӮ’йҖЈијүгҒ—зҹӯжӯҢйқ©ж–°гҒ«д№—гӮҠеҮәгҒ—гҒҹгҖӮжҳҺжІ»32е№ҙгҒ«гҒҜгҖҺдҝіи«§еӨ§иҰҒгҖҸгҖҒгҖҺдҝідәәи•Әжқ‘гҖҸгҒӘгҒ©гӮ’еҲҠиЎҢгҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«жҳҺжІ»33е№ҙ2жңҲгҒ«гҒҜгҖҢеҸҷдәӢж–ҮгҖҚгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҖҒгҖҢеҶҷз”ҹж–ҮгҖҚгӮ’жҸҗе”ұгҒҷгӮӢгҖӮеҶҷз”ҹж–ҮгҒҜиҰӘеҸӢгҒ®з”»е®¶дёӯжқ‘дёҚжҠҳпјҲ第2йғЁеҸӮз…§пјүгӮ’д»ӢгҒ—гҒҰзҹҘгҒЈгҒҹиҘҝжҙӢзөөз”»гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢгҖҢеҶҷз”ҹгҖҚгҒ®зҗҶи«–гҒ«зӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮҠгҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҖҢгҒӮгӮӢжҷҜиүІгҒҫгҒҹгҒҜдәәдәӢгӮ’иҰӢгҒҰйқўзҷҪгҒ—гҒЁжҖқгҒІгҒ—жҷӮгҒ«гҖҒгҒқгӮ’ж–Үз« гҒ«зӣҙгҒ—гҒҰиӘӯиҖ…гӮ’гҒ—гҒҰе·ұгҒЁеҗҢж§ҳгҒ«йқўзҷҪгҒҸж„ҹгҒңгҒ—гӮҒгӮ“гҒЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒиЁҖи‘үгӮ’йЈҫгӮӢгҒ№гҒӢгӮүгҒҡгҖҒиӘҮејөгӮ’еҠ гҒҶгҒ№гҒӢгӮүгҒҡгҖҒгҒҹгҒ гҒӮгӮҠгҒ®гҒҫгҒҫиҰӢгҒҹгӮӢгҒҫгҒҫгҒ«гҒқгҒ®дәӢзү©гӮ’жЁЎеҶҷгҒҷгӮӢгӮ’еҸҜгҒЁгҒҷгҖҚпјҲгҖҢеҸҷдәӢж–ҮгҖҚпјүгҒЁиҝ°гҒ№гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»33е№ҙ2жңҲ12ж—Ҙд»ҳгҒ‘гҒ§гҖҒгҖҢдҫӢгҒ®ж„ҡз—ҙи«ҮгҒ гҒӢгӮүгғ’гғһгғҠжҷӮгҒ«иӘӯгӮ“гҒ§гҒҸгӮҢзҺүгҒёгҖҚгҒЁе§ӢгҒҫгӮӢй•·ж–ҮгҒ®жүӢзҙҷгӮ’жјұзҹігҒёйҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жүӢзҙҷгӮ’гҖҢжұәгҒ—гҒҰдәәгҒ«иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢзҺүгҒөгҒӘгҖҚгҒЁиҝ°гҒ№гӮӢгҖӮ
гҖҖеғ•гғҸгҖҢиҗҪжіӘгҖҚгғҲгӮӨгғ•дәӢгғІжӣёгӮӨгӮҝгғҺгғІеҗӣгғҸжҖӘгғ гғҮгӮўгғӯгғјгӮ¬гӮҪгғ¬гғҸгғҚж–ҜгӮҰгӮӨгғ•гғҜгӮұгғҖгҖӮеҗӣгғҲдәҢдәәгғҮй Ҳз”°гғҳеҫҖгғҶеғ•гғўзңјгғІиҰӢгғҶгғўгғ©гӮҰгӮҝгӮігғҲгӮ¬гӮўгғ«гҖӮе…¶жҷӮй Ҳз”°гғӢгҖҢгғүгғігғҠз—…ж°—гӮ«гҖҚгғҲиҒһгӮӨгӮҝгғ©й Ҳз”°гғҸгҖҢж¶ҷгғҺз©ҙгҒ«еЎһгӮ¬гғ„гӮҝгғҺгғҖгҖҚгғҲгӮӨгғ•гӮҝгҖӮе…¶жҷӮгғҸдҪ•гғҲгғўжҖқгғҸгғҠгӮ«гғ„гӮҝгӮ¬д»ҠжҖқгғ’еҮәгӮ№гғҲгғЁгғӣгғүйқўзҷҪгӮӨз—…ж°—гғҖгҖӮгӮҪгғҺй ғгғҸгӮҪгғ¬гӮ¬гӮҝгғЎгғҮгғўгӮўгғ«гғһгӮӨгӮ¬еғ•гғҸдҪҷгғӘжіЈгӮӨгӮҝгӮігғҲгғҸгғҠгӮӨгҖӮеӢҝи«–е–ҖиЎҖеҫҢгғҺгӮігғҲгғҖгӮ¬гҖҒдёҖеәҰгҖҒе°‘гӮ·жӮІгӮ·гӮӨгӮігғҲгӮ¬гӮўгғ„гӮҝгӮ«гғ©гҖҒгҖҢеғ•гғҸжҳЁж—ҘжіЈгӮӨгӮҝгҖҚгғҲеҗӣгғӢи©ұгӮ№гғҲгҖҒеҗӣгғҸгҖҢй¬јгғҺзӣ®гғӢж¶ҷгғҖгҖҚгғҲгӮӨгғ„гғҶ笑гғ„гӮҝгҖӮгӮҪгғ¬гӮ¬зҘһжҲёз—…йҷўгғӢйҖҷе…Ҙгғ„гғҶеҫҢгғҸжҷӮгҖ…жіЈгӮҜгғӨгӮҰгғӢгғҠгғ„гӮҝгӮ¬гҖҒиҝ‘жқҘгғҺжіЈгӮӯгғӨгӮҰгғҸе®ҹгғӢгғҸгӮІгӮ·гӮҜгғҠгғ„гӮҝгҖӮдҪ•гғўжіЈгӮҜзЁӢгғҺдәӢгӮ¬гӮўгғ„гғҶжіЈгӮҜгғҺгғҮгғҸгғҠгӮӨгҖӮдҪ•гӮ«еҲҶгғ©гғігӮігғҲгғӢдёҖеҜёж„ҹгӮёгӮҝгғҲжҖқгғ•гғҲгӮ№гӮ°ж¶ҷгӮ¬еҮәгғ«гҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүд»Ҡе№ҙгғҺеӨҸгҖҒеҗӣгӮ¬дёҠдә¬гӮ·гғҶгҖҒеғ•гғҺеҶ…гғҳжқҘгғҶйЎ”гғІеҗҲгӮ»гӮҝгғ©гҖҒгғҠгғүгӮқиҖғгғҳгӮҝгғҲгӮӯгғӢжіӘгӮ¬еҮәгғ«гҖӮгӮұгғ¬гғүеғ•гӮ¬жңҖж—©еҶҚгғ“еҗӣгғӢйҖўгғҸгғ¬гғҢгғҠгғүгӮқжҖқгғ•гғҶеұ…гғ«гғҺгғҮгғҸгғҠгӮӨгҖӮдҪөгӮ·гғҠгӮ¬гғ©еҗӣеҝғй…ҚгғҠгғүгӮ№гғ«гғӢгғҸеҸҠгғҗгғігғЁгҖӮеҗӣгғҲе®ҹйҡӣйЎ”гғІеҗҲгғҜгӮ»гӮҝгӮ«гғ©гғҲгғҶеғ•гғҸз„Ўи«–жіЈгӮҜж°—йҒЈгғ’гғҸгғҠгӮӨгҖӮз©әжғігғҮиҖғгғҳгӮҝжҷӮгғӢеҚҙгҖ…жіЈгӮҜгғҺгғҖгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүеғ•гғҺж„ҡз—ҙгғІиҒһгӮҜгғҖгӮұиҒһгғҶеҫҢгғҮе–„гӮӨеҠ жёӣгғӢ笑гғ„гғҶгӮҜгғ¬гғ«гғҺгғҸеҗӣгғҮгӮўгғ©гӮҰгғҲжҖқгғ„гғҶеҗӣгғӢеҗ‘гғ„гғҶгӮӨгғ•гғҺгғҖгӮ«гғ©иІ§д№Ҹ鬮引гӮӨгӮҝгғҲжҖқгғ„гғҶ笑гғ„гғҶгӮҜгғ¬зҺүгғҳгҖӮеғ•гғҖгғ„гғҶжіӘгӮ¬гғҠгӮҜгғҠгғ„гғҶиҖғгғҳгғ«гғҲе®ҹгғӢгғІгӮ«гӮ·гӮӨгғЁгҖӮвҖҰвҖҰвҖҰвҖҰдҪөгӮ·еҗӣгҖҒжӯӨж„ҡз—ҙгғІзңҹйқўзӣ®гғӢгӮҰгӮұгғҶиҝ”дәӢгғҠгғүгӮҜгғ¬гғҶгғҸеӣ°гғ«гғЁгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјүе®ҹйҡӣеҗӣгғҲеҗ‘еҗҲгғ•гӮҝгғҲгӮӯеҗӣгӮ¬гӮ№гғҲгғјгғҙгӮігӮ·гғ©гӮЁгғҶгғӨгғӯгӮ«гғҲгӮӨгғ•гӮҝгғҲгғҶеғ•гғҸгҖҢгӮҰгғігҖҚгғҲгӮӨгғ„гғҶгғ«дҪҚгғҺгғўгғҺгғҮжіЈгӮӯгғўгӮ»гғҢгҖӮгӮұгғ¬гғүжүӢзҙҷгғҮгӮҪгғјгӮӨгғ•гӮігғҲгғІгӮӨгғҸгғ¬гғ«гғҲе°‘гӮ·ж¶ҷгӮ°гғ гғҚгҖӮгӮҪгғ¬гғўжүӢзҙҷгғІиҰӢгғҶгӮ№гӮ°ж¶ҷгғўдҪ•гғўеҮәгғӨгӮҰгғҲгғўгӮ»гғҢгҖӮгӮҝгғҖеӨңгғ’гғҲгғӘеҜҗгғҶгғ°гғ«гғҲгӮӯгғӢгғ•гғҲгӮҪгғ¬гғІиҖғгғҳеҮәгӮ№гғҲжіЈгӮҜгӮігғҲгӮ¬гӮўгғ«гҖӮиҮӘеҲҶгғҺдҪ“гӮ¬ејұгғ„гғҶгғ°гғ«гғҲгӮӯгғӢжіЈгӮҜгғҺгғҖгӮ«гғ©иҖҒдәәгӮ¬еҚ—з„ЎгӮўгғҹгғҖпјҸпјјгғҲгӮӨгғ„гғҶзӢ¬гғӘжіЈгӮӨгғҶгӮӨгғ«гғӨгӮҰгғҠгғўгғҺгғҖгӮ«гғ©гҖҒиҝ”дәӢгғҠгғүгӮӘгӮігӮ·гғҶгӮҜгғ¬зҺүгғ•гғҠгҖӮеҗӣгӮ¬гӮігғ¬гғІиҰӢгғҶгҖҢгғ•гғігҖҚгғҲгӮӨгғ„гғҶгӮҜгғ¬гғ¬гғҗгӮҪгғ¬гғҮеҚҒеҲҶгғҖгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖж–°гӮүгҒ—гҒ„ж„ҡз—ҙгҒҢеҮәжқҘгҒҹгӮүгҒҫгҒҹгҒ“гҒјгҒҷгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ гҒ‘гҒ„гҒөгҒҰйқһеёёгҒ«гҒ•гҒӨгҒұгӮҠгҒ—гҒҹгҒӢгӮүгҖҒеҗӣгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰжӣёйқўдёҠгҒ«ж„ҡз—ҙгӮ’гҒ“гҒјгҒҷгҒ®гғҸгӮӮгҒҶгҒ“гӮҢйҷҗгӮҠгҒЁгҒ—гҒҹгҒ„гҒЁжҖқгҒөгҒҰгӮҗгӮӢгҖӮйҮ‘жҹ‘гҒ®еҫЎзӨјгӮ’гҒ„гҒҜгҒҶгҒЁжҖқгҒөгҒҰгҒ“гӮ“гҒӘдәӢгҒ«гҒӘгҒӨгҒҹгҖӮжұәгҒ—гҒҰдәәгҒ«иҰӢгҒӣгҒҰгҒҸгӮҢзҺүгҒөгҒӘгҖӮгӮӮгҒ—д»–дәәгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгҒҰгҒҜеӣ°гӮӢгҒЁжҖқгҒөгҒҰжӣёз•ҷгҒ«гҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҖӮ
гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒ3жңҲ3ж—ҘгҒ«гҒҜжјұзҹігҒ®й•·еҘігғ»зӯҶеӯҗгҒ®еҲқзҜҖеҸҘгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«йӣӣдәәеҪўгӮ’йҖҒгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒҜгҖҒгҖҢгҒ„гҒҡгӮҢгҒӢгҒЁгҒ„гҒҲгҒ°гҒҝгҒҷгҒ°гӮүгҒ—гҒ„гҒӮгӮҠгҒөгӮҢгҒҹдёүдәәе®ҳеҘігҖҚгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҢгҒ“гҒ®йӣӣгҒ®е°ҸгҒ•гҒҸгҒҜгҒҲгҒӘгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒгҒӢгҒҲгҒЈгҒҰеұ…еЈ«гҒ®з”ҹжҙ»гҒҢеҒІгҒ°гӮҢгҒҰгҖҒгҒҫгҒҹгҒӘгҒҸгӮҶгҒӢгҒ—гҒҸгӮӮжңүйӣЈгҒ„гҖҚпјҲжқҫеІЎиӯІгҖҢеӯҗиҰҸгҒ®йӣӣгҖҚпјүгҖӮ
гҖҖгҒ•гӮүгҒ«6жңҲдёӯж—¬гҒ«гҒҜжјұзҹігҒ«иҮӘзӯҶгҒ®гҖҢгҒӮгҒҘгҒҫиҸҠгҖҚгҒ®зөөгӮ’йҖҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒжҳҺжІ»32е№ҙпјҲ1889пјүз§Ӣй ғгҒӢгӮүгҖҒдёӯжқ‘дёҚжҠҳгҒӢгӮүиҙҲгӮүгӮҢгҒҹзөөгҒ®е…·гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰеҶҷз”ҹз”»гӮ’е§ӢгӮҒгҒҹгҖӮжҷ©е№ҙгҒ®еӯҗиҰҸгҒҜзөөгӮ’жӣёгҒҸгҒ“гҒЁгҒ«еӨ§гҒҚгҒӘж…°гӮҒгҒЁе–ңгҒігӮ’иҰӢеҮәгҒ—гҒҹгҒ®гҒ гҒЈгҒҹгҖӮ
гҖҖгҖҢгҒӮгҒҘгҒҫиҸҠгҖҚгҒ«гҒҜгҖҒгҖҢгӮігғ¬гғҸиҗҺгғҹгӮ«гӮұгӮҝеҮҰгғҲжҖқгғ’гӮҝгғһгғҳпјҸз”»гӮ¬гғһгғ…гӮӨгғҺгғҸз—…дәәгғҖгӮ«гғ©гғҲжҖқпјҸгғ’гӮҝгғһгғҳеҳҳгғҖгғҲжҖқгғҸгғҫиӮұгғ„гӮӨгғҶгӮ«гӮӨпјҸгғҶиҰӢзҺүгғҳгҖҚгҒЁгҒ®еӯҗиҰҸгҒ®ж·»гҒҲжӣёгҒҚгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮжјұзҹігҒҜеӯҗиҰҸгҒ®гҒ“гҒ®зөөгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӘһгӮӢгҖӮгҖҢдёҖијӘиҠұ瓶гҒ«жҢҝгҒ—гҒҹжқұиҸҠгҒ§гҖҒеӣіжҹ„гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҘөгӮҒгҒҰеҚҳз°ЎгҒӘгҖҚгҒ“гҒ®зөөгӮ’жҸҸгҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒеӯҗиҰҸгҒҜгҖҢйқһеёёгҒӘеҠӘеҠӣгӮ’жғңгҒ—гҒҫгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹж§ҳгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢгҖҚгҖӮжјұзҹігҒҜгҖҒгҒ“гҒ®зөөгҒ«гҒҜгҖҒеӯҗиҰҸгҒ®гҖҢйҡ гҒ—еҲҮгӮҢгҒӘгҒ„жӢҷгҒҢжәўгӮҢгҒҰгӮҗгӮӢгҖҚпјҲгҖҢеӯҗиҰҸгҒ®з”»гҖҚпјүгҖӮ
гҖҖжқұиҸҠгҒ«гӮҲгҒӨгҒҰд»ЈиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹеӯҗиҰҸгҒ®з”»гҒҜгҖҒжӢҷгҒҸгҒҰдё”зңҹйқўзӣ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжүҚгӮ’е‘өгҒ—гҒҰзӣҙгҒЎгҒ«з« гӮ’гҒӘгҒҷеҪјгҒ®ж–ҮзӯҶгҒҢгҖҒзөөгҒ®е…·зҡҝгҒ«жөёгӮӢгҒЁеҗҢжҷӮгҒ«гҖҒеҝҪгҒЎе …гҒҸгҒӘгҒӨгҒҰгҖҒз©Ӯе…ҲгҒ®йҒӢиЎҢ гҒҢгҒӯгҒӨгҒЁгӮҠз«ҰгӮ“гҒ§д»•иҲһгҒӨгҒҹгҒ®гҒӢгҒЁжҖқгҒөгҒЁгҖҒдҪҷгҒҜеҫ®з¬‘гӮ’зҰҒгҒҳгҒҲгҒӘгҒ„гҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү гҖҖеӯҗиҰҸгҒҜдәәй–“гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҸҲж–ҮеӯҰиҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒжңҖгӮӮгҖҢжӢҷгҖҚгҒ®ж¬ д№ҸгҒ—гҒҹз”·гҒ§гҒӮгҒӨгҒҹгҖӮж°ёе№ҙеҪјгҒЁдәӨйҡӣгӮ’гҒ—гҒҹдҪ•гҒ®жңҲгҒ«гӮӮгҖҒдҪ•гҒ®ж—ҘгҒ«гӮӮгҖҒдҪҷгҒҜжңӘгҒ жӣҫгҒҰеҪјгҒ®жӢҷгӮ’笑гҒІеҫ—гӮӢгҒ®ж©ҹдјҡгӮ’жҚүгҒёеҫ—гҒҹи©ҰгҒҢгҒӘгҒ„гҖӮеҸҲеҪјгҒ®жӢҷгҒ«жғҡгӮҢиҫјгӮ“гҒ зһ¬й–“гҒ®е ҙеҗҲгҒ•гҒёжңүгҒҹгҒӘгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮеҪјгҒ®жӯҝеҫҢж®ҶгҒ©еҚҒе№ҙгҒ«гҒӘгӮүгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢд»Ҡж—ҘгҖҒеҪјгҒ®гӮҸгҒ–гӮҸгҒ–дҪҷгҒ®зӮәгҒ«жҸҸгҒ„гҒҹдёҖијӘгҒ®жқұиҸҠгҒ®дёӯгҒ«гҖҒзўәгҒ«жӯӨдёҖжӢҷеӯ—гӮ’иӘҚгӮҒгӮӢдәӢгҒ®еҮәжқҘгҒҹгҒ®гҒҜгҖҒе…¶зөҗжһңгҒҢдҪҷгӮ’гҒ—гҒҰеӨұ笑гҒӣгҒ—гӮҖгӮӢгҒЁгҖҒж„ҹжңҚгҒӣгҒ—гӮҖгӮӢгҒЁгҒ«и«–гҒӘгҒҸгҖҒдҪҷгҒ«еҸ–гҒӨгҒҰгҒҜеӨҡеӨ§гҒ®иҲҲе‘ігҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгӮһз”»гҒҢеҰӮдҪ•гҒ«гӮӮж·ӢгҒ—гҒ„гҖӮеҮәжқҘеҫ—гӮӢгҒӘгӮүгҒ°гҖҒеӯҗиҰҸгҒ«жӯӨжӢҷгҒӘжүҖгӮ’гӮӮгҒҶе°‘гҒ—йӣ„еӨ§гҒ«зҷәжҸ®гҒ•гҒӣгҒҰгҖҒж·ӢгҒ—гҒ•гҒ®е„ҹгҒІгҒЁгҒ—гҒҹгҒӢгҒӨгҒҹгҖӮ
пјҲгҖҢеӯҗиҰҸгҒ®з”»гҖҚпјү
гҖҖж–ҮйғЁзңҒгҒӢгӮү2е№ҙй–“гҒ®иӢұеӣҪз•ҷеӯҰгӮ’е‘ҪгҒҳгӮүгӮҢгҒҹжјұзҹігҒҜгҖҒжҳҺжІ»33е№ҙпјҲ1900пјү8жңҲ26ж—ҘгҖҒеҜәз”°еҜ…еҪҰгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еӯҗиҰҸгӮ’иҰӢиҲһгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢжјұзҹігҒЁеӯҗиҰҸгҒ®жңҖеҫҢгҒ®йқўдјҡгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеӯҗиҰҸгҒҜгҖҒгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸ第3巻第12еҸ·пјҲжҳҺжІ»33е№ҙ9жңҲпјүгҒ«гҖҒж¬ЎгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иЁҳгҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖжјұзҹіж°ҸгҒҜдәҢе№ҙй–“иӢұеӣҪз•ҷеӯҰгӮ’е‘ҪгҒңгӮүгӮҢжӯӨеӨҸзҶҠжң¬гӮҲгӮҠдёҠдә¬гҖҒе°Ҹз”ҹгӮӮд№…гҖ…гҒ«гҒҰйқўи«ҮиҮҙеҖҷгҖӮеҺ»гӮӢд№қжңҲе…«ж—ҘзӢ¬йҖёиҲ№гҒ«д№—иҫјжЁӘжөңеҮәзҷә欧е·һгҒ«еҗ‘гҒҜгӮҢеҖҷгҖӮе°Ҹз”ҹгҒҜдёҖдҪңгҖ…е№ҙеӨ§жӮЈгҒ«йҖўгҒІгҒ—еҫҢгҒҜжҙӢиЎҢгҒ®дәәгӮ’йҖҒгӮӢжҜҺгҒ«жңҖж—©еҶҚдјҡгҒҜеҮәжқҘгҒҫгҒҳгҒҸгҒЁгҒ„гҒӨгӮӮеҝғзҙ°гҒҸжҖқгҒІеҖҷгҒІгҒ—гҒ«е…¶дәә次第пјҸпјјгҒ«её°гӮҠжқҘгӮҠеҶҚдјҡгҒ®е–ңгӮ’еҫ—гҒҹгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮе°‘гҒӢгӮүгҒҡеҖҷгҖӮдҪөгҒ—жјұзҹіж°ҸжҙӢиЎҢгҒЁиҒһгҒҸгӮ„еҗҰгӮ„гҖҒиҝҡгӮӮд»ҠеәҰгҒҜгҒЁзӢ¬гӮҠжӮІгҒ—гҒҸзӣёжҲҗз”іеҖҷгҖӮ
гҖҖжјұзҹігҒҜзҶҠжң¬гҒ«гҒҜзҙ„5е№ҙй–“гҖҒж»һеңЁгҒ—гҒҹгҖӮ第дә”й«ҳзӯүеӯҰж ЎгҒ®ж•ҷгҒҲеӯҗгҒ«гҒҜеҜәз”°еҜ…еҪҰгӮүгҒҢгҒҠгӮҠгҖҒгҒҫгҒҹзӢ©йҮҺдәЁеҗүгӮ’дә”й«ҳгҒ«жӢӣиҒҳгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«е°ҪеҠӣгҒ—гҒҹгҒ®гҒҢжјұзҹігҒ гҒЁиЁҖгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжјұзҹігҒҜеәҰгҖ…гҖҒзӢ©йҮҺгӮүгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«е°ҸеӨ©жё©жіүгҒ«еҮәгҒӢгҒ‘гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҶҠжң¬гҒ§гҒ®з”ҹжҙ»гҒҢгҒ®гҒЎгҒ«гҖҺиҚүжһ•гҖҸгӮ„гҖҺдәҢзҷҫеҚҒж—ҘгҖҸгҒЁгҒ—гҒҰзөҗе®ҹгҒ—гҒҹгҖӮ