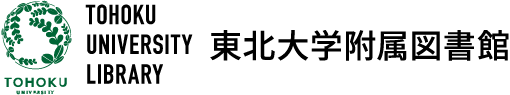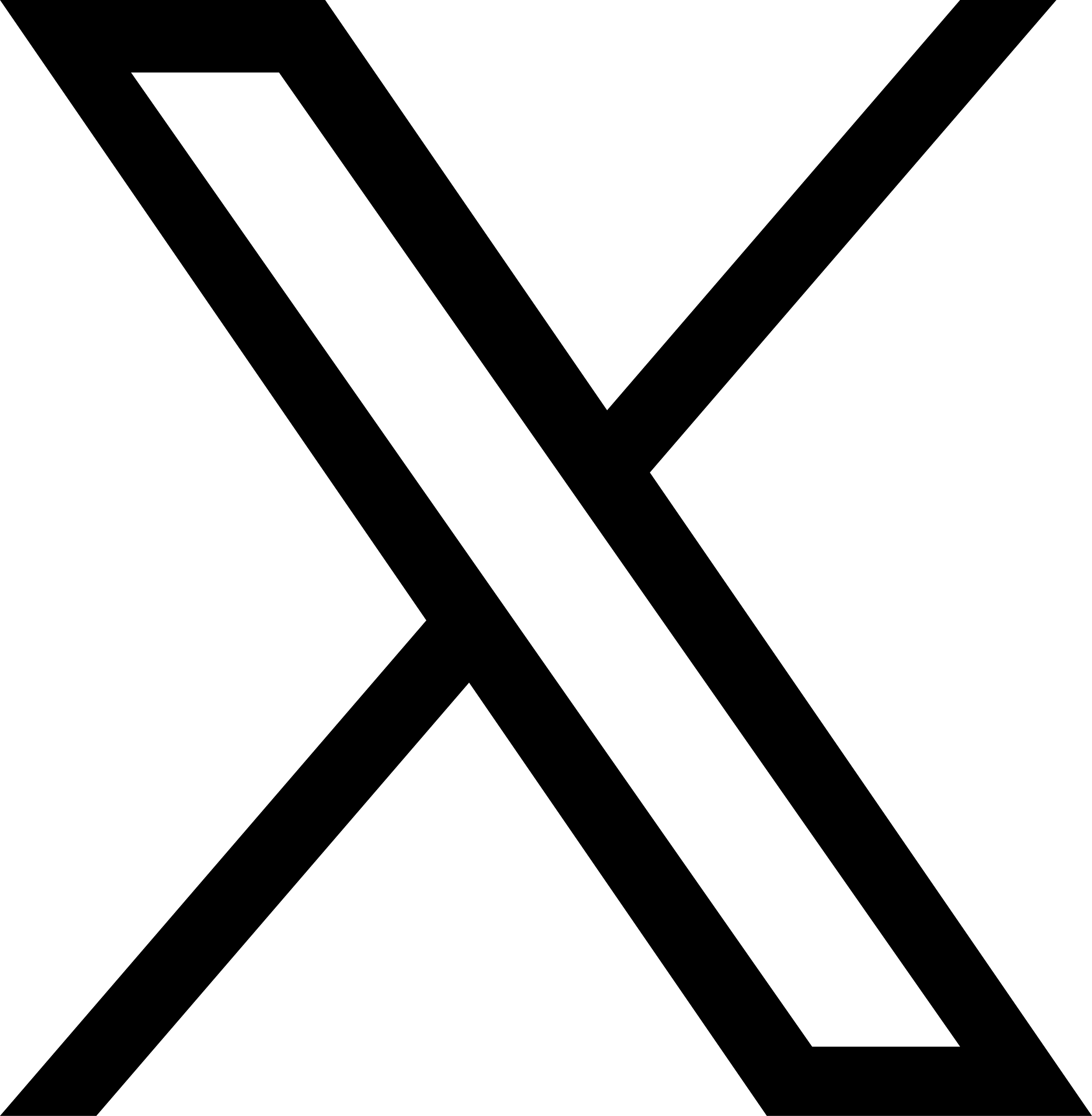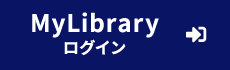APC支援事業利用者インタビュー
APC支援事業について
本学の研究成果発信力強化及び若手研究者支援のため、国際的な学術ジャーナルに投稿される論文のオープンアクセス化にかかる経費の支援を実施します。 図書館では論文のオープンアクセス化を支援しています。
本インタビューは、論文をオープンアクセス(OA)にされた先生方にAPC支援事業を利用した経緯や利用しての感想をお伺いしたものです。
APC支援事業利用者インタビュー
李弘毅(リ コウキ)先生(金属材料研究所 市坪研究室 特任助教)

日 時 :2025年3月17日(月)15:00~15:50
場 所 :金属材料研究所2号館
話 者 :李弘毅(リ コウキ)先生(金属材料研究所 市坪研究室 特任助教)
2023年はAPC支援事業を2回利用
インタビュアー:附属図書館情報管理課長 木下直
〃 情報管理課オープンアクセス推進係長 藤本菜穂子(当時)
図:本日はお時間をいただき、ありがとうございます。始めに本学のAPC支援事業を知ったきっかけを教えていただけますでしょうか。
李:少し前のことなので記憶が曖昧なのですが、確か部局事務からのメールでした。ちょうどそのタイミングでアクセプトされた論文があり、手続きしていたところだったので、目に留まりました。
あとは今日こちらに来る前にご覧になったかもしれませんが、1階のエレベーター横の掲示板にもポスターがあって。
図:実は2023年にAPC支援事業を開始した際の最初の申し込みが、李先生だったんです。
李:ははは。そうでしたか。
図:李先生は、以前にも論文をオープンアクセス出版(以下「OA」)したことがありますか?
李:はい。論文をOAにしようということは周りの先生からも聞いていて、自分もできるだけOAにした方がよいだろうと思っていました。ただ、最近のジャーナルのAPC(Article Processing Charge)って高額ですよね。だから、東北大学がその経費を支援してくれるのは、すごく助かります。
図: APCは毎年値上がりしていることもあり、他の先生からも非常にありがたいというご意見を多くいただいています。
李:Nature Communicationsのような、APCを払わないと出版できない完全OAジャーナルもありますし、APCを支払えばオープンになるハイブリッドジャーナルでも、なるべく誰でも見られるようにできたらいいなと思っています。
最初に支援を受けてOAにしたものは、企業との共同研究の論文で、企業側にとってもOAであれば簡単に内容が確認できるので、良いことだと思いました。先方は材料開発をしていて、開発した材料をデバイスを作る会社に使ってもらう際に、学術論文も一緒に見せるとより説得力があるとも聞きました。大手企業であれば、何らかの方法で学術論文を入手できるのでしょうが、一般的な企業は、そもそもまだ論文を読む習慣がないという所も多く、入手も難しいんです。OAの論文なら宣伝もしやすいので、産学連携の観点からも良いと思います。
図:従来のクローズの場合でも、ファイルをメールで送るといった方法があると思いますが、やはりOAの方がよいのでしょうか?
李:ええ、わざわざファイルを送るのはちょっとと思う場合でも、OAなら気軽にできます。
図:なるほど。見てもらいやすくなったことで、閲覧数は増えたでしょうか?
李:どれくらい増えたか、あまりモニタリングはしていません。出版社によって、閲覧数が分かる場合と分からない場合もありますし。
数年前に上司の予算でOAにしたNature Communicationsの論文は、かなり閲覧数が多かったのですが、正直内容によると思いますね。論題に専門用語が並ぶような専門性の高い論文は、OAにしてもあまり閲覧されないような気がします。でも、ダウンロード数はやはりOAにした方が多いと思います。
図:では、先生が論文をOAにしたのは、閲覧数等の増というより、成果をシェアしやすくするためということなんですね。
李:そうですね。論文を書く研究者は、ジャーナルが読める機関に所属していることが多いので、OAにせずとも読めますし、引用もしてくれます。なので、閲覧・引用数にどの程度影響があるのかは、正直よく分からないです。
図:確かに「自身の関係者はジャーナルを読める環境にあるから、わざわざ高額なAPCを払ってまでOAにする必要はない」と言う先生も若干います。
李:そもそものOAのモットーは、知識をより平等に、公平に、誰でも見られるようにするということだと思いますが、そういう点ではOAは絶対に意味がありますね。繰り返しになってしまいますが、産学連携に関しても、効果があると思います。人数の少ない、特殊な素材を作るメーカーとか、論文の入手が難しい方にとっては、論文が公開され、どこの大学でどんな研究をしているか知ることができれば、より相談しやすくなるのではないかと思います。
図:現在実施中のAPC支援事業の内容は十分でしょうか?
李:僕の材料工学関係であれば、ほとんどのジャーナルがカバーされていますね。
図:それは良かったです。
李:ただ、最近の傾向というか、僕は中国出身なのですが、いま中国の学術機関は多数の論文を書いていて、以前ならWiley,ACS,RSCといったメジャーなジャーナルに投稿されていたであろう論文が、最近は中国の大学や学会のジャーナルに投稿されているんです。なので、現在支援対象となっているジャーナルのインパクトファクター(IF)が少しずつ下がっていて、カオスな状況になってきている印象があります。
そういった状況に、日本の研究機関にいる研究者としてどう対応するか、もうすでにハイインパクトジャーナル投稿支援プログラムの対象誌として中国のジャーナルも入っているのかもしれませんが、少し考えているところです。
図:図書館としては、なるべく先生方の希望に沿った支援ができればと思っています。現時点は足りているようですが、将来的には対象ジャーナルの基準について見直す必要も生じるかもしれませんね。
APC支援事業は、他の先生にもお薦めできそうでしょうか?
李:僕は他の研究室の先生と共同研究をすることがあるのですが、新しい分野の研究を始めた時は、いきなり良い論文は書けないんです。そうなると、ハイインパクトジャーナル投稿支援プログラムの対象ジャーナルに投稿するのは難しくて、なかなか薦めづらいところはあります。ですが、Elsevier/Springer/Wiley/ACS支援プログラムなら全体が対象なので、そちらを選ぶかもしれません。
図:Elsevier/Springer/Wiley/ACS支援プログラムで相当のジャーナルをカバーしているとは思います。すべてのジャーナルが支援対象であればなおよいのですが、大学が目指す方向性をふまえ、一定の基準は必要だと考えています。でも、現場の声としてとても参考になります。実際、論文の投稿先は、どのように決めているのですか?
李:僕の研究室は、教授が内容を見て判断します。まずはNature系を候補にし、レピュテーションを保つために、IFの低いジャーナルには投稿せず、由緒あるジャーナルに投稿するという方針で、APC支援事業のおかげでフルOA誌にも投稿しやすくなりました。
図:支援事業があるので、フルOA誌に投稿できたという声もよくいただきます。
李:ただ、最近のフルゴールド誌の位置づけがよく分からないというか、ACS(アメリカ化学会)はJACS (Journal of the American Chemical Society:ハイブリッド誌)のほかJACS Au(フルOA誌)も出版していて、なぜ並行しているのかなと思うことはあります。
図:たしかに最近はいろいろなジャーナルが創刊していますね。
2025年度から、公的資金の研究成果(論文・データ)の公開が義務付けられます。李先生はSupporting Informationという形で、論文と共にデータを公開されているようですが、義務化による影響は何かありそうですか?
李:義務化の件はよく理解していないのですが、おそらくあまりないと思っています。データの公開って、結局何を公開すればいいんでしょうね?
図:分野によってだいぶ異なりそうです。
李:いまSIに入れているのも、生データから加工したものになります。詳細なものを公開した場合、最近であればAIといったものにどう利用・分析されるのかという懸念もあります。
図:ただデータを公開すればよいというものでもないのですね。
李:図であれば、まだAIが読み取れるレベルではないので問題ないかもしれませんが、テキストデータの場合は規則性が勝手に分かってしまう可能性もあり、そういったところをコントロールできるか心配です。
図:義務化の件は、研究室の方は全員ご存じなのでしょうか?何かしなくては、といった声はあったりしますか?
李:いえ、先生方は義務化のことを聞いていると思いますが、話題になったことはないです。
図:そうですか。学内の研究者の方々に、いろいろな方法でAPC支援事業や公的資金による研究成果の公開義務化について、情報をお伝えできたらと思っています。
本日は貴重なお話どうもありがとうございました。
大森仁 先生(情報科学研究科 教授)
日 時 :2025年3月19日(水)10:00~11:30
場 所 :情報科学研究科 大森研究室
話 者 :大森仁 先生(情報科学研究科 教授)
2023年はAPC支援事業を3回利用
インタビュアー:附属図書館情報管理課長 木下直
〃 情報管理課オープンアクセス推進係長 藤本菜穂子(当時)
図:本日はお時間をいただき、ありがとうございます。始めに本学のAPC支援事業を知ったきっかけを教えてください。
大:おそらく配布されたチラシがきっかけです。あと1階のエレベーター近くにもポスターが貼ってありますよね。情報科学の総務係からメールも来ていたと思います。
図:ポスターがとても目立つ位置に貼ってあり、驚きました。さまざまな方法で先生方にはお知らせが届いていたんですね。
大:はい。関心ない方もいるので、受け止め方には差があったかもしれませんが、チラシはよかったと思います。
図:先生はチラシをご覧になって、初めて論文をオープンアクセス出版(以下「OA」)してみようと思ったのでしょうか?
大:いえ。実は僕は前職ドイツにいまして、Springer社がドイツの会社なので、ドイツの大学協会が出版社と交渉して、大学の研究者の論文は自動的に全部OAになる仕組みがあったんです。それで自己負担なしでOAにしていました。
図:そうでしたか。海外で利用していた方のお話は初めてうかがうのですが、自動的にとはいえ、何か図書館とやり取りはあるのですか?
大:はい。Springer社のシステムで申し込みをすると、おそらく図書館に通知が行き、図書館から連絡をもらって、お願いしますと返信をするという東北大学と全く同じ流れで手続きしていました。分野によっては公開に慎重になるような場合もあるので、おそらくそういったプロセスを経ているのだと思います。
図:では、東北大での手続きについては、、。
大:全然問題なかったです。むしろ私は考えがあって研究では東北大のメールアドレスではなくGメールを使用しているので、支援対象になるか心配していたのですが、スムーズに手続きが進み、助かりました。
図:論文をOAにしたことによって、どんな効果があったか詳しくお聞かせいただきたいのですが。
大:私はイントロダクションを丁寧に書くことが好きで、2016年頃にとある特別号にイントロダクションを書きました。査読論文ではないので、その時は自動的にOAになったのですが、結果そのジャーナルで一番閲覧された論文になりました。それはやはりクリックすれば見られるという点が非常に大きかったのだと思います。日本はアメリカやヨーロッパとよく比較しますが、発展途上国と呼ばれるような経済力が強くない国の方が実は研究者数は圧倒的に多いので、クリックしてすぐ読めるようになれば、読者層は爆発的に増えるわけです。
図:なるほど。
大:経済力のない国にも優秀な若手の研究者は大勢いるので、そういう次世代の人たちに読んでもらうという意味でも、論文はOAにした方がよいだろうと思っています。
図:具体的に、どの程度増えたか分かるものでしょうか?
大:内容にもよると思うので正確には分かりませんが、でもOAにした論文の方がやはり見られる可能性が高いと思いますし、引用されていると感じますね。
図:以前実施した利用者アンケートでも、OAにした効果の1つとして「発展途上国の方にも見てもらえる」と答えた先生が他にいました。
大:欧米諸国の外にも大きなコミュニティ・厚い読者層があるので、私は重要だと思っています。
図:現在の支援事業はWileyやElsevierなどのジャーナルも対象に実施していますが、全体に対する印象はいかがですか?人文系の研究者としてのご意見もお聞かせいただけたらありがたいです。
大:人文系全般となると一般化しすぎて難しいのですが、哲学の分野ですと、OxfordやCambridgeの大学出版会のジャーナルの評価が高く、それらは現在対象になっていませんよね?今年度(2024年度)中にOxfordに論文を1本書いたのですが、APCが50万円以上するんです。格式あるジャーナルではあるのですが、3-4ページの論文に対してAPCを支払うかというと、、。
図:APC支援事業にはElsevier, Springer, Wiley用のプログラム(※正確にはACSも含む)と、Nature等のジャーナルを支援するプログラム(「ハイインパクトジャーナル投稿支援プログラム」)があり、OxfordやCambridgeのジャーナルの一部は後者で支援できるはずなのですが、対象になっていませんでしたか?
大:僕が見落としていたのかもしれません。
図:どのジャーナルが支援対象なのか、図書館の特設サイトで一覧リストを公開していて、調べやすくしているつもりなのですが、プログラムが2種類あったりして複雑なので、分かりにくいという声も時折あります。
大:出版社のシステム上にOAオプションが表示されれば、すぐ対象と分かるんですけども、今回表示されていなかったです。
図:はい。ハイインパクトジャーナル投稿支援プログラムは学内独自の支援制度なので、出版社のシステムには表示されません。
大:今回は支援を受けられないと思い、自分の研究費を使うか、研究科でも独自の支援制度があるので、それを利用するか迷ったのですが、1ページあたり10万円以上と考えるとどうかなと思い、結局やめました。研究成果をなるべくオープンにしたいとは思いますが、人文科学の予算規模は基本的に小さいので、APCを自己負担してまでOAにするのは非常に難しいです。ですので、大学が支援してくれるのはとてもありがたいですが、評価の高いジャーナルが対象になっていないとしたら、もったいないですね。プレプリントサーバーといったものの整備も重要なんでしょうね。
図:OAにするかしないかは、先生にご判断いただくことではありますが、希望に沿うよう考えていきたいと思っています。他の先生にもお薦めできそうでしょうか。
大:分野によると思います。英語などで論文を書かない方ももちろんいるので。でも、若手の方で、英語で論文を書くような方であれば、当然支援を受けた方がよいと思います。
4月から研究員を1名受け入れるのですが、Springerに投稿した論文はOAになると伝えたら喜んでいましたよ。僕がドイツから東北大に来た時期にちょうど支援事業が始まり、ドイツで当たり前だった環境が引き継げたのはとても嬉しかったですね。海外の若い方に声をかける時は、東北大の研究環境が良くなっていると説明する中でOA支援があることも話しています。
図:研究成果が多くの方の目に触れることは、キャリアにも影響してくることだと思いますので、若い研究者にはたくさん利用してもらいたいと思っています。
大:オープンアクセスに関しては、ローカルなグループや研究者がボランタリーに運営しながら、しっかりと査読をして有用なコメントを返してくれ、無料でOAにしている優良ジャーナルも結構あります。ですので、高額なAPCを必要とするジャーナルの仕組みには疑問を感じる時があります。僕は40歳を超え、キャリアとしては安定してきているので、評価の対象にならないようなジャーナルを大切にすることも、個人的には重要なのではないかと思っています。APCが不要となる理想の形も忘れずにいたいですね。
図:おっしゃる通りだと思います。望ましいオープンアクセスの在り方を考えていると、研究者の評価の問題も密接に関係していると感じますし、大手出版社に依存しない方策も考える必要があります。
大:東北大学の機関リポジトリ(「TOUR」)も、これまで使ったことがなかったのですが、DOIが付けられるということで安定性が高まるので、ぜひ利用してみたいです。
図:ありがとうございます。
大:アップロードとか最低限の操作で済むとありがたいのですが。
図:そうですね。登録サポートシステムについては現在開発中です(インタビュー当時)。2025年度から始まる公的資金による研究成果の公開義務化と合わせ広報できればと思っています。 本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
お問い合わせ
APC支援による事業に関するお問い合わせ先
東北大学附属図書館 情報管理課 オープンアクセス推進係
〒980-8576 仙台市青葉区川内27-1
E-mail: lib.apc〔a〕grp.tohoku.ac.jp ※〔a〕はアットマークに読み替えてください。