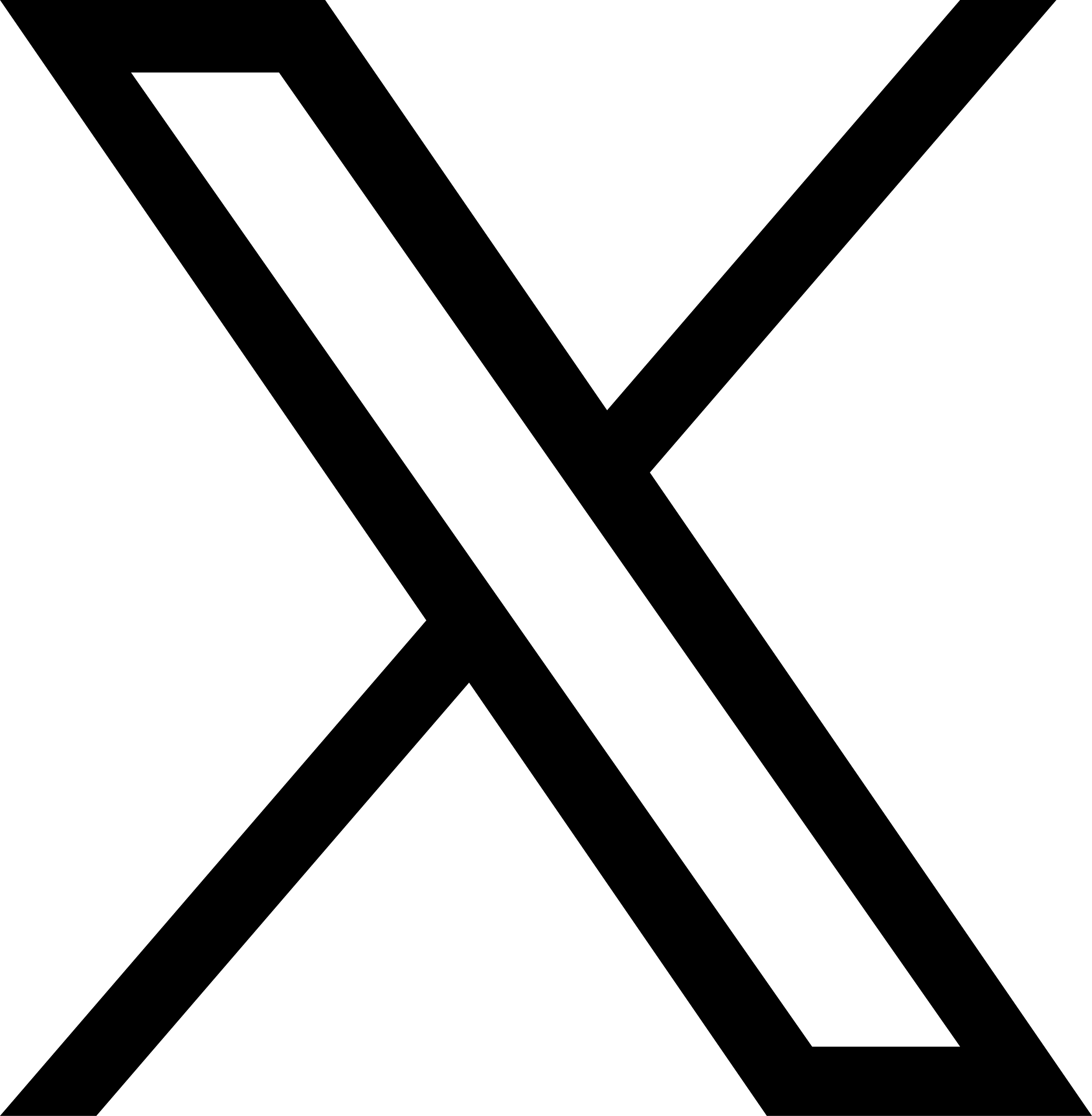жқұеҢ—еӨ§еӯҰйҷ„еұһеӣіжӣёйӨЁгҖҖеӨҸзӣ®жјұзҹігғ©гӮӨгғ–гғ©гғӘ
дё»иҰҒдҪңе“Ғе…Ёи§ЈиӘ¬
еҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢ
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгҖҖжҳҺжІ»38е№ҙ1жңҲпҪһжҳҺжІ»39е№ҙ8жңҲгҒҫгҒ§10еӣһгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠж–ӯз¶ҡзҡ„гҒ«йҖЈијү
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүдёҠз·ЁгҖҖжҳҺжІ»38е№ҙ10жңҲгҖҖдёӯз·ЁгҖҖжҳҺжІ»39е№ҙ11жңҲгҖҖдёӢз·ЁгҖҖжҳҺжІ»40е№ҙ5жңҲгҖҖеӨ§еҖүжӣёеә—гғ»жңҚйғЁжӣёеә—
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖзҢ«гӮ’иӘһгӮҠжүӢгҒЁгҒ—гҒҰиӢҰжІҷејҘгғ»иҝ·дәӯгӮүеӨӘе№ігҒ®йҖёж°‘гҒҹгҒЎгҒ«ж»‘зЁҪгҒЁи«·еҲәгӮ’еӯҳеҲҶгҒ«жј”гҒҳгҒ•гҒӣиӘһгӮүгҒӣгҒҹгҒ“гҒ®е°ҸиӘ¬гҒҜгҖҢеқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҖҚгҒЁгҒӮгҒ„йҖҡгҒҡгӮӢзү№еҫҙгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒҜжәўгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘиЁҖиӘһгҒ®ж№§еҮәгҒЁжӯҜеҲҮгӮҢгҒ®гҒ„гҒ„ж–ҮдҪ“гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®иұҠгҒӢгҒӘе°ҸиӘ¬иЁҖиӘһгҒ®ж°ҙи„ҲгӮ’зҷәиҰӢгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§иӢұж–ҮеӯҰиҖ…гғ»жјұзҹігҒҜе°ҸиӘ¬е®¶жјұзҹіпјҲ1867-1916пјүгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖжқұйўЁеҗӣгҖҒиӢҰжІҷејҘеҗӣгҖҒзҡҶеӢқжүӢгҒӘдәӢгӮ’з”іеҖҷгҖӮгҒқгӮҢж•…гҒ«еӨӘе№ігҒ®йҖёж°‘гҒ«еҖҷгҖӮзҸҫе®ҹдё–з•ҢгҒ«гҒӮгҒ®дё»зҫ©гҒ§гҒҜеҰӮдҪ•гҒЁеӯҳеҖҷгҖӮеҫЎеҸҚеҜҫеҫЎе°ӨгҒ«еҖҷгҖӮжјұзҹіе…Ҳз”ҹгӮӮеҸҚеҜҫгҒ«еҖҷгҖӮ
гҖҖеҪјгӮүгҒ®гҒ„гҒөжүҖгҒҜзҡҶзңҹзҗҶгҒ«еҖҷгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒҹгҒ дёҖйқўгҒ®зңҹзҗҶгҒ«еҖҷгҖӮжұәгҒ—гҒҰдҪңиҖ…гҒ®дәәз”ҹиҰігҒ®е…ЁйғЁгҒ«з„Ўд№Ӣж•…пјҲгҒ“гӮҢгҒӘгҒҚгӮҶгҒҲпјүгҒқгҒ®иҫәгҒҜеҫЎдәҶзҹҘиў«дёӢпјҲгҒҸгҒ гҒ•гӮҢгҒҹгҒҸпјүеҖҷгҖӮгҒӮгӮҢгҒҜз·ҸдҪ“гҒҢи«·еҲәгҒ«еҖҷгҖӮзҸҫд»ЈгҒ«гҒӮгӮ“гҒӘи«·еҲәгҒҜе°ӨгӮӮйҒ©еҲҮгҒЁеӯҳгҒҳгҖҺзҢ«гҖҸдёӯгҒ«еҸҺгӮҒеҖҷгҖӮгӮӮгҒ—е°Ҹз”ҹгҒ®еҖӢжҖ§и«–гӮ’и«–ж–ҮгҒЁгҒ—гҒҰгҒӢгҒ‘гҒ°еҸҚеҜҫгҒ®ж–№йқўгҒЁеҸҢж–№гҒ®еғҚгҒҚгҒӢгҒ‘гӮӢжүҖгӮ’иӯ°и«–иҮҙгҒ—гҒҹгҒҸгҒЁеӯҳеҖҷгҖӮ
пјҲжҳҺжІ»39е№ҙ8жңҲ7ж—ҘгҖҖз•”жҹіиҠҘиҲҹгҒӮгҒҰжӣёз°ЎгӮҲгӮҠпјү
гҖҖгҖҺзҢ«гҖҸгҒ§гҒҷгҒӢгҖҒгҒӮгӮҢгҒҜжңҖеҲқгҒҜдҪ•гӮӮгҒӮгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«й•·гҒҸз¶ҡгҒ‘гҒҰжӣёгҒ“гҒҶгҒЁгҒ„гҒҶиҖғгҒҲгӮӮгҒӘгҒ—гҖҒи…№жЎҲгҒӘгҒ©гӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҒӢгӮүз„Ўи«–дёҖеӣһгҒ гҒ‘гҒ§гҒ—гҒҫгҒҶгҒӨгӮӮгӮҠгҖӮгҒҫгҒҹгҒӢгҒҸгҒҫгҒ§дё–й–“гҒ®и©•еҲӨгӮ’еҸ—гҒ‘гӮҲгҒҶгҒЁгҒҜе°‘гҒ—гӮӮжҖқгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮжңҖеҲқиҷҡеӯҗеҗӣгҒӢгӮүгҖҢдҪ•гҒӢжӣёгҒ„гҒҰгҒҸгӮҢгҖҚгҒЁй јгҒҫгӮҢгҒҫгҒ—гҒҰгҖҒгҒӮгӮҢгӮ’дёҖеӣһжӣёгҒ„гҒҰгӮ„гӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮдёҒеәҰгҒқгҒ®й ғж–Үз« дјҡгҒЁгҒ„гҒҶгӮӮгҒ®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҰгҖҒгҖҺзҢ«гҖҸгҒ®еҺҹзЁҝгӮ’гҒқгҒ®дјҡгҒёеҮәгҒ—гҒҫгҒҷгҒЁгҖҒгҒқгӮҢгӮ’гҒқгҒ®еёӯгҒ§еҜ’е·қйј йӘЁеҗӣгҒҢжң—иӘӯгҒ—гҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҒҢгҖҒеӨҡеҲҶжң—иӘӯгҒ®д»•ж–№гҒ§гӮӮж—ЁгҒӢгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒ—гӮҮгҒҶгҖҒз”ҡгҒҸгҒқгҒ®еёӯгҒ§е–қйҮҮгӮ’еҚҡгҒ—гҒҹгҒқгҒҶгҒ§гҒҷгҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖеҰҷгҒӘгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒжӣёгҒ„гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҹеҪ“еә§гҒҜгҖҒ全然иғёдёӯгҒ®ж–Үеӯ—гӮ’еҗҗгҒҚеҮәгҒ—гҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰгҖҒгӮӮгҒҶгҒ“гҒ®ж¬ЎгҒ«гҒҜдҪ•гӮӮжӣёгҒҸгӮҲгҒҶгҒӘгҒ“гҒЁгҒҜгҒӘгҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҒ»гҒ©гҒ§гҒҷгҒҢгҖҒгҒ•гҒҰеҚҒж—ҘзөҢгҒЎе»ҝж—ҘзөҢгҒЈгҒҰиҰӢгӮӢгҒЁж—ҘгҖ…гҒ®еҮәжқҘдәӢгӮ’иҰіеҜҹгҒ—гҒҰгҖҒгҒҫгҒҹж–°гҒҹгҒ«жӣёгҒҚгҒҹгҒ„гӮҲгҒҶгҒӘж„ҹжғігӮӮ湧гҒ„гҒҰжқҘгӮӢгҖӮжқҗж–ҷгӮӮи’җгӮҒгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гӮ“гҒӘйўЁгҒ§гҒҷгҒӢгӮүгҖҺзҢ«гҖҸгҒӘгҒ©гҒҜжӣёгҒ“гҒҶгҒЁжҖқгҒҲгҒ°е№ҫгӮүгҒ§гӮӮй•·гҒҸз¶ҡгҒ‘гӮүгӮҢгҒҫгҒҷгҖӮпјҲгҖҢж–ҮеӯҰи«ҮгҖҚпјү
еқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүгҖҺгғӣгғҲгғҲгӮ®гӮ№гҖҸгҖҖжҳҺжІ»39е№ҙ4жңҲ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүгҖҺй¶үзұ гҖҸжүҖеҸҺгҖҖжҳҺжІ»40е№ҙ1жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖгҖҢеқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҖҚгҒҜж•°гҒӮгӮӢжјұзҹігҒ®дҪңе“ҒдёӯгӮӮгҒЈгҒЁгӮӮеәғгҒҸиҰӘгҒ—гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮзӣҙжғ…еҫ„иЎҢгҖҒз„Ўйү„з ІгҒ§гӮ„гҒҹгӮүе–§еҳ©ж—©гҒ„еқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҒҢиөӨгӮ·гғЈгғ„гғ»зӢёгҒҹгҒЎгҒ®дёҖе…ҡгӮ’гӮҖгҒ“гҒҶгҒ«гҒҫгӮҸгҒ—гҒҰгҒҸгӮҠеұ•гҒ’гӮӢз—ӣеҝ«гҒӘзү©иӘһгҒҜдҪ•еәҰиӘӯгӮ“гҒ§гӮӮиғёгҒҢгҒҷгҒҸгҖӮгҒҢгҖҒз—ӣеҝ«гҒ гҖҒйқўзҷҪгҒ„гҒЁгҒ°гҒӢгӮҠгӮӮиЁҖгҒЈгҒҰгҒ„гӮүгӮҢгҒӘгҒ„гҖӮеқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҒҜгҖҒиҰҒгҒҷгӮӢгҒ«ж•—йҖҖгҒҷгӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖпјҲдёӯз•ҘпјүгҖҺеқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҖҸгҒ®дёӯгҒ®еқҠгҒЈгҒЎгӮғгӮ“гҒЁгҒ„гҒҶдәәзү©гҒҜжҲ–зӮ№гҒҫгҒ§гҒҜж„ӣгҒҷгҒ№гҒҸгҖҒеҗҢжғ…гӮ’иЎЁгҒҷгҒ№гҒҚдҫЎеҖӨгҒ®гҒӮгӮӢдәәзү©гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҚҳзҙ”йҒҺгҒҺгҒҰзөҢйЁ“гҒҢд№ҸгҒ—йҒҺгҒҺгҒҰзҸҫд»ҠгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«иӨҮйӣ‘гҒӘзӨҫдјҡгҒ«гҒҜеҶҶжәҖгҒ«з”ҹеӯҳгҒ—гҒ«гҒҸгҒ„дәәгҒ гҒӘгҒЁиӘӯиҖ…гҒҢж„ҹгҒҳгҒҰеҗҲзӮ№гҒ—гҒ•гҒҲгҒҷгӮҢгҒ°гҖҒгҒқгӮҢгҒ§дҪңиҖ…гҒ®дәәз”ҹиҰігҒҢиӘӯиҖ…гҒ«еҫ№гҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҒҰгӮҲгҒ„гҒ®гҒ§гҒҷгҖӮпјҲгҖҢж–ҮеӯҰи«ҮгҖҚпјү
иҚүгҖҖжһ•
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүж–°е°ҸиӘ¬гҖҖжҳҺжІ»39е№ҙ9жңҲ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүгҖҺй¶үзұ гҖҸжүҖеҸҺгҖҖжҳҺжІ»40е№ҙ1жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖгҖҢгҒ—гҒӨгҒ“гҒ„гҖҒжҜ’гҖ…гҒ—гҒ„гҖҒгҒ“гҒӣгҒ“гҒӣгҒ—гҒҹгҖҒгҒқгҒ®дёҠгҒҡгҒҶгҒҡгҒҶгҒ—гҒ„гҖҒгҒ„гӮ„гҒӘеҘҙгҖҚгҒ§еҹӢгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢдҝ—з•ҢгӮ’и„ұгҒ—гҒҰйқһдәәжғ…гҒ®дё–з•ҢгҒ«йҒҠгҒјгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢз”»е·ҘгҒ®зү©иӘһгҖӮдҪңиҖ…иҮӘиә«гҒ“гӮҢгӮ’гҖҢй–‘ж–Үеӯ—гҖҚгҒЁи©•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢжһңгҒ—гҒҰгҒқгҒҶгҒӢгҖӮдё»дәәе…¬гҒ®иЎҢеӢ•гӮ„зҗҶи«–гҒ®жӮ й•·гҒ•гҒЁгҒҜиЈҸи…№гҒ«гҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгҒ©гҒ“гӮ’еҲҮгҒЈгҒҰгӮӮжјұзҹігҒ®зҶұгҒ„иЎҖгҒҢеҷҙгҒҚеҮәгҒҷдҪ“гҒ®дҪңе“ҒгҒӘгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖгҒҹгҒ гҒҚгӮҢгҒ„гҒ«гҒҶгҒӨгҒҸгҒ—гҒҸжҡ®гӮүгҒҷгҖҒеҚігҒЎи©©дәәзҡ„гҒ«гҒҸгӮүгҒҷгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒҜз”ҹжҙ»гҒ®ж„Ҹзҫ©гҒ®дҪ•еҲҶдёҖгҒӢзҹҘгӮүгҒ¬гҒҢгӮ„гҒҜгӮҠжҘөгӮҒгҒҰеғ…е°‘гҒӘйғЁеҲҶгҒӢгҒЁжҖқгҒҶгҖӮгҒ§гҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдё»дәәе…¬гҒ§гҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮҢгӮӮгҒ„гҒ„гҒҢгӮ„гҒҜгӮҠд»ҠгҒ®дё–з•ҢгҒ«з”ҹеӯҳгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ®гӮҲгҒ„жүҖгӮ’йҖҡгҒқгҒҶгҒЁгҒҷгӮӢгҒ«гҒҜгҒ©гҒҶгҒ—гҒҰгӮӮгӮӨгғ–гӮ»гғіжөҒгҒ«еҮәгҒӘгҒҸгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮпјҲжҳҺжІ»39е№ҙ10жңҲ26ж—ҘгҖҖйҲҙжңЁдёүйҮҚеҗүгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
гҖҖз§ҒгҒ®гҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®дё–й–“жҷ®йҖҡгҒ«гҒ„гҒҶе°ҸиӘ¬гҒЁгҒҜе…ЁгҒҸеҸҚеҜҫгҒ®ж„Ҹе‘ігҒ§жӣёгҒ„гҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе”ҜгҒ дёҖзЁ®гҒ®ж„ҹгҒҳ--зҫҺгҒҸгҒ—гҒ„ж„ҹгҒҳгҒҢиӘӯиҖ…гҒ®й ӯгҒ«ж®ӢгӮҠгҒ•гҒҲгҒҷгӮҢгҒ°гӮҲгҒ„гҖӮгҒқгӮҢд»ҘеӨ–гҒ«дҪ•гӮӮзү№еҲҘгҒӘзӣ®зҡ„гҒҢгҒӮгӮӢгҒ®гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮгҒ•гӮҢгҒ°гҒ“гҒқгҖҒгғ—гғӯгғғгғҲгӮӮз„ЎгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒдәӢ件гҒ®зҷәеұ•гӮӮгҒӘгҒ„гҖӮпјҲдёӯз•Ҙпјү
гҖҖжҷ®йҖҡгҒ«дә‘гҒҶе°ҸиӘ¬гҖҒеҚігҒЎдәәз”ҹгҒ®зңҹзӣёгӮ’е‘ігҒҜгҒӣгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮзөҗж§ӢгҒ§гҒҜгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒеҗҢжҷӮгҒ«гҒҫгҒҹгҖҒдәәз”ҹгҒ®иӢҰгӮ’еҝҳгӮҢгҒҰгҖҒж…°и—үгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶж„Ҹе‘ігҒ®е°ҸиӘ¬гӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒ„гҒЁжҖқгҒҶгҖӮз§ҒгҒ®гҖҺиҚүжһ•гҖҸгҒҜгҖҒз„Ўи«–еҫҢиҖ…гҒ«еұһгҒҷгҒ№гҒҚгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲи«Үи©ұгҖҢдҪҷгҒҢгҖҺиҚүжһ•гҖҸпјү
иҷһзҫҺдәәиҚү
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖжҳҺжІ»40е№ҙ6жңҲ23ж—ҘпҪһ10жңҲ29ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүжҳҺжІ»41е№ҙ1жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖжҳҺжІ»43е№ҙгҖҒжңқж—Ҙж–°иҒһгҒ«е…ҘзӨҫгҒ—гҒҹжјұзҹігҒҢиҒ·жҘӯдҪң家гҒЁгҒ—гҒҰжӣёгҒ„гҒҹ第1дҪңгҖӮжҲ‘ж„ҸгҒЁиҷҡж „гӮ’гҒӨгӮүгҒ¬гҒҸгҒҹгӮҒгҒ«гҒҜе…ЁгҒҰгӮ’зҠ зүІгҒ«гҒ—гҒҰжӮ”гҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зҹҘгӮүгҒ¬и—Өе°ҫгҒ«и¶…дҝ—гҒ®е“ІеӯҰиҖ…з”ІйҮҺгҖҒйҒ“зҫ©гҒ®дәәеүөе®—иҝ‘гӮүгӮ’й…ҚгҒ—гҒҰгҒ“гҒ®гғ’гғӯгӮӨгғігҒ®иҮӘж»…гҒ®жӮІеҠҮгӮ’зөўзҲӣгҒҹгӮӢж–ҮдҪ“гҒ§жҸҸгҒҸгҖӮжјұзҹігҒҜдҝіеҸҘгӮ’дёҖеҸҘдёҖеҸҘйҖЈгҒӯгӮӢгҒҰгҒ„гҒҸгӮҲгҒҶгҒ«ж–Үз« гҒ«иӢҰеҝғгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖгҖҺиҷһзҫҺдәәиҚүгҖҸгҒҜжҜҺж—ҘгҒӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮи—Өе°ҫгҒЁгҒ„гҒҶеҘігҒ«гҒқгӮ“гҒӘеҗҢжғ…гӮ’гӮӮгҒЈгҒҰгҒҜгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮҢгҒҜе«ҢгҒӘеҘігҒ гҖӮи©©зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢеӨ§дәәгҒ—гҒҸгҒӘгҒ„гҖӮеҫізҫ©еҝғгҒҢж¬ д№ҸгҒ—гҒҹеҘігҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгҒ„гҒӨгӮ’гҒ—гҒҫгҒ„гҒ«ж®әгҒҷгҒ®гҒҢдёҖзҜҮгҒ®дё»ж„ҸгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҶгҒҫгҒҸж®әгҒӣгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҠ©гҒ‘гҒҰгӮ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—еҠ©гҒӢгӮҢгҒ°гҒӘгҒҠгҒӘгҒҠи—Өе°ҫгҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜ駄зӣ®гҒӘдәәй–“гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮжңҖеҫҢгҒ«е“ІеӯҰгӮ’гҒӨгҒ‘гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е“ІеӯҰгҒҜдёҖгҒӨгҒ®гӮ»гӮӘгғӘгғјгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеғ•гҒҜгҒ“гҒ®гӮ»гӮӘгғӘгғјгӮ’иӘ¬жҳҺгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«е…ЁзҜҮгӮ’гҒӢгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒӢгӮүжұәгҒ—гҒҰгҒӮгӮ“гҒӘеҘігӮ’гҒ„гҒ„гҒЁжҖқгҒЈгҒЎгӮғгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮе°ҸеӨңеӯҗгҒЁгҒ„гҒҶеҘігҒ®ж–№гҒҢгҒ„гҒҸгӮүеҸҜжҶҗгҒ гҒӢгӮҸгҒӢгӮҠгӮ„гҒ—гҒӘгҒ„гҖӮпјҲжҳҺжІ»40е№ҙ7жңҲ19ж—Ҙе°Ҹе®®иұҠйҡҶгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
дёүеӣӣйғҺ
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖжҳҺжІ»41е№ҙ9жңҲ1ж—ҘпҪһ12жңҲ29ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүжҳҺжІ»42е№ҙ5жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖеӨ§еӯҰе…ҘеӯҰгҒ®гҒҹгӮҒгҒ«д№қе·һгҒӢгӮүдёҠдә¬гҒ—гҒҹдёүеӣӣйғҺгҒҜжқұдә¬гҒ®ж–°гҒ—гҒ„з©әж°—гҒ®гҒӘгҒӢгҒ§гҖҒдё–з•ҢгҒЁдәәз”ҹгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰдёҖгҒӨдёҖгҒӨзөҢйЁ“гӮ’йҮҚгҒӯгҒӘгҒҢгӮүжҲҗй•·гҒ—гҒҰгӮҶгҒҸгҖӮзӯӢжӣёгҒ гҒ‘гӮ’гҒЁгӮҠеҮәгҒӣгҒ°гҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҒҜдёҖиҰӢдҪ•гҒ®еӨүе“ІгӮӮгҒӘгҒ„ж•ҷйӨҠе°ҸиӘ¬гҒЁиҰӢгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒеҚ“и¶ҠгҒ—гҒҹе°ҸиӘ¬гҒ®жҲҰз•Ҙ家жјұзҹігҒҜдёҖзӯӢзё„гҒ§гҒҜиЎҢгҒӢгҒ¬е°ҸиӘ¬зҡ„дјҒгҒҝгӮ’е®ҹгҒҜгҒҹгҒЈгҒ·гӮҠгҒЁд»•жҺӣгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ гҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖйЎҢеҗҚ--гҖҢйқ’е№ҙгҖҚгҖҢжқұиҘҝгҖҚгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҖҢе№ігҖ…ең°гҖҚ
гҖҖеҸігҒ®гҒҶгҒЎеҫЎжҠһгҒҝиў«дёӢеәҰеҖҷгҖӮе°Ҹз”ҹгҒ®гҒҜгҒҳгӮҒгҒӨгҒ‘гҒҹеҗҚгҒҜгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚе°ӨгӮӮе№іеҮЎгҒ«гҒҰгӮҲгӮҚгҒ—гҒҸгҒЁеӯҳеҖҷгҖӮгҒҹгҒ гҒӮгҒҫгӮҠиӘӯгӮ“гҒ§иҰӢгҒҹгҒ„ж°—гҒҜиө·гӮҠз”ігҒҷгҒҫгҒҳгҒҸгҒЁгӮӮиҰҡеҖҷгҖӮ
гҖҖпјҲз”°иҲҺгҒ®й«ҳзӯүеӯҰж ЎгӮ’еҚ’жҘӯгҒ—гҒҰеӨ§еӯҰгҒ«йҖҷе…ҘгҒЈгҒҹдёүеӣӣйғҺгҒҢж–°гҒ—гҒ„з©әж°—гҒ«и§ҰгӮҢгӮӢгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҰеҗҢиј©гҒ гҒ®е…Ҳиј©гҒ гҒ®иӢҘгҒ„еҘігҒ гҒ®гҒ«жҺҘи§ҰгҒ—гҒҰиүІгҖ…гҒ«еӢ•гҒ„гҒҰжқҘгӮӢгҖҒжүӢй–“гҒҜжӯӨз©әж°—гҒ®гҒҶгҒЎгҒ«жҳҜзӯүгҒ®дәәй–“гӮ’ж”ҫгҒҷдёҲгҒ§гҒӮгӮӢгҖҒгҒӮгҒЁгҒҜдәәй–“гҒҢеӢқжүӢгҒ«жіігҒ„гҒ§гҖҒиҮӘгҒӢгӮүжіўзҖҫгҒҢеҮәжқҘгӮӢгҒ гӮҚгҒҶгҒЁжҖқгҒҶпјҲз•ҘпјүпјҲжҳҺжІ»41е№ҙжёӢе·қзҺ„иҖігҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
гҒқгӮҢгҒӢгӮү
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖжҳҺжІ»42е№ҙ6жңҲ27ж—ҘпҪһ10жңҲ14ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүжҳҺжІ»43е№ҙ1жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖиӢҘгҒҚд»ЈеҠ©гҒҜзҫ©дҫ еҝғгҒӢгӮүеҸӢдәәе№іеІЎгҒ«ж„ӣгҒҷгӮӢдёүеҚғд»ЈгӮ’гӮҶгҒҡгӮҠиҮӘгӮүж–Ўж—ӢгҒ—гҒҰдәҢдәәгӮ’зөҗгҒігҒӮгӮҸгҒӣгҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜгҖҢиҮӘ然гҖҚгҒ«гӮӮгҒЁгӮӢиЎҢзӮәгҒ гҒЈгҒҹгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮү3е№ҙгҖҒгҒӨгҒ„гҒ«д»ЈеҠ©гҒҜдёүеҚғд»ЈгҒЁгҒ®ж„ӣгӮ’гҒӨгӮүгҒ¬гҒ“гҒҶгҒЁжұәж„ҸгҒҷгӮӢгҖӮгҖҢиҮӘ然гҖҚгҒ«гҒҜгҒӢгҒӘгҒҶгҒҢгҖҒгҒ—гҒӢгҒ—дәәгҒ®жҺҹгҒ«гҒқгӮҖгҒҸгҒ“гҒ®ж„ӣгҒ«з”ҹгҒҚгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜдәҢдәәгҒҢзӨҫдјҡгҒӢгӮүиҝҪгҒ„ж”ҫгҒҹгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒ—гҒҹгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖиүІгҖ…гҒӘж„Ҹе‘ігҒ«ж–јгҒҰгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҒ«гҒҜеӨ§еӯҰз”ҹгҒ®дәӢгӮ’жҸҸгҒҹгҒҢгҖҒжӯӨе°ҸиӘ¬гҒ«гҒҜгҒқгӮҢгҒӢгӮүе…ҲгҒ®дәӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҹгҒӢгӮүгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҒ®дё»дәәе…¬гҒҜгҒӮгҒ®йҖҡгӮҠеҚҳзҙ”гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒжӯӨдё»дәәе…¬гҒҜгҒқгӮҢгҒӢгӮүеҫҢгҒ®з”·гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүжӯӨзӮ№гҒ«ж–јгҒҰгӮӮгҖҒгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжӯӨдё»дәәе…¬гҒҜжңҖеҫҢгҒ«гҖҒеҰҷгҒӘйҒӢе‘ҪгҒ«йҷҘгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ•гҒҚдҪ•гҒҶгҒӘгӮӢгҒӢгҒҜжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжӯӨж„Ҹе‘ігҒ«ж–јгҒҰгӮӮдәҰгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲгҖҺгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҖҸдәҲе‘Ҡпјү
й–Җ
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖжҳҺжІ»43е№ҙ3жңҲ1ж—ҘпҪһ6жңҲ12ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүжҳҺжІ»44е№ҙ1жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖжЁӘз”әгҒ®еҘҘгҒ®еҙ–дёӢгҒ®жҡ—гҒ„家гҒ§дё–й–“гҒ«иғҢгӮ’гӮҖгҒ‘гҒҰгҒІгҒЈгҒқгӮҠгҒЁгҒ—гҒҰз”ҹгҒҚгӮӢе®—еҠ©гҒЁеҫЎзұігҖӮгҖҢеҪјгӮүгҒҜиҮӘжҘӯиҮӘеҫ—гҒ§гҖҒеҪјгӮүгҒ®жңӘжқҘгӮ’еЎ—жҠ№гҒ—гҒҹгҖҚгҒҢгҖҒдёҖеәҰзҠҜгҒ—гҒҹзҪӘгҒҜгҒ©гҒ“гҒҫгҒ§гӮӮиҝҪгҒЈгҒҰжқҘгӮӢгҖӮеҪјгӮүгӮ’иҘІгҒҶгҖҢйҒӢе‘ҪгҒ®еҠӣгҖҚгҒҢе…ЁзҜҮгӮ’йҖҡгҒҳгҒҰеҫ№еә•гҒ—гҒҹпјңжҳ еғҸпјқиЁҖиӘһпјһгҒ§жҸҸгҒӢгӮҢгӮӢгҖӮгҖҢдёүеӣӣйғҺгҖҚгҖҢгҒқгӮҢгҒӢгӮүгҖҚгҒ«з¶ҡгҒҸдёүйғЁдҪңгҒ®зөӮзҜҮгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖжӢқеҫ©гҖӮи‘үжӣёгӮ’гҒӮгӮҠгҒҢгҒЁгҒҶгҖӮгҖҺй–ҖгҖҸгҒҢеҮәгҒҹгҒЁгҒҚгҒӢгӮүд»Ҡж—ҘгҒҫгҒ§иӘ°гӮӮдҪ•гӮӮгҒ„гҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒҜдёҖдәәгӮӮгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒ§гҒ—гҒҹгҖӮз§ҒгҒҜиҝ‘й ғеӯӨзӢ¬гҒЁгҒ„гҒҶдәӢгҒ«ж…ЈгӮҢгҒҰиҠёиЎ“дёҠгҒ®еҗҢжғ…гӮ’еҸ—гҒ‘гҒӘгҒ„гҒ§гӮӮгҒ©гҒҶгҒӢгҒ“гҒҶгҒӢжҡ®гӮүгҒ—гҒҰиЎҢгҒ‘гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҫ“гҒЈгҒҰиҮӘеҲҶгҒ®дҪңзү©гҒ«еҜҫгҒ—гҒҰиіһиіӣгҒ®еЈ°гҒӘгҒ©гҒҜе…ЁгҒҸдәҲжңҹгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒӣгӮ“гҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҺй–ҖгҖҸгҒ®дёҖйғЁеҲҶгҒҢиІҙж–№гҒ«иӘӯгҒҫгӮҢгҒҰгҖҒгҒқгҒҶгҒ—гҒҰиІҙж–№гӮ’еӢ•гҒӢгҒ—гҒҹгҒЁгҒ„гҒҶдәӢгӮ’иІҙж–№гҒ®еҸЈгҒӢгӮүиҒһгҒҸгҒЁе¬үгҒ—гҒ„жәҖи¶ігҒҢ湧гҒ„гҒҰеҮәгҒҫгҒҷгҖӮпјҲеӨ§жӯЈе…ғе№ҙ10жңҲ12ж—ҘйҳҝйғЁж¬ЎйғҺгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
еҪјеІёйҒҺиҝ„
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖжҳҺжІ»45е№ҙ1жңҲ2ж—ҘпҪһ4жңҲ29ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүеӨ§жӯЈе…ғе№ҙ9жңҲгҖҖжҳҘйҷҪе Ӯ
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®зҹӯз·ЁгӮ’йҖЈгҒӯгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§дёҖзҜҮгҒ®й•·з·ЁгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶжјұзҹіе№ҙжқҘгҒ®ж–№жі•гӮ’е…·дҪ“еҢ–гҒ—гҒҹдҪңгҖӮгҒқгҒ®дёӯеҝғгӮ’гҒӘгҒҷгҒ®гҒҜй Ҳж°ёгҒЁеҚғд»ЈеӯҗгҒ®зү©иӘһгҒ гҒҢгҖҒгғ©гӮӨгғҙгӮЎгғ«гҒ®й«ҳжңЁгҒ«еҜҫгҒҷгӮӢй Ҳж°ёгҒ®е«үеҰ¬гӮ’жјұзҹігҒҜжҜ”йЎһгҒӘгҒ„ж·ұгҒ•гҒ«гҒҫгҒ§жҺҳгӮҠдёӢгҒ’гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«жҲҗеҠҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жҝҖгҒ—гҒ„жғ…еҝөгҒ“гҒқгҒҜжјұзҹіж–ҮеӯҰгҒ«гҒЁгҒЈгҒҰгҒ®ж–°гҒ—гҒ„иӘІйЎҢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜе…ғж—ҘгҒӢгӮүе§ӢгӮҒгҒҰгҖҒеҪјеІёйҒҺиҝ„жӣёгҒҸдәҲе®ҡгҒ гҒӢгӮүеҚҳгҒ«гҒқгҒҶеҗҚд»ҳгҒ‘гҒҹиҝ„гҒ«йҒҺгҒҺгҒӘгҒ„е®ҹгҒҜз©әгҒ—гҒ„жЁҷйЎҢгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӢгҒӯгҒҰгҒӢгӮүиҮӘеҲҶгҒҜеҖӢгҖ…гҒ®зҹӯз·ЁгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹжң«гҒ«гҖҒе…¶гҒ®еҖӢгҖ…гҒ®зҹӯз·ЁгҒҢзӣёеҗҲгҒ—гҒҰдёҖй•·з·ЁгӮ’ж§ӢжҲҗгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«д»•зө„гӮ“гҒ гӮүгҖҒж–°иҒһе°ҸиӘ¬гҒЁгҒ—гҒҰеӯҳеӨ–йқўзҷҪгҒҸиӘӯгҒҫгӮҢгҒҜгҒ—гҒӘгҒ„гҒ гӮҚгҒҶгҒӢгҒЁгҒ„гҒҶж„ҸиҰӢгӮ’жҢҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮгҒҢгҖҒгҒӨгҒ„гҒқгӮҢгӮ’и©ҰгҒҝгӮӢж©ҹдјҡгӮӮгҒӘгҒҸгҒҰд»Ҡж—Ҙиҝ„йҒҺгҒҺгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒӢгӮүгҖҒгӮӮгҒ—иҮӘеҲҶгҒ®жүӢйҡӣгҒҢиЁұгҒҷгҒӘгӮүгҒ°жӯӨгҒ®гҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҖҚгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰгҒ®жҖқгҒҜгҒҸйҖҡгӮҠгҒ«дҪңгӮҠдёҠгҒ’гҒҹгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮпјҲгҖҢеҪјеІёйҒҺиҝ„гҒ«е°ұгҒ„гҒҰгҖҚпјү
иЎҢгҖҖдәә
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖеӨ§жӯЈе…ғе№ҙ12жңҲ6ж—ҘпҪһеӨ§жӯЈ2е№ҙ11жңҲ15ж—ҘпјҲеӨ§жӯЈ2е№ҙ4жңҲ8ж—ҘпҪһ9жңҲ15ж—ҘгҒҫгҒ§дј‘ијүпјү
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүеӨ§жӯЈ3е№ҙ1жңҲгҖҖеӨ§еҖүжӣёеә—
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖеҰ»гҒҠзӣҙгҒЁејҹдәҢйғҺгҒ®д»ІгӮ’з–‘гҒҶдёҖйғҺгҒҜеҰ»гӮ’и©ҰгҒҷгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒдәҢйғҺгҒ«гҒҠзӣҙгҒЁдәҢдәәгҒ§дёҖгҒӨжүҖгҒёиЎҢгҒЈгҒҰдёҖгҒӨе®ҝгҒ«жіҠгҒҫгҒЈгҒҰгҒҸгӮҢгҒЁй јгӮҖвҖҰгҖӮзҹҘжҖ§гҒ®еӯӨзӢ¬ең°зҚ„гӮ’з”ҹгҒҚгҖҒдәәгӮ’дҝЎгҒҳгҒҲгҒ¬дёҖйғҺгҒҜгҖҒгӮ„гҒҢгҒҰгҖҢжӯ»гҒ¬гҒӢгҖҒж°—гҒҢйҒ•гҒҶгҒӢгҖҒгҒқгӮҢгҒ§гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°е®—ж•ҷгҒ«е…ҘгӮӢгҒӢгҖҚгҒЁиЁҖгҒ„еҮәгҒҷгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒе®—ж•ҷгҒ«е…ҘгӮҢгҒ¬гҒ“гҒЁгҒҜеҪ“гҒ®дёҖйғҺгҒҢиӘ°гӮҲгӮҠгӮӮгӮҲгҒҸзҹҘгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
гҒ“гӮқгӮҚ
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖеӨ§жӯЈ3е№ҙ4жңҲ20ж—ҘпҪһ8жңҲ11ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүеӨ§жӯЈ3е№ҙ9жңҲгҖҖеІ©жіўжӣёеә—гҖҖжјұзҹіиҮӘиЈ…
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖгҒ“гҒ®е°ҸиӘ¬гҒ®дё»дәәе…¬гҒ§гҒӮгӮӢгҖҢе…Ҳз”ҹгҖҚгҒҜгҖҒгҒӢгҒӨгҒҰиҰӘеҸӢгӮ’иЈҸеҲҮгҒЈгҒҰжӯ»гҒ«иҝҪгҒ„гӮ„гҒЈгҒҹйҒҺеҺ»гӮ’иғҢиІ гҒ„гҖҒзҪӘгҒ®ж„ҸиӯҳгҒ«гҒ•гҒ„гҒӘгҒҫгӮҢгҒӨгҒӨгҖҒгҒҫгӮӢгҒ§з”ҹе‘ҪгӮ’гҒІгҒҚгҒҡгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҰз”ҹгҒҚгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒЁгҖҒгҒқгҒ“гҒёжҳҺжІ»еӨ©зҡҮгҒҢдәЎгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒеҫҢгӮ’гҒҠгҒЈгҒҰд№ғжңЁеӨ§е°ҶгҒҢж®үжӯ»гҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶдәӢ件гҒҢгҒҠгҒ“гҒЈгҒҹгҖӮгҖҢе…Ҳз”ҹгҖҚгӮӮгҒҫгҒҹжӯ»гӮ’жұәж„ҸгҒҷгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒгҒӘгҒңвҖҰгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
пјҲеүҚз•ҘпјүеҪ“жҷӮгҒ®дәҲе‘ҠгҒ«гҒҜж•°зЁ®гҒ®зҹӯз·ЁгӮ’еҗҲгҒ—гҒҰгҒқгӮҢгҒ«гҖҺеҝғгҖҸгҒЁгҒ„гҒөжЁҷйЎҢгӮ’еҶ гӮүгҒӣгӮӢз©ҚгҒ гҒЁиӘӯиҖ…гҒ«ж–ӯгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒе…¶зҹӯз·ЁгҒ®з¬¬дёҖгҒ«еҪ“гӮӢгҖҺе…Ҳз”ҹгҒ®йҒәжӣёгҖҸгӮ’жӣёгҒҚиҫјгӮ“гҒ§иЎҢгҒҸгҒҶгҒЎгҒ«гҖҒдәҲжғійҖҡгӮҠж—©гҒҸзүҮгҒҢд»ҳгҒӢгҒӘгҒ„дәӢгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҖҒгҒЁгҒҶпјҸпјјгҒқгҒ®дёҖзҜҮдёҲгӮ’еҚҳиЎҢжң¬гҒ«зәҸгӮҒгҒҰе…¬гҒ‘гҒ«гҒҷгӮӢж–№йҮқгҒ«жЁЎж§ҳгҒҢгҒёгӮ’гҒ—гҒҹгҖӮ
гҖҖ然гҒ—жӯӨгҖҺе…Ҳз”ҹгҒ®йҒәжӣёгҖҸгӮӮиҮӘгҒӢгӮүзӢ¬з«ӢгҒ—гҒҹгӮ„гҒҶгҒӘеҸҲй–ўдҝӮгҒ®ж·ұгҒ„гӮ„гҒҶгҒӘдёүеҖӢгҒ®е§үеҰ№зҜҮгҒӢгӮүзө„гҒҝз«ӢгҒҰгӮүгӮҢгҒҰгӮҗгӮӢд»ҘдёҠгҖҒз§ҒгҒҜгҒқгӮҢгӮ’гҖҺе…Ҳз”ҹгҒЁз§ҒгҖҸгҖҒгҖҺдёЎиҰӘгҒЁз§ҒгҖҸгҖҒгҖҺе…Ҳз”ҹгҒЁйҒәжӣёгҖҸгҒЁгҒ«еҢәеҲҘгҒ—гҒҰгҖҒе…ЁдҪ“гҒ«гҖҺеҝғгҖҸгҒЁгҒ„гҒөиҰӢеҮәгҒ—гӮ’д»ҳгҒ‘гҒҰгӮӮе·®ж”ҜгҒҲгҒӘгҒ„гӮ„гҒҶгҒ«жҖқгҒӨгҒҹгҒ®гҒ§гҖҒйЎҢгҒҜе…ғгҒ®е„ҳгҒ«гҒ—гҒҰзҪ®гҒ„гҒҹгҖӮгҒҹгӮһдёӯе‘ігӮ’дёҠдёӯдёӢгҒ«д»•еҲҮгҒӨгҒҹдёҲгҒҢгҖҒж–°иҒһгҒ«еҮәгҒҹжҷӮгҒЁгҒ®зӣёйҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ
гҖҖиЈ…е№ҖгҒ®дәӢгҒҜд»Ҡиҝ„е°Ӯй–Җ家гҒ«гҒ°гҒӢгӮҠдҫқй јгҒ—гҒҰгӮҗгҒҹгҒ®гҒ гҒҢгҖҒд»ҠеәҰгҒҜгҒөгҒЁгҒ—гҒҹеӢ•ж©ҹгҒӢгӮүиҮӘеҲҶгҒ§йҒЈгҒӨгҒҰиҰӢгӮӢж°—гҒ«гҒӘгҒӨгҒҰгҖҒз®ұгҖҒиЎЁзҙҷгҖҒиҰӢиҝ”гҒ—гҖҒжүүеҸҠгҒіеҘҘйҷ„гҒ®жЁЎж§ҳеҸҠгҒійЎҢеӯ—гҖҒжңұеҚ°гҖҒжӨңеҚ°гҒЁгӮӮгҒ«гҖҒжӮүгҒҸиҮӘеҲҶгҒ§иҖғжЎҲгҒ—гҒҰиҮӘеҲҶгҒ§жҸҸгҒ„гҒҹгҖӮпјҲеҫҢз•ҘпјүпјҲгҖҺеҝғгҖҸиҮӘеәҸпјү
гҖҖгҒӮгҒ®гҖҺеҝғгҖҸгҒЁгҒ„гҒҶе°ҸиӘ¬гҒ®гҒӘгҒӢгҒ«гҒӮгӮӢе…Ҳз”ҹгҒЁгҒ„гҒҶдәәгҒҜгӮӮгҒҶжӯ»гӮ“гҒ§гҒ—гҒҫгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮеҗҚеүҚгҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒҷгҒҢиҰҡгҒҲгҒҰгӮӮеҪ№гҒ«з«ӢгҒҹгҒӘгҒ„дәәгҒ§гҒҷгҖӮгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜе°ҸеӯҰгҒ®е…ӯе№ҙгҒ§гӮҲгҒҸгҒӮгӮ“гҒӘгӮӮгҒ®гӮ’гӮҲгҒҝгҒҫгҒҷгҒӯгҖӮгҒӮгӮҢгҒҜе°ҸдҫӣгҒҢгӮҲгӮ“гҒ§гҒҹгӮҒгҒ«гҒӘгӮӢгӮӮгҒ®гҒҳгӮғгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгӮүгҒҠгӮҲгҒ—гҒӘгҒ•гҒ„гҖӮпјҲеҫҢз•ҘпјүпјҲеӨ§жӯЈпј“е№ҙ4жңҲ24ж—Ҙжқҫе°ҫеҜӣдёҖгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
йҒ“гҖҖиҚү
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖеӨ§жӯЈ4е№ҙ6жңҲ3ж—ҘпҪһ9жңҲ14ж—Ҙ
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүеӨ§жӯЈ4е№ҙ10жңҲгҖҖеІ©жіўжӣёеә—
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҢйҒ“иҚүгҖҚгҒҜжјұзҹіе”ҜдёҖгҒ®иҮӘдјқе°ҸиӘ¬гҒ гҒЁгҒҷгӮӢиҰӢж–№гҒҜгҒ»гҒје®ҡиӘ¬гҒ гҒЁгҒ„гҒЈгҒҰгӮҲгҒ„гҖӮгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎгҖҒгҖҢеҗҫиј©гҒҜзҢ«гҒ§гҒӮгӮӢгҖҚеҹ·зӯҶеүҚеҫҢгҒ®жјұзҹіиҮӘиә«гҒ®е®ҹдҪ“йЁ“гӮ’гҖҢзӣҙжҺҘгҒ«гҖҒиөӨиЈёгҖ…гҒ«иЎЁзҸҫгҖҚгҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢе®ҹдҪ“йЁ“гҒҢгҒ©гҒҶгҒ„гҒҶйҒҺзЁӢгҒ§дҪңе“ҒеҢ–гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгӮ’иҝҪжұӮгҒ—гҒҰгӮҶгҒҸгҒЁгҖҒгҒ“гҒ®дҪңе“ҒгҒҢз§Ғе°ҸиӘ¬зі»зөұгҒ®ж–ҮеӯҰгҒЁгҒҜе…ЁгҒҸиіӘгӮ’з•°гҒ«гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгӮӢгҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
жҳҺгҖҖжҡ—
пјҲеҲқгҖҖеҮәпјүжңқж—Ҙж–°иҒһгҖҖеӨ§жӯЈ5е№ҙ5жңҲ26ж—ҘпҪһ12жңҲ14ж—ҘпјҲеӨ§йҳӘжңқж—Ҙж–°иҒһгҒҜгҖҒдј‘ијүгӮ’гҒҜгҒ•гҒҝгҖҒ12жңҲ27ж—ҘгҒҫгҒ§пјүгҖҖжјұзҹігҒ®жӯ»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰйҖЈијү188еӣһгҒ§дёӯзө¶гҖҒжңӘе®Ң
пјҲеҚҳиЎҢжң¬пјүеӨ§жӯЈ6е№ҙ1жңҲгҖҖеІ©жіўжӣёеә—
пјҲеҶ…гҖҖе®№пјү
гҖҖдё»дәәе…¬жҙҘз”°гҒЁгҒқгҒ®еҰ»гҒҠ延гҒ®з”ҹгҒҚж–№гӮ’дёӯеҝғгҒЁгҒ—гҒҰгӮЁгӮҙгӮӨгӮәгғ гҒ®е•ҸйЎҢгҒ«е®№иөҰгҒӘгҒҸе…үгӮ’гҒӮгҒҰгҒҹгҖҢжҳҺжҡ—гҖҚгҒҜжјұзҹігҒҢз”ҹж¶ҜгҒ®жңҖеҫҢгҒ«еҲ°йҒ”гҒ—гҒҹжҖқжғігҖҢеүҮеӨ©еҺ»з§ҒгҖҚгҒ®ж–ҮеӯҰзҡ„е®ҹи·өгҒ гҒЈгҒҹгҖӮдҪңиҖ…гҒ®жӯ»гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжңӘе®ҢгҒ«зөӮгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжғіеғҸеҠӣиұҠгҒӢгҒ«дҪңе“ҒгҒ®ж§ӢйҖ гӮ’иӘӯгҒҝгҒЁгҒҸгҒ“гҒЁгҒ§гҖҢжҳҺжҡ—гҖҚгҒ®гҖҢгҒқгҒ®еҫҢгҖҚгӮ’иҖғгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜеҝ…гҒҡгҒ—гӮӮдёҚеҸҜиғҪгҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҖӮпјҲеІ©жіўж–Үеә«и§ЈиӘ¬гӮҲгӮҠпјү
пјҲиҮӘдҪңгҒёгҒ®иЁҖеҸҠпјү
гҖҖгҒӮгҒӘгҒҹгҒҜгҒҠ延гҒЁгҒ„гҒҶеҘігҒ®жҠҖе·§зҡ„гҒӘиЈҸгҒ«дҪ•гҒӢгҒ®ж¬ йҷҘгҒҢжҪңгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«жҖқгҒЈгҒҰиӘӯгӮ“гҒ§гҒ„гҒҹгҖӮ然гӮӢгҒ«гҖҒгҒқгҒ®гҒҠ延гҒҢдё»дәәе…¬гҒ®ең°дҪҚгҒ«з«ӢгҒЈгҒҰиҮӘз”ұгҒ«иҮӘеҲҶгҒ®еҝғзҗҶгӮ’иӘ¬жҳҺгҒ—еҫ—гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дәҲжңҹйҖҡгӮҠгҒ®гӮӮгҒ®гҒҢеҮәгҒҰжқҘгҒӘгҒ„гҖӮгҒқгӮҢгҒ§гҒӮгҒӘгҒҹгҒҜз§ҒгҒ«еҗ‘гҒЈгҒҰгҖҒгҖҢеҗӣгҒҜдҪ•гҒ®гҒҹгӮҒгҒ«дё»дәәе…¬гӮ’еӨүгҒҲгҒҹгҒ®гҒӢгҖҚгҒЁгҒ„гҒ„гҒҹгҒҸгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒ§гҒҜгҒӮгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҒӢгҖӮ
гҖҖгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дәҲжңҹйҖҡгӮҠеҘідё»дәәе…¬гҒ«гӮӮгҒЈгҒЁеӨ§иўҲиЈҹгҒӘеҮ„гҒҫгҒҳгҒ„ж¬ йҷҘгӮ’жӢөгҒҲгҒҰе°ҸиӘ¬гҒ«гҒҷгӮӢдәӢгҒҜз§ҒгӮӮжүҝзҹҘгҒ—гҒҰгҒ„гҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—з§ҒгҒҜгӮҸгҒ–гҒЁгҒқгӮҢгӮ’еӣһйҒҝгҒ—гҒҹгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮдҪ•ж•…гҒЁгҒ„гҒҶгҒЁгҖҒгҒқгҒҶгҒҷгӮӢгҒЁгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢе°ҸиӘ¬гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ—гҒҫгҒЈгҒҰз§ҒгҒ«гҒҜпјҲйҷіи…җгҒ§пјүйқўзҷҪгҒҸгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮүгҒ§гҒҷгҖӮз§ҒгҒҜгҒӮгҒӘгҒҹгҒ®дҫӢгҒ«еј•гҒӢгӮҢгӮӢгғҲгғ«гӮ№гғҲгӮӨгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒҶгҒҫгҒҸгҒқгӮҢгӮ’д»•йҒӮгҒ’гӮӢдәӢгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒӢгӮӮзҹҘгӮҢгҒҫгҒӣгӮ“гҒҢгҖҒз§ҒзӣёеҝңгҒ®еҠӣгҒ§гҖҒгҒқгӮҢгӮ’и©ҰгҒҝгҒ гҒ‘гҒ®дәӢгҒӘгӮүгҖҒпјҲгӮӮгҒ—гғҲгғ«гӮ№гғҲгӮӨжөҒгҒ§гӮӮж§ӢгӮҸгҒӘгҒ„гҒЁгҒ•гҒҲжҖқгҒҲгҒ°пјүгҖҒйҒЈгӮҢгӮӢгҒ гӮҚгҒҶдҪҚгҒ«е·ұжғҡгӮҢгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮпјҲеӨ§жӯЈ5е№ҙ7жңҲ19ж—ҘеӨ§зҹіжі°и”өгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү
пјҲеүҚз•Ҙпјүеғ•гҒҜгҒӮгҒ„гҒӢгӮҸгӮүгҒҡгҖҺжҳҺжҡ—гҖҸгӮ’еҚҲеүҚдёӯжӣёгҒ„гҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеҝғжҢҒгҒҜиӢҰз—ӣгҖҒеҝ«жҘҪгҖҒеҷЁжў°зҡ„гҖҒгҒ“гҒ®дёүгҒӨгӮ’гҒӢгҒӯгҒҰгҒ„гҒҫгҒҷгҖӮеӯҳеӨ–ж¶јгҒ—гҒ„гҒ®гҒҢдҪ•гӮҲгӮҠд»•еҗҲгҒӣгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгӮҢгҒ§гӮӮ жҜҺж—Ҙзҷҫеӣһиҝ‘гҒҸгӮӮгҒӮгӮ“гҒӘдәӢгӮ’жӣёгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁеӨ§гҒ„гҒ«дҝ—дәҶгҒ•гӮҢгҒҹеҝғжҢҒгҒ«гҒӘгӮҠгҒҫгҒҷгҒ®гҒ§дёүгҖҒеӣӣж—ҘеүҚгҒӢгӮүеҚҲеҫҢгҒ®ж—ҘиӘІгҒЁгҒ—гҒҰжјўи©©гӮ’дҪңгӮҠгҒҫгҒҷгҖӮж—ҘгҒ«дёҖгҒӨдҪҚгҒ§гҒҷгҖӮгҒқгҒҶгҒ—гҒҰдёғиЁҖеҫӢи©©гҒ§гҒҷгҖӮеҺӯгҒ«гҒӘгӮҢгҒ°гҒҷгҒҗе·ігӮҒгӮӢгҒ®гҒ гҒӢгӮүгҒ„гҒҸгҒӨеҮәжқҘгӮӢгҒӢеҲҶгӮҠгҒҫгҒӣгӮ“гҖӮпјҲеӨ§жӯЈ5е№ҙ8жңҲ21ж—Ҙд№…зұіжӯЈйӣ„гғ»иҠҘе·қйҫҚд№Ӣд»ӢгҒӮгҒҰжӣёз°Ўпјү