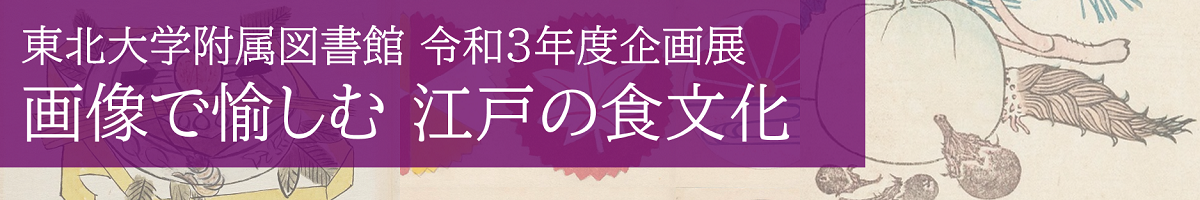
江戸時代は、茶屋から発展した料理茶屋が出現するなど、日本料理に躍進が見られた時期です。今もよく食べられ和食を代表する食材の一つである漬物のレシピが刊行されたり、料理やお菓子の材料として欠かせない砂糖の製造に力が入れられるなど、こうした現在にも続く日本料理にちなんだ資料もあわせて、第2部で紹介します。
現在までその名の残る料亭・八百善(やおぜん)の創業者による料理本。4巻からなり、各巻で本膳、精進料理、卓袱(しっぽく)料理などについて紹介している。上方(かみがた)から長崎へと取材が行われたことも述べられている。本書は大変評判となり、追随して多くの料理や菓子に関する書物が出版されるほどであった。
著者は江戸の漬物問屋主人。たくあん漬け、浅漬け、梅干し漬けなど64種の漬物の作り方が記されている。序には「あらましをあぐるのみ」とあるが、現在でも利用できる製法が詳細に記述されている。
著者は幕府の命により、紀伊の安田泰という人物から砂糖製作を学び、この書を記したという。「甘蔗(かんしゃ)」すなわちサトウキビの栽培にはじまり、収穫したサトウキビから汁をしぼり、煮詰めて砂糖にするまでの手順が示されている。挿絵には、人力でサトウキビを圧搾している様子(画像2)や、水車を用いた図、そのほか製糖に用いる道具等が描かれている。